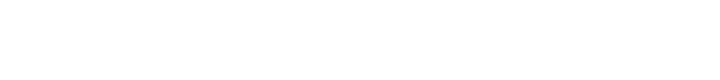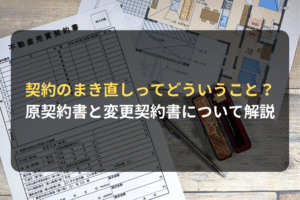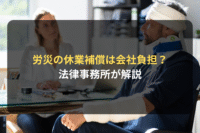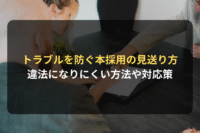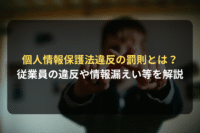- 2025.04.25
労災の休業補償は会社負担?法律事務所が解説
経営者の皆さまは、どんなに気をつけていても時として起こる労働災害、略して「労災」については、どのくらい知識をお持ちでしょうか。
特に、従業員が労災のために休業することとなった場合は、より問題は深刻です。
一労働者である従業員は、突然に働けなくなったことで、明日からの生活に不安を抱くこととなります。
事業主として適切な負担をすることは、法律を遵守する上でも、従業員との信頼関係を築く上でも、とても大切なことなのです。
「従業員がケガで休業することになった。事業主の対応としては、どんなことをすればいい?」
「労災保険の制度は、どうなっているのか?」
「従業員が労災で休業中に支払わなければならないものは?」
「会社の負担が必要なことはわかったが、補償すべき金額の基準や計算方法がわからない」
「通勤災害の場合はどうなるのだろう?」
この記事では、そのような経営者の皆さまのお悩みを解決するために、労災の休業補償における会社の負担についてわかりやすく解説します。
目次
労災における休業補償とは?
休業(補償)給付
まずは、国の労災補償制度についてみていきましょう。
従業員を雇用している事業主には、国の労災保険に加入する義務があります。
仕事または通勤が原因でのケガや病気で働けず休業した場合、労働者が労働基準監督署に申請をして認められれば、労災保険から休業(補償)給付が支給されます(労災保険法第14条)。
休業(補償)給付は休業4日目以降から支給され、最初の休業から3日間は後述する「待期期間」にあたり、休業(補償)給付の支給対象外です。
〈労災の休業(補償)給付の支給要件〉
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
(労災保険法第14条第1項)
なお、労働者が労災保険を請求せずに会社が休業補償を全額負担することもできますが、あくまで労働者自身の意思に基づくものであることが必要です。また、その場合も、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出して労災事故の発生を報告する義務があります。
会社が労災事故の発生を隠蔽しているとみられると、「労災かくし」として罪に問われる可能性がありますので、労働者死傷病報告の提出は必ず行うようにしてください。
| 参考情報:休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続 |厚生労働省 参考情報:「労災かくし」は犯罪です。|厚生労働省 |
待期期間について
休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありません。この3日間のことを「待期期間」といいます。待期期間は、業務災害の場合、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うと定められています(労働基準法第76条)。
待期期間では、会社所定の休日も期間日数にカウントされます。たとえば、土日が休日である会社において、労働者が金曜日の所定労働時間中にケガをし働けなくなった場合、金曜日を初日として、金土日の3日間を待期期間として数えます。なお、ケガの初日に最後まで仕事をやり終えたり、ケガをしたのが残業中であったなど、所定労働時間の終了まで働いていた場合は、その翌日が休業日の初日になります。
待期期間は連続している必要はありません。休業日が断続していても、初日から数えて通算3日目までを待期期間として数えます。
通勤災害の場合は?
労災保険の休業補償制度では、業務災害に対する給付を「休業補償給付」、通勤災害に対する給付を「休業給付」といいます。両方を合わせて「休業(補償)給付」と表記されることが一般的です。
通勤災害の場合は、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。
会社が休業補償を負担する義務はありませんが、一定の要件を満たし通勤災害と認定されれば、労働者は休業4日目以降、労災保険からの休業給付を受けることができます。
休業(補償)給付の計算方法
休業1日につき、給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。
給付基礎日額とは、労働基準法上の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、原則として、労災事故が発生した日(賃金締切日がある場合は、事故直前の賃金締切日)の直前3か月間に被災労働者に支払われた賃金の総額(ボーナスなどの臨時収入は除きます)を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額です(労働基準法第12条)。
従業員が労災で休業した場合の会社の負担は?
待期期間の場合
前述のとおり、待期期間では、業務災害について事業主に平均賃金の60%の休業補償を行う責任があります。
ただし、これは労働基準法が定めた最低ラインであり、一般的には100%の補償を行う会社が多いでしょう。これは、従業員の生活保障という目的以外にも、「従業員が働けなくなったことについて会社に責任がある場合には賃金の全額を支払わなければならない」という民法上の考え方に基づくものです(民法536条2項参照)。
会社には従業員の安全に配慮する義務があるため、労災が起こるということは、基本的には会社に責任があると考えられます。従業員の過失が大きく会社に全く非がないといえる場合や、就業規則等に別段の定めがある場合以外は、100%の休業補償をしておくことが望ましいでしょう。
症状が重く、また治療が長引けば長引くほど、被災した労働者としては「会社のために頑張ってきた自分がなぜ…」という思いになりがちです。後々トラブルにならないためにも、そういった労働者の心情に十分配慮しつつ、適切な初期対応を行うことが重要となります。「会社がきちんと対応をしてくれた」と思ってもらうことは、労働者を就労意欲や信頼を損なうことなくスムーズに復帰へと導くばかりでなく、従業員全体との信頼関係の構築や、ひいては世間から見た企業の社会的評価にまでつながっていくといえましょう。
休業4日目以降の場合
休業4日目以降は、労災保険から休業(補償)給付が支給されます。
前述の考え方からは、ここでも会社としては休業(補償)給付で足りない部分について負担をすることが望ましいといえます。
1-4で述べたように、労災保険からは1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。
休業特別支給金は、被災労働者の社会復帰促進の目的で労働福祉事業から保険給付に上乗せして支給されるものであり、保険給付とは性質の違うものです。したがって、保険給付60%だけを除いた残り40%について負担をする会社もあります。
なお、健康保険の傷病手当金は会社が何%かの賃金を支払えばその分減額されますが、労働保険の場合は減額されず、満額支給されます。60%以上を支払うと、1-1で述べた〈労災の休業(補償)給付の支給要件〉の「③賃金を受けていないこと」の要件を満たさなくなるので注意が必要ですが、60%未満であれば会社が負担しても保険給付からは満額支給される、ということになります。
もっとも、他の従業員との公平性を考え、最大でも40%の負担にとどめておくのがよいでしょう。
休業が長引く場合は?
会社がいつまで休業補償の負担をするというきまりはありません。一般的には、労働基準監督署で何らかの決定が行われたタイミングで、その結果をふまえて会社として判断するケースが多いでしょう。
おうおうにして休業期間は長引くことも多く、労働基準監督署でも補償打ち切りの判断が難しいケースが多々あるようです。会社にとっても同様に、いつまで休業補償を支払うかは大変悩ましい問題となります。
このようなことでお悩みの際は、ぜひ、専門家にご相談ください。ケースに合わせた最適なアドバイスを行います。
会社が給付金を立て替えて支払う場合
労災保険には、受任者払い制度というものがあります。
労災保険が支給決定されるまでには約1か月程度、事案によってはもっと長くかかるケースもあります。受任者払い制度は、会社が従業員に対し、休業(補償)給付に相当する額を立て替え払いをすることで、早期に生活の安定を図る制度です。
立て替え払いをするときは、会社が従業員から保険給付の受領を委任されている旨の委任状を作成し、休業(補償)給付の請求書とともに受任者払申請書及び委任状を提出します。受任者払申請書及び委任状を提出することで、従業員に支給される休業(補償)給付を会社の指定する口座に振り込んでもらうことができます。
受任者払申請書及び委任状の書式は、各都道府県労働局によって異なります。管轄の労働局または労働基準監督署に問い合わせて入手しましょう。
従業員を雇用したら労働保険に加入しておこう
労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といいます。建設業等では多少取扱いが異なりますが、通常は、これらは同じ機会に加入手続きを行います。
事業主は、一日でも従業員を雇用した場合、それがアルバイトやパートタイマー等であっても労災保険に加入手続きを行う義務があります。雇用保険の場合は、一定の要件を満たし雇用保険の対象となる従業員を雇用した場合に義務が発生します。従業員を雇用した場合は、その他の手続きとともに、労働保険加入の手続きも忘れず行ってください。
ところで、労災保険に未加入の会社で労災事故が起こった場合、保険は給付されるのでしょうか?
事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合も、被災した労働者には保険が給付されます。また、その際には労働基準監督署の調査が行われ、遡って保険料が徴収される他、保険給付金の 100%又は40%を徴収されることになり、事業主にとっては大変大きな負担となります。
| 参考情報:厚生労働省:成立手続を怠っていた場合は |
このようなことが起こらないよう、従業員を雇用することになったらすぐに労働保険の加入手続きを行い、労働保険料をきちんと納付しましょう。ご不明の点は、専門家にご相談ください。
労災が起こったときの会社負担についてのお悩み・課題は解決できます
しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、労災を含む会社の諸問題を解決してきた実績があります。
また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。
当事務所にご依頼いただくことで、
「従業員に労災が発生したときに、会社がなすべきことについて、理由とともにポイントをおさえた説明が受けられる」
「労災保険の申請についてもわかりやすく教えてもらえる」
「従業員に対しても、十分な説明が可能となり、安心が得られる」
「専門家のトータルサービスを受けながら手続きができるので、会社としても先を見据えたスピーディーな対応ができる」
「判断が難しく悩ましいケースについても、会社の立場に立った多面的なアドバイスが受けられる」
さらに、
「会社が適切な費用負担をすることで従業員の仕事復帰までをきちんとサポートでき、従業員の信頼を得て会社の結束が高まる」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは
「突然労災が発生し時間の余裕もなく困っていたが、会社が次にとるべき対応についてこちらの立場に立ったアドバイスがもらえ、安心して手続きを進めることができた」
「従業員へも丁寧な説明ができ、突然の労災に遭って不安になっていた従業員に安心と信頼を与え以前より良好な関係を構築することができた」
「知らなければ損をしていたかもしれないさまざまな制度について、一覧でまとめて紹介するなどわかりやすく教えてもらえ、請求漏れの心配がなくなった」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する経営者の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせください。
こちらから「メールでスピード相談」ができます。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解の上、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、是非専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」