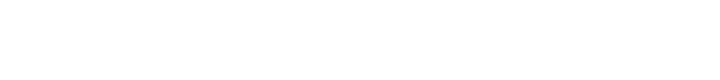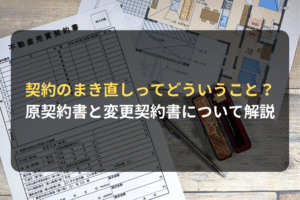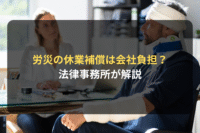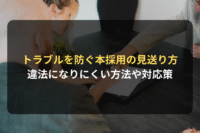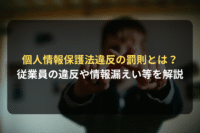- 2024.11.19
自社株の相続でトラブルを防ぐためには?株式承継・事業承継の5つの対策を弁護士がわかりやすく解説
自社株の相続について、経営者の皆さまは、下記のようなお悩みがあるのではないでしょうか。
「相続のときに家族で揉めたり、会社がバラバラになったりしないだろうか?」
「後継ぎはこのままで本当に大丈夫なんだろうか?」
「株が分散して、経営の決定権が弱くなったらどうしよう?」
「相続税が高くて、家族や会社が困ることにならないだろうか?」
「遺言や贈与って、どうすれば一番良い形で使えるんだろう?」
「法律とか税金のこと、ちゃんと理解できているんだろうか?」
「相続の問題が従業員や取引先に悪い影響を与えたりしないかな?」
この記事では、このようなお悩みを解決できるように、自社株の相続について、経営者の皆さまが知っておきたい問題点と、5つの対策を、わかりやすく解説します。
目次
自社株式の相続とは?
会社を後継者に相続させる際、具体的には何を相続させるのでしょうか。
会社法第3条には、「会社は、法人とする。」と規定されており、会社は法人格を持ち、自分の名前で財産を持つ(所有権の主体となる)ことが可能です。
たとえば、会社が不動産を所有している場合、その不動産は会社固有の持ち物であり、経営者から後継者に事業のバトンタッチが行われた場合でも、持ち主は会社のままとなります。
※同様に、会社が銀行などからお金を借りている場合、経営者から後継者に事業のバトンタッチが行われた場合でも、借主は会社のままです(だだし、たとえば、前経営者が借入金の連帯保証人になっているようなケースでは、後継者が連帯保証人を引き継ぐことを求められる場合があります。
会社を後継者に相続させる場合、主に問題となるのは株式です。会社法には、株式を持つ人(株主)の権利について規定されています。株主に認められている権利の1つに「株主総会における議決権」があります。(会社法第105条3項)
つまり、株主総会で議案に対して賛成・反対を投票する権利が株主には認められているのです。また、会社法では株主総会の決議要件についても規定されており、法令や定款に別段の定めがある場合を除き、「議決権の過半数を有する株主の出席」「出席した株主の議決権の過半数の賛成または反対」が要件となります。(会社法第309条1項)
株主総会では、定款に一定の定めがある取締役会設置会社を除き、株式会社の組織・運営・管理・その他株式会社に関する一切の事項を決議することが可能です。株式会社の株主は会社の経営に関する議決権(決定権)を持ちます(会社法第295条)。経営者が持つ自社株(自社が発行した株式)は、会社を相続する際の重要な財産であると考えられます。
前述した決議要件を満たすように、自社株を後継者が所有することで、会社の組織・運営・管理等について経営者として決定していくことが可能となります。
なお、自社株式と似た言葉で自己株式というものがあります。自社株式は会社が発行した株式全体を指しますが、一方で、自己株式は一度株主の手に渡った株式を、会社が株主から買い戻したものです。自己株式の持ち主は会社であり、会社は自己株式について議決権の行使、配当金の受け取りといった権利を行使することはできません。
- 事業承継の種類(方法)
-
事業承継とは、その名の通り、経営者の引退に伴い、会社の思いや技術を次の世代に引き継ぐことを指します。
中小企業の経営者は高齢化が進んでおり、経営年齢のピークはこの2000年からの20年間で、50代から60~70代へと大きく上昇しています。さらには、後継者不在率の上昇、廃業予定企業が挙げる廃業理由の3割を「後継者不足」が占めるということもあり、事業承継は中小企業にとって大きな課題です。
一方で、事業承継をした会社は3年目以降、売上高成長率が同業同種平均を上回り、事業承継時の経営者の年齢が若い会社ほど、事業再構築への取り組みに意欲的というデータもあります。
上記のことから、会社の思いや技術を未来につなげるためには、事業承継は重要なテーマであるといえます。
事業承継は、引継ぎ先によって親族内承継・従業員承継・M&A(社外への引継ぎ)の3つの類型に分類できます。
下記の一覧表に、各類型の概要やメリット・デメリットの一例をまとめています。ご参照ください。
類型
引継ぎ先
メリット
デメリット
親族内承継
現経営者の子をはじめとした親族に承継
・本人や従業員の心の準備期間の確保がしやすい
・相続等による株式の後継者移転の後継者
・現経営者が個人保証を行っている(融資の連帯保証人になっている)という場合には、その保証を外し、後継者に引継ぐ必要がある
・「2.自社株の相続に関する問題点」にて解説します
従業員承継
親族以外の従業員に承継
・経営能力のある人材を見極めて承継が可能
・長期間働いてきた従業員であれば、経営方針等の一貫性を期待することが可能
・現経営者が個人保証を行っている(融資の連帯保証人になっている)という場合には、その保証を外し、後継者に引継ぐ必要がある
・前経営者の経営方針を踏襲するため、新たな取り組みに対して消極的になってしまうケースがある
M&A
(社外への引継ぎ)
社外の第三者(起業や創業希望者等)への株式譲渡・事業譲渡により承継
・親族や社内に適任者がいない場合でも、広く候補者を求めることが可能
・現経営者は会社売却の利益を得ることが可能
・従業員の理解を得ることが難しく、人材の流出につながる可能性がある
・取引先の理解を得ることが難しい場合がある
・売却益に対して税金が発生する
出典:「事業承継を知る」(中小企業庁)(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/know_business_succession.html)を加工して作成
自社株の相続に関する問題点
後継者とその他の相続人によるトラブル
自社株を後継者に相続させる場合に問題となるのが遺留分です。経営者が自己の財産(自社株)をどのように相続するのかは自由ですが、民法では遺族の生活の安定、最低限度の相続人間の平等のため、相続人(兄弟姉妹を除く。)に対して「遺留分」という、最低限の「相続する権利」を保証しています。
自己の相続分が遺留分を下回った(遺留分を侵害された)場合、その相続人は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求めることが可能です(民法第1042条)。
経営者が亡くなり、2人の子供(A・B)が相続をするケースを想定してみましょう。経営者の財産(評価額)は、自社株 2,000万円とします。
通常の場合、自社株を1,000万円ずつ、等しい割合で相続します。
しかし、亡くなった経営者がAを後継者とし、自社株の全てをAが相続した場合、Bには相続する財産が亡くなってしまいます。
ここで問題となるのが遺留分です。Bは法定相続分(1,000万円)の1/2である、500万円の遺留分を相続する権利があります。ですから、BはAに対し「Aだけが遺産を相続することは不公平だ!私には最低でも500万円を相続する権利があるのだから、500万円を私に支払ってください!」と請求することができるのです。これを、遺留分侵害額請求といいます。
その場合、Aは会社を継ぐ(自社株を相続する)ためにBに対して500万円を支払う必要がありますが、相続財産は自社株のみのため、500万円は自らの資金で支払わなければならず、Aの金銭的な負担が過大となります。また、遺留分の支払いが難しいため、結果的に自社株や事業用資産を手放し、自社株(議決権)が分散することによる経営の混乱、円滑な事業承継の妨げが生じる可能性もあります。
上記のような遺留分による問題は、亡くなった経営者が遺言書を作成していない場合にも生じる可能性があります。遺言書がないことにより、相続割合は法定通りとなり、株式が相続人に平等に分配されると、後継者は経営権を確保するために、他の相続人の株式を買い取る必要がでてきます。
後継者の相続税の負担が大きい
非上場企業の自社株を相続する際には、まずは自社株にどの程度の金銭的価値があるのかを客観的に把握する必要があります。方法としては、財産評価基本通達に従って自社株の評価を行い、相続税評価額を算出します。この相続税評価額に応じて、相続税をいくら支払うのかが決定されるのです。
具体的には、会社が相続税法上の大会社・中会社・小会社のいずれに該当するかを特定します(財産評価基本通達178)。さらに、特定した会社の区分に応じた評価方法により、相続税評価額を算出します。下記の一覧表に、各評価方法の概要を簡単に記載します。ご参照ください。
|
会社規模 |
評価方法 |
概要 |
|
大会社 |
原則 類似業種比準価格による評価 |
自社と類似する業種の株価・自社の配当金額・利益金額・純資産価格等を参考に、自社の株価を計算する方法 |
|
中会社 |
類似業種比準価格と純資産価格による併用 |
財産評価基本通達により定められた割合で、類似業種比準価格と純資産価格による評価を併用する方法 |
|
小会社 |
原則 純資産価格による評価 |
自社の保有する資産から、債務や税金等を差引き、純資産額を算出。純資産額を株式数で割り、1株当たりの価格を算出する方法 |
出典:「気配相場等のある株式の評価」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/02.htm#a-178 )を加工して作成
|
相続税の速算表 |
||
|
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
- |
|
1,000万円超から3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
3,000万円超から5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
5,000万円超から1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
1億円超から2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
2億円超から3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
3億円超から6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
出典:「No.4155 相続税の税率」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)
こちらは、相続税の目安となる速算表ですが、後継者が相続税評価額2,000万円の自社株式を相続した場合、
2,000万円×15%(相続税率)=300万円
300万円-50万円(控除額)=250万円
250万円の相続税の支払い義務が後継者に生じます(相続税の基礎控除を考慮する必要はあります)。相続税の支払いが難しい場合に、自社株を売ろうとしても、非上場株式は換金性に乏しく、また換金する(自社株を第三者の売却する)ことにより経営権が分散するおそれがあります。
後継者の負担を減らし、経営権の分散を防止するためにも、自社株の相続を考える際には、相続税対策が必要不可欠であるといえます。
自社株の相続税対策5つ
定款の変更で株式の分散を防ぐ
会社の定款を変更することにより、株式(議決権)の分散を防ぐ方法について解説します。
まずは、「相続人等に対する売渡しの請求」に関して定款に定め、相続人に平等に引き継がれた株式を会社が買い取り、自己株式(金庫株)とする方法です。(会社法第174条)
自己株式(金庫株)とすることにより、それらの議決権や配当請求権は停止するため、議決権の分散を防止する効果があります。
次に、種類株式(内容の異なる2以上の種類の株式)を発行する方法です。会社法第108条では、所定の事項を定款で定めることにより、種類株式を発行することができると規定されています。
種類株式を発行する際に、株主総会において議決権を行使することができる事項について、普通株式と異なる定めをすることが可能です。(会社法第108条1項3号)以上の方法により、議決権制限株式を発行し、後継者でない相続人には議決権のない、配当や残余財産の分配といった金銭的権利のみがある株式を相続させ、議決権の分散を防止することが可能です。
また、種類株式を発行する際には、剰余金の配当について、普通株式と異なる定めをすることが可能です。相続人間の平等感を確保するために、議決権制限株式の配当金について、普通株式より優先的に配当を受けられる旨を定める方法も考えられます。
後継者が会社を繫栄させた場合、後継者には議決権が集中し、その他の相続人は配当金による金銭的メリットを受けることができ、双方にとって納得感のある取り組みであると考えます。
遺言書の作成を行う
所定の事項を記載した遺言書を作成しておくことにより、相続人間の遺産をめぐる争い、株式の分散を防ぐ方法について解説します。
たとえば、評価額2,000万円分の自社株を持つ経営者が亡くなり、子供A・Bが経営者を相続することになったケースです。ここで、経営者が遺言書を用意していない場合、AとBは、1,000万円分ずつ、等しい割合で自社株を相続することになります。経営者はAを後継者にしたいと考えていましたが、遺言書がないことにより、自社株(議決権)が分散してしまいます。
一部ですが、遺言書を作成するポイントを3つご紹介します。
・相続分の指定を行う
民法では、被相続人(本ケースでは現経営者)は、遺言で、共同相続人(本ケースでは子供A・B)の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができると規定されています。(民法第902条1項)
あらかじめ、経営者自身が自社株式についてはすべてAに相続させることを遺言書に定めることで、Bへの株式の分散を防ぐ効果が期待できます。
・遺言執行者の指定
経営者自身が望むような形できちんと遺産分割が行われるよう、遺言執行者を指定する方法も考えられます。民法では、実際に遺言の内容を執行(実現)する者を遺言で指定することが認められています。(民法第1006条)
本ケースの場合には、Aを遺言執行者に指定することで、滞りなく自社株がAに相続される効果を期待できます。
・付言事項を記載する
遺言の内容は、法定事項と法定外事項に分けられます。たとえば、相続や財産処分に関する事項、認知などの身分に関する事項といった内容は法定事項とされ、民法をはじめとした法律により、効果が保証されています。
一方、付言事項は法定外事項に分類されます。たとえば、「自社株をすべてAに相続させる。」という文言は、遺産分割(相続)に関する事項のため、法定事項です。しかし、「どうしてAに自社株を相続させようと考えたか。」といった過程、経営者の思いについては、法定外事項(付言事項)となります。
付言事項に記載する内容については、特段の制限はありません。
本ケースの場合、Bは遺言書を見たときに不公平感を覚える可能性があります。付言事項で「Aに自社株を相続させるに至った思い」「家族への感謝の気持ち」「BにAを支えてほしい旨」等を記載することにより、Bの納得感が増し、Bが相続について協力的になる効果も期待できます。
遺留分侵害額請求に備える
3つ目の対策は、後継者が他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合に備えることです。後継者の金銭的、精神的な負担を軽減し、スムーズな事業承継が行われる効果が期待できます。
・生前贈与を活用する
自社株を相続による一括取得ではなく、生前から数年に分けて後継者に取得させる方法です。後継者に贈与税はかかるものの、比較的低い贈与税率で自社株を引き継がせる効果が期待できます。贈与を受けた財産は原則として相続財産に含まれないためです。
しかし、生前贈与が特別受益(民法第903条1項)であると判断されると、贈与を受けた金額が相続財産に持ち戻される可能性があるため、活用の際には弁護士、税理士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。
・種類株式の活用
3-1でも触れた通り、種類株式(議決権制限株式や優先配当株式)を活用することにより、後継者だけでなく他の相続人に対しても株式を相続させる方法です。
他の相続人の不公平感が少なく、遺留分侵害額請求を受ける確率を低減する効果が期待できます。
・役員退職金の活用
自社株を後継者に相続させる代わりに、役員退職金を他の相続人へ相続することで、遺留分侵害額請求を受ける可能性を低減する方法です。
役員退職金の活用は、遺留分侵害額請求だけでなく、自社株の評価額の引き下げにも活用できる可能性があります。
・事業承継を円滑に行うための民法の特例を活用
自社株や事業用資産を相続財産から除外する方法(除外合意)により、他の相続人は自社株については遺留分の主張ができなくなります。
また、自社株の株価を時価で固定する方法(固定合意)により、株価上昇による多額の遺留分侵害額請求を受けるリスクに備えることが可能です。固定合意を行う際には、時価を適正に評価するため、弁護士、公認会計士、税理士等による証明が必要です。(中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律 第4条、第5条)
事業承継税制を活用する
4つ目の対策は、事業承継税制を活用することにより、後継者が支払う相続税を免除・猶予する方法です。
事業承継税制は、後継者である相続人等が、所定の認定を受けている非上場会社の株式を贈与又は相続等によって取得した場合、その非上場株式の贈与税・相続税について、一定の要件のもと、納税を猶予、猶予されている贈与税・相続税が免除される制度です。
本制度を活用するためには、2026年3月31日までに、会社の主たる事務所が所在する都道府県庁に対して、特例承継計画を提出する必要があります。認定の要件や認定後の報告義務もある制度ですが、後継者の相続税の負担がなくなることで、円滑な事業承継が期待できます。
▶参考情報:中小企業庁HP「法人版事業承継税制の活用事例」
自社株の評価額を実情に合うように引き下げる
5つ目の対策は、自社株の評価額を実情に合うように引き下げ、相続税の金額自体を減らす方法です。
2-2で解説した通り、非上場の自社株を評価する際の方法は①類似業種比準価格方式②純資産価格方式の2パターンです。どちらの方法が適用されるかは、会社の規模区分により異なりますが、①は業績に応じた評価、②は保有している純資産に応じた評価であるといえます。
・業績を下げる(経営状態を赤字にする)
・純資産を減らす(会社の資産を減らす、負債を増やす)
ことにより、類似業種株価や純資産株価を引き下げる効果が期待できます。
たとえば、類似業種比準価格方式では、自社株の1株当たりの配当金・利益・純資産を、類似業種で割り、その数が大きければ大きいほど、評価額が高くなります。
ですから、配当金・利益・純資産を減らすことにより、相続税の低減効果が期待できます。具体的には、役員退職金の支給や含み益のある土地を売却する(損金に算入する)ことにより、利益の減少、資産の減少を行います。
- 遺言書の種類ごとのメリット・デメリットを解説
-
民法では普通の方式による遺言と、特別の方式による遺言について規定されています。特別の方式による遺言については、危篤、伝染病による隔離等の場合について規定したものであるため、今回は普通方式の遺言について、下記の一覧表にて解説します。
種類
概要
メリット
デメリット
自筆証書遺言
(民法968条)
遺言の全文、日付、氏名を自書し、捺印する方法
・費用が掛からない
・遺言の内容を自分だけに留めておくことが可能
・自筆証書遺言保管制度を活用することにより、適切な保管、死亡時の相続人への通知、検認手続きの省略等が可能
・要件を満たさないことによる遺言無効のリスク
・遺言書の紛失、忘れ去られ
・遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたりするリスク
・死後に家庭裁判所で検認手続きが必要
公正証書遺言
(民法969条)
証人立会いの下、公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人に遺言書を作成してもらう方法
・公証人による作成のため、遺言無効の心配がない
・遺言書は公証役場に保管されるので、勝手に書き換えられたり、捨てられる心配がない
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・証人(相続人やその配偶者、家族は不可)2人が必要
・費用が掛かる(相続財産の価格による)
・手間がかかる
・証人には遺言書の内容が知られてしまう
秘密証書遺言
(民法970条)
遺言書を封じ、署名捺印した後、証人と公証人に提出する方法
・自筆証書遺言と違い、署名のみを自書すればよい
・公正証書遺言よりも費用が安い
・公正証書遺言と異なり、保管は自分で行うため、自筆証書遺言と同様の紛失、改ざんリスクがある
・証人(相続人やその配偶者、家族は不可)2人が必要
自社株の相続についてのお悩み・課題は、解決できます
この記事では、自社株の相続について、経営者の皆さまが直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社の自社株の相続や事業承継がトラブルなく行われ、貴社の皆さんが笑顔で、会社が代々続いていく未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、会社の株式や経営権、事業承継を解決してきた実績があります。
また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。
当法律事務所にご依頼いただくことで、
「後継ぎの方がスムーズに会社を引き継げる体制を作れるようになる。」
「株が分散していても、経営権をしっかり守れる仕組みを整えられるようになる。」
「相続税の負担を減らす方法を見つけて、家族や会社の負担を軽くできるようになる。」
さらに、
「遺言や贈与を使って、家族や会社にとって一番いい形を作れるようになる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「家族で揉めることがないよう、事前にしっかり準備して安心できるようになった。」
「法律や税金のことを専門家に任せて、自分もちゃんと理解できるようになった。」
「相続問題で従業員や取引先に心配をかけないで、経営を続けられるようになった」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する経営者の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
こちらから「メールでスピード相談」ができます。
■この記事の内容は「わかりやすさ」と、「要はどうすればよいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解の上、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、是非専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」