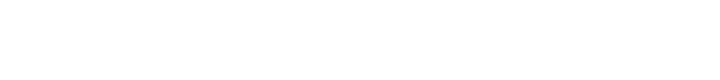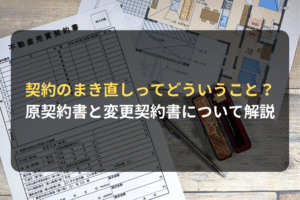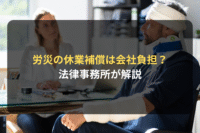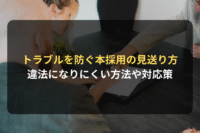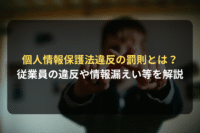- 2024.10.15
著作権をわかりやすく教えてください。もし他社のホームページなどを真似した場合、損害賠償のリスクがありますか?
著作権侵害って何ですか?という社長のご質問に対し、弁護士がお答えします。著作権侵害の基本的な要件や例外的に著作権侵害にあたらないケース、損害の算定方法などについて、わかりやすく解説しています。
目次
著作権侵害とは?
|
支分権の種類 |
権利の内容 |
|
「複製権」 |
著作物を形ある物にコピーする権利(著作権法第21条) |
|
「上演権・演奏権」 |
著作物を無断で、公衆向けに上演(演劇・舞踊等)、演奏(コンサート・オペラ等)されない権利(著作権法第22条) |
|
「上映権」 |
著作物を公衆向け上映する(スクリーン等に映し出す)権利(著作権法第22条の2) |
|
「公衆送信権・公の伝達権」 |
著作物を公衆に放送やインターネットで送信する権利、公衆送信された著作物をテレビなどの受信装置を通し公衆向けに伝達する権利(著作権法第23条第2条) |
|
「口述権」 |
小説等の著作物を、朗読などで公衆に伝達する権利(著作権法第24条) |
|
「展示権」 |
美術の著作物(原作品)や未発行の写真の著作物(原作品)を公に展示する権利(著作権法第25条) |
|
「譲渡権」 |
著作物(複製物も含む)を譲渡によって、公衆に提供する権利(著作権法第26条の2) |
|
「貸与権」 |
著作物を複製したものを貸与によって、公衆に提供する権利(著作権法26条の3) |
|
「頒布権」 |
映画の著作物に限って、著作物を複製物により公衆向けに譲渡、貸与する権利(著作権法第26条) |
|
「翻訳権・翻案権等」 |
著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化等により加工する権利(著作権法第27条) |
|
「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」 |
著作物を基に作られた、二次的著作物について、二次的著作物の著作者が持つ権利と同一の権利(著作権法第28条) |
- 著作者人格権とは?
 T社長著作権についてちょっと理解が深まった気がします。
T社長著作権についてちょっと理解が深まった気がします。
それはよかったです。ところで、T社長は著作者人格権という言葉を聞いたことがありますか? 小野弁護士
小野弁護士
 T社長著作者人格権ですか…。耳にすることはありますが、詳しくは分からないです。
T社長著作者人格権ですか…。耳にすることはありますが、詳しくは分からないです。
著作者人格権というのは、著作者の精神的利益を守るための権利であり、『著作者』だからこそ認められるものなので、著作権と違い、他の人に売ったり相続させたりすることはできません。例えば、T社長が広告コンテンツ(動画・静止画・紹介文など)の製作・納品を外部に委託する場合には、原則として著作者人格権は受託側が取得し、委託側がこれを譲り受けることはできないということです。そのため、実務では、著作人格権をめぐるトラブルを前もって防ぐ趣旨のもと、受託側との間で著作人格権を行使しない旨の特約(いわゆる著作者人格権不行使特約)を合意しておくことが多いです。
ただし、相手が著作者人格権不行使特約に合意したからといって、著作者の名誉や作品に込めた想いを害するような悪質な変更等を行った場合には、当該特約の効力が及ばないとされたり又は著作者の名誉を害する行為にあたるとして著作者人格権への侵害があったとみなされる(著作権法第113条第11項)等して、著作者人格権への侵害が成立してしまうケースもあります。誰かの著作物を使う場合は、相手や著作物への敬意をもってこれを活用するという姿勢を大事にしましょう。 小野弁護士
小野弁護士
なお、著作者人格権の具体的な権利内容については、下記いたしましたので、ご参考下さい。 小野弁護士
小野弁護士著作者人格権
権利の内容
「公表権」
公表されていない自分の著作物を、公表するかしないか決定できる権利(著作権法第18条第1項)
「氏名表示権」
自分の著作物を公表するときに、「氏名を公表するかどうか」、表示するとしたら「本名にするかペンネームにするかどうか」等を決定できる権利(著作権法第19条第1項)
「同一性保持権」
自分の著作物の内容や題名を、自分の意思に反して無断で変更されない権利(著作権法第20条第1項)
著作権侵害の成立要件
著作権侵害を主張する者(被侵害者)が著作権を有していること
著作物とは、①思想または感情を②創作的に③表現したものであって④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを指すので、例えば、A社の記事の内容が歴史的な事実だけを述べている場合には①や②が認められないことが多く、上記⑴を満たさないので、一般的には著作物として認められません。
さらに、仮にA社の記事が①~④の要件を満たし、著作物として認められても、A社が他人から譲渡を受けることなく、当該他人の著作物をそのまま記事にしているような場合、A社はその記事について著作権をもっているとはいえません。このような場合には、上記⑵を満たさず、A社はB社に対して著作権の侵害を主張できないことになります。
ただし、この場合にも、A社が著作権の侵害を主張できないことと、本当の著作者がB 社に対して著作権の侵害を主張してくる可能性があることは別に考える必要があります。
著作権侵害行為の存在
前述した例(「2-1.」参照)にならい、A社がインターネット上に掲載した記事を、B社がホームページで参考にした場合で考えてみましょう。この場合には、例えば、B社としては、A社の記事(著作物)を参考にしてホームページを作成したという点で複製権又は翻案権を侵害する可能性がありますし、また作成したホームページをオンライン上に掲載したという点で公衆送信権を侵害する可能性があります。
なお、複製権と翻案権のどちらが成立するのかは、問題となっているB社ホームページの箇所に著作物性(2-1.要件①~④参照)が認められるかどうかで決まります。具体的には、当該箇所に著作物性が認められる場合には翻案権侵害を検討し、反対に著作物性が認められない場合には複製権侵害を検討することになります(著作権法第21条、第27条参照)。ただし、著作物性の有無は実際に争ってみないと分からない所もあるので、実務では、どちらも主張しておくケースが多いですね。
そこで、実際の裁判では、相手の著作物に依拠せず複製・翻案等を行った場合には、著作権侵害は成立しないという考え方が採られています。
なお、この判断の際には、他者の著作物を参照できる客観的な状況・立場の有無、他者の著作物と類似する範囲や程度、類似するに至った経緯などが考慮されることになります。
つまり、依拠性を否定するには、単に「他者の著作物の存在を知らずに似たものを作ってしまいました」という内心を主張するだけでは足りず、そのことを客観的に裏付ける事実(状況・経緯など)も併せて主張していく必要があります。
ただ、これらの判断を含め、著作権をめぐるトラブル解決には専門的な法律知識や微妙な法的判断を求められる場合が多く、もしこうしたトラブルに巻き込まれてしまった場合には、一度専門の弁護士に相談することをお勧めします。
著作権侵害行為を行った者に故意・過失が認められること
※「著作権侵害への救済手続 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)」参照
被侵害者に損害が発生していること
著作権等を侵害をしてしまった場合にはどのようなリスクに晒される?
リスクの具体例
損害賠償請求(民法第709条)について
著作権等の知的財産権をめぐる損害賠償については高額になる事例・事件も多く、例えば、写真家が撮影した猫の写真を無断で使用、改変した企業に対し、複製権の侵害として66万円、著作者人格権の侵害による慰謝料として200万円、弁護士費用として26万円、合わせて292万円の支払いが命じられたケースもあります。(「東京地方裁判所 判決 2014年5月27日」参照)
差止請求(著作権法第112条第1項・第2項)について
⑴ 侵害行為をする者に対して、その行為の停止を請求することができる
⑵ 侵害のおそれのある行為をする者に対して、侵害の予防を請求することができる
⑶ 侵害行為によって作成されたもの、侵害行為に使われた機械や器具の破棄、その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求(廃棄請求)ができる。ただし、この廃棄請求は、⑴または⑵の請求の実行力を確保するための権利なので、⑴または⑵の請求と併せて行う必要があり、かつこれらの請求に必要な範囲内でのみ認められています。
例えば、A社のホームページをB社が真似し、B社に著作権侵害または著作権侵害のおそ
れが認められる場合には、A社から⑴または⑵と併せて⑶の廃棄請求が行われるおそれが
あり、この場合には、B社はせっかく費用をかけて作成したホームページを削除しなけれ
ばいけなくなる可能性があります。
名誉回復措置請求(著作権法115条)について
その他の注意点について(刑事罰)
|
|
著作権に対する侵害の場合 |
著作者人格権に対する侵害の場合 |
|
刑罰の量刑 |
次の刑またはその併科。 ▪懲役10年以下 ▪罰金1000万円以下 (※著作権法119条1項) |
次の刑またはその併科。 ▪懲役5年以下 ▪罰金500万円以下 (※著作権法119条2項) |
|
両罰規定の存否 |
どちらも両罰規定が存在する。 具体的には、法人の代表者や従業員が、職務に関して、著作権侵害を行った場合、当該法人に対しても罰金が科されることになる。 ただし、当該代表者等が行ったのが著作権侵害なのか著作者人格権侵害なのかで、次の違いが生じることに注意する。 ①代表者等が行ったのが著作権侵害の場合 ・・・法人に課せられるのは3億円以下の罰金 ②代表者等が行ったのが著作者人格権の場合 ・・・法人に課せられるのは500万円以下の罰金 (※著作権法124条) |
|
著作権侵害とならないケース
|
認められる利用方法 |
例 |
注意点 |
条文 |
|
「私的使用のための複製」 |
・アイドルのポスターをコピーして、自室とリビングに貼る
|
・複製物を人に譲渡することはできない ・複製の際に不特定多数の人が使用する自動複製機(コピー機等)は使用不可。 ※ただし、コンビニに据え置かれるコピー機を使うことについては、例外的に適法である。 |
著作権法第30条第1項、同法附則第5条の2 |
|
「引用」 |
・本に記載された一節をブログにて掲載し、その一節に対して自分の考えや感想を書く |
・後述します(「3-3.」参照) |
著作権法第32条 |
|
「付随対象著作物の利用」 |
・海の写真を撮った際、たまたま人が映り込んでしまったとしても、度合いが軽微であれば、映り込んだ人をも含んだ著作物として、その写真を複製したり、伝達できる |
・映り込みが軽微かどうかは、収益を得る目的があったかどうか、海の風景から映り込んだ人を分離できるかどうか、等の要素を総合的に判断する必要がある |
著作権法第30条の2 |
|
「検討の過程における利用」 |
著作権者から許可を得て、または文化庁から裁定を得て著作物(絵画)を利用しようとしているA社が、実際に絵画を使用してTシャツやグッズを作成し、著作物を利用するかどうか検討する |
・必要と認められる範囲(社内のみ等)で行わなければならない ・著作権者の利益を害するような利用はできない |
著作権法第30条の3 |
|
「思想または感情の享受を目的としない利用」 |
・本を朗読、録音し、試験の問題とする ・ソフトウエアをバックアップ(複製)、バグの修正(改変)をする |
・著作物から思想や感情を受け取ったり、楽しむことを目的としていないことが必要 |
著作権法第30条の4 |
正しい「引用」の仕方とは?
- 損害額の算定方法について
 T社長そういえば、著作権侵害の損害額ってどうやって証明するのでしょうか?
T社長そういえば、著作権侵害の損害額ってどうやって証明するのでしょうか?
民法の規定に従って損害額を証明する方法がありますが、著作権等の知的財産権の場合、侵害行為によって実際にいくらの損害が生じたのか、証明することが難しいです。
さらに、証明責任は被侵害者にあるため、著作権法第114条第1項~第3項には損害賠償を推定する規定があります。この推定規定があると、法律上は相手からの反証がない限りは、その推定金額が損害額となるため、被侵害者の証明をする負担が軽減されます。具体的には、下記の3パターンの推定規定があります。 小野弁護士
小野弁護士推定規定
推定される損害額
具体的な算定方法
パターン①
(著作権法第114条第1項)
侵害行為がなかったら著作権者等が販売により取得したであろう利益
「譲渡・公衆送信・複製した数量(以下「譲渡等数量」)」×「商品1個当たりの利益の額」。
ただし、被害者の販売能力を超える部分については損害額から除く。
パターン②
(著作権法第114条第2項)
侵害行為により加害者が取得した利益
「譲渡等数量」×「侵害品1個当たりの単位数量辺りの利益」
パターン③
(著作権法第114条第3項)
侵害行為がなかったら著作権者等がライセンス契約等により取得したであろう利益
「譲渡等数量」×「著作権行使1回当たりの利益の額」(ライセンス料)
なお、上記のパターン①~③の推定規定を活用する場合には、加害者側の営業上の情報(譲渡等数量や売上額、利益額など)が必要となるので、実務では、文書提出命令(著作権法114条の3)や計算に関する鑑定(著作権法114条の4)を活用し、著作権を侵害した側に損害額の計算に必要な書類の提出を命じるケースも多いです。 小野弁護士
小野弁護士
 T社長著作権侵害の損害賠償は証明が難しいけれど、法律できちんと計算できるよう決められているんですね。著作権に関するビジネスの際は、気を付けながら進めていきたいと思います!
T社長著作権侵害の損害賠償は証明が難しいけれど、法律できちんと計算できるよう決められているんですね。著作権に関するビジネスの際は、気を付けながら進めていきたいと思います!
著作権侵害への対応について、弁護士に相談できますか?
(法律事務所に対し、著作権侵害に関して依頼・問い合わせることのメリット)
著作権侵害を行ってしまうと、前述の通り、会社の信用問題、金銭的な負担の増加にもつながります。また、意図せず著作権侵害をしてしまった場合、素早い対応により侵害の拡大を防止する必要があります。知財に詳しい企業法務弁護士に依頼することで、著作権侵害に関する事前チェックのほかにも、著作権を適切に利用してビジネスを拡大するなど、ビジネス上のアドバイスも受けることができます。
著作権法をはじめとした知的財産権に関する法律は複雑で、ときには個別の事情に応じて判断することも必要になります。外部の弁護士に依頼することで、リーガルチェックの負担を軽減して、ビジネスに集中することができますから、気軽に相談してくださいね。
まとめ
最近ですと、地方自治体の広報担当者が「イラスト 無料」と検索して出てきた他人のイラストをうっかり広報業務に利用した結果、著作権者から提訴され、25万円の和解金を支払ったケースもあります。。
インターネットやSNSの普及により、だれもが著作物を利用できるようになった現代で、著作権侵害はとても身近な問題になったと考えます。企業活動の際にも、他人の権利を侵害していないかどうか、そういったおそれがないかどうか、念頭に置いておくことが重要です。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」