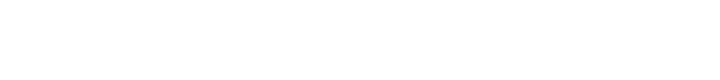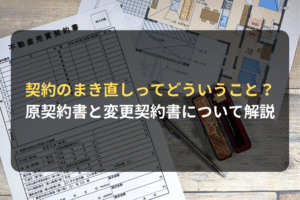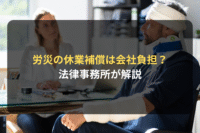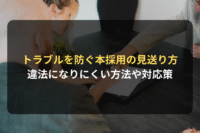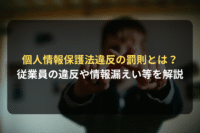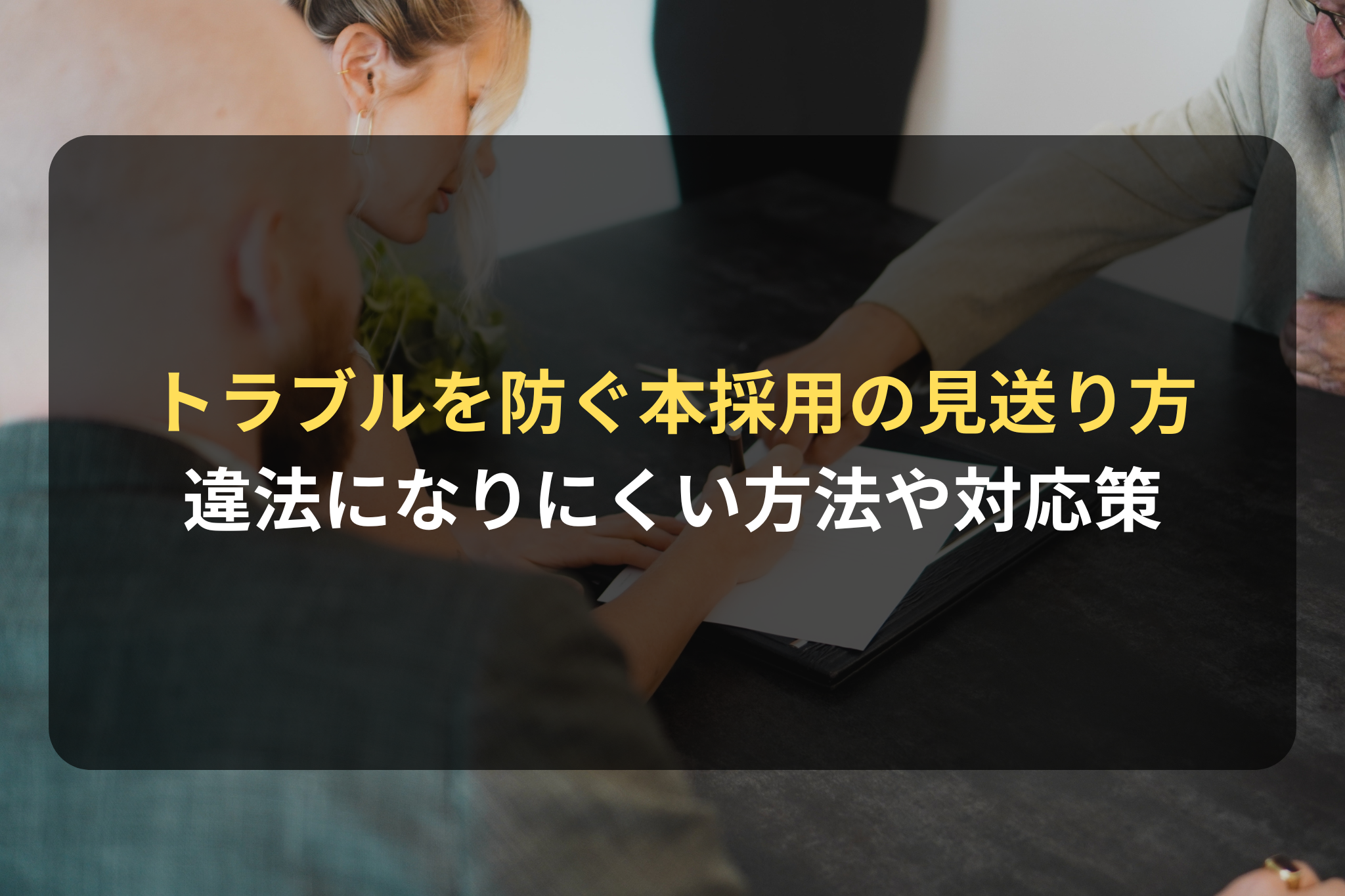
- 2024.08.22
トラブルになりにくい本採用の見送り方とは?(試用期間の意味を踏まえて、違法になりにくい本採用の見送りについて、企業が行うべき具体的な対応策を弁護士がわかりやすく解説)
試用期間中及び満了時に行う本採用拒否の法的なリスクを踏まえた上で、企業としては試用期間中どのようなことに注意して当該従業員と向き合えばよいかについて、弁護士がわかりやすい解説します。
目次
本採用や試用期間って何ですか?
(本採用や試用期間の意味や両者の関係について簡単に解説)
T社長
先生!わが社では人材採用において、今回の募集から試用期間を設けることを考えています。試用期間中の注意点があれば教えていただきたいです。
なるほど。今日は『試用期間と本採用』の相談ですね。
小野弁護士
T社長
そもそも、試用期間と本採用ってどのような関係なんでしょうか?
簡単にまとめると、試用期間というのは『従業員の見極め期間』、本採用とは『試用期間を経て、その従業員を正式に採用すること』です。一般的に、従業員を一度採用すると、簡単には解雇できません。そのため、一定期間、人材の能力や勤務態度を見極めて本採用をするかどうかを決めるんです。
また、試用期間とは、法的には『解約権留保付労働契約』と解釈されることが一般的です。(三菱樹脂事件 最高裁大法廷判決 昭和48年12月12日)つまり、雇用契約は成立しているが、企業には雇用契約を解約する権利が残っているため、一定の事情がある場合にはその従業員の本採用を拒否する(解雇する)ことが可能なんですよ。
また、試用期間とは、法的には『解約権留保付労働契約』と解釈されることが一般的です。(三菱樹脂事件 最高裁大法廷判決 昭和48年12月12日)つまり、雇用契約は成立しているが、企業には雇用契約を解約する権利が残っているため、一定の事情がある場合にはその従業員の本採用を拒否する(解雇する)ことが可能なんですよ。
小野弁護士
- 試用期間中の従業員の地位
 T社長先生!そういえば、試用期間中の従業員の待遇については、どのように考えればいいでしょうか?試用期間中の従業員の地位については、法律で明確な規定はありません。しかし、試用期間中であっても雇用契約は成立しているため、労働基準法や最低賃金法の適用がある点には注意です。わかりやすく一覧にしてまとめてみましたので、参考にしてみてくださいね。
T社長先生!そういえば、試用期間中の従業員の待遇については、どのように考えればいいでしょうか?試用期間中の従業員の地位については、法律で明確な規定はありません。しかし、試用期間中であっても雇用契約は成立しているため、労働基準法や最低賃金法の適用がある点には注意です。わかりやすく一覧にしてまとめてみましたので、参考にしてみてくださいね。 小野弁護士
小野弁護士給与
従業員との合意があれば、本採用時よりも低く設定することは可能。
ただし、最低賃金法の適用に注意。
社会保険
本採用の場合と同様。
有給休暇
試用期間が6か月を超える場合には付与が必要。
賞与
法律上の支給義務はないものの、就業規則や賃金規定で定めがある場合には支給が必要。
残業
本採用の場合と同様。
本採用の見送りが違法となることはありますか?
(本採用を拒否する際の法的リスク及び実際の事例をいくつか紹介)
T社長
試用期間が終わってから、本採用を見送る場合の注意点はありますか?
一般的に、試用期間満了後に従業員の本採用を拒否する(解雇する)場合には、雇い入れ後の解雇よりも企業側の裁量は広い(解雇のハードルは低い)と解釈されます。(三菱樹脂事件 最高裁大法廷判決 昭和48年12月12日)
しかし、客観的に合理的な理由なく本採用の拒否(解雇)を行った場合には、その解雇は無効となり、従業員に対して未払い賃金や慰謝料、解決金の支払いが必要になるリスクがあります。『合理的な理由』については個々の事案によって異なりますので、解雇権の濫用、いわゆる不当解雇とならないように注意が必要です。
しかし、客観的に合理的な理由なく本採用の拒否(解雇)を行った場合には、その解雇は無効となり、従業員に対して未払い賃金や慰謝料、解決金の支払いが必要になるリスクがあります。『合理的な理由』については個々の事案によって異なりますので、解雇権の濫用、いわゆる不当解雇とならないように注意が必要です。
小野弁護士
T社長
試用期間ってもう少し気楽なイメージがありましたが、本採用しない場合には解雇と同様に慎重になる必要があるんですね。実際にどのような理由での本採用の拒否が認められるのでしょうか?
本採用の拒否が不当解雇にならないためには、①客観的に合理的な理由があるか②社会相当性があるか、の2点が重要なポイントです。試用期間中の解雇の事例ごとにわかりやすく解説していきますね。
小野弁護士
まずは、①について認められた『雅叙園観光事件(東京地方裁判所判決 昭和60年11月20日)』です。周囲とのいざこざが絶えなかった従業員の行為について、就業規則に解雇事由として挙げられていた『就業態度が著しく不良で他に配置転換の見込みがないと認めたとき』に該当するとして、解雇が有効と判断された事例です。
その他に『ブレーンベース事件(東京地方裁判所判決 平成13年12月25日)』では、
・従業員が緊急の対応に速やかに応じなかった
・採用面接の際にパソコンに精通していると述べたにも関わらず、簡単な作業すらできなかった
・代表取締役の業務上の指示に応じなかった
といったことを理由に、『期待に沿う業務が実行される可能性を見出しがたい』と認められ、解雇が有効とされました。
その他に『ブレーンベース事件(東京地方裁判所判決 平成13年12月25日)』では、
・従業員が緊急の対応に速やかに応じなかった
・採用面接の際にパソコンに精通していると述べたにも関わらず、簡単な作業すらできなかった
・代表取締役の業務上の指示に応じなかった
といったことを理由に、『期待に沿う業務が実行される可能性を見出しがたい』と認められ、解雇が有効とされました。
小野弁護士
T社長
たしかに、会社の調和を乱したり、仕事に必要な指示に背いたり、聞いていたスキルのレベルや従業員の情報が実際とかけ離れているのは、客観的に見て本採用見送りも仕方がない感じがしますね…。
そうですね。協調性に欠け、上司の指示に従わない(業務不適格)、業務を覚える意思がない(勤務成績不良)、乱暴な言動(言動の不適格)等によって解雇が有効とされた事例もありますよ。
次に②について解雇が無効とされた事例をご紹介しますね。『テーダブルジェー事件(東京地方裁判所判決 平成13年2月27日)』です。企業の会長に対して挨拶をしなかったことを理由として従業員が解雇されましたが、社会通念上相当性がないとして無効とされました。
その他に、『オープンタイドジャパン事件(東京地方裁判所判決 平成14年8月9日)』では、企業が年俸1,300万円で中途採用をした上級管理職を、
・業務が速やかでない
・企業の方針に合わない
といった理由で2か月の試用期間を経て解雇しましたが、『業務遂行能力が著しく不良、上級管理職として不適格とはいえず、2か月で企業の期待に応えることは困難であった』として解雇が無効とされました。本事例は、2ヵ月という短い期間で解雇を決定したことに社会相当性があったか(実績を残すチャンスがあったか)がポイントです。
次に②について解雇が無効とされた事例をご紹介しますね。『テーダブルジェー事件(東京地方裁判所判決 平成13年2月27日)』です。企業の会長に対して挨拶をしなかったことを理由として従業員が解雇されましたが、社会通念上相当性がないとして無効とされました。
その他に、『オープンタイドジャパン事件(東京地方裁判所判決 平成14年8月9日)』では、企業が年俸1,300万円で中途採用をした上級管理職を、
・業務が速やかでない
・企業の方針に合わない
といった理由で2か月の試用期間を経て解雇しましたが、『業務遂行能力が著しく不良、上級管理職として不適格とはいえず、2か月で企業の期待に応えることは困難であった』として解雇が無効とされました。本事例は、2ヵ月という短い期間で解雇を決定したことに社会相当性があったか(実績を残すチャンスがあったか)がポイントです。
小野弁護士
T社長
本採用を拒否する理由や、本採用を拒否するに至った経緯も大切なポイントなんですね。
おっしゃる通りです。事例によって、
・企業の慣行
・業務内容
・従業員の言動等は異なり、一概に判断することは難しいため、個々の事例に応じてきちんとした理由があるか、社会的に認められるような解雇なのか、精査することが重要です。
・企業の慣行
・業務内容
・従業員の言動等は異なり、一概に判断することは難しいため、個々の事例に応じてきちんとした理由があるか、社会的に認められるような解雇なのか、精査することが重要です。
小野弁護士
- 試用期間として設定することが許される期間とは?
 T社長先生、試用期間は長く設けた方が安心ですか?
T社長先生、試用期間は長く設けた方が安心ですか?
一概にそうともいえません。たとえば、『ブラザー工業事件(名古屋地裁判決 昭和59年3月23日)』では、6~15か月の見習い期間を経て試用社員となった従業員に対して、さらに12~15か月の試用期間を課すこと(労働能力や勤務態度等業務への適性を判断するのに必要な合理的な期間を超える試用期間を課すこと)は、試用期間中の労働者が不安定な地位に置かれる状況を鑑みて、公序良俗(民法90条)に違反するとして無効と判断されました。
試用期間の長さが合理的か、そうでないかの判断は、ただ単に期間だけをみて判断するのではなく、業務の性質や種類、従業員のポジション等によって個別に判断されます。過去の事例では、『大阪読売新聞試用者解雇事件(大阪高裁判決 昭和45年7月10日)』において1年間の試用期間が認められましたが、前述の『ブラザー工業事件(名古屋地裁判決 昭和59年3月23日)』では6ヶ月~1年の試用期間は認められませんでした。
なお、試用期間は、1か月~6か月の期間を設けている企業がほとんどとなります。(厚生労働省HP『第47回労働政策審議会労働条件分科会 会議次第及び資料項目』参照) 小野弁護士
小野弁護士
 T社長長ければいいわけではないんですね。長すぎる試用期間を設けた場合、どんなリスクがありますか?
T社長長ければいいわけではないんですね。長すぎる試用期間を設けた場合、どんなリスクがありますか?
例えば、試用期間を9か月とし、試用期間満了後に本採用を見送ったとしましょう。その後、従業員から訴えられた末、試用期間の長さが違法無効であり、6か月を超える試用期間は試用期間として認められないと認定されたとします。この場合、企業が行った解雇は試用期間満了後の解雇にあたるため、試用期間中の解雇よりも厳しい解雇要件が必要となり、本採用の見送りが不当解雇となるリスクが高まるんです。 小野弁護士
小野弁護士
適法に本採用を見送るために企業がしておくべき対策
(試用期間の目的を踏まえて、有効な試用期間の使い方をわかりやすく説明)
T社長
先生、適法に(=不当解雇とならないように)本採用を見送るには、わが社ではどのような取り組みができるでしょうか?
そのためには、試用期間中に従業員にどのような教育・指導を行うべきなのか、試用期間の目的を考えることが重要です。
例えば、面接時には筆記試験や面接を行いますよね。しかし、数回の試験や面接で、その人の能力が求めているレベルに達しているかどうか、共に働いていける人材であるかどうかを見抜くことは困難ではないですか?
例えば、面接時には筆記試験や面接を行いますよね。しかし、数回の試験や面接で、その人の能力が求めているレベルに達しているかどうか、共に働いていける人材であるかどうかを見抜くことは困難ではないですか?
小野弁護士
T社長
たしかに、わが社でも筆記試験はありますが部署ごとに異なる形式ではなく画一的なものですし、面接でもどこまで突っ込んでいいのかわからず、意外と重要なことを聞けていなかった、なんてことがあります。
まさに、そういった入社試験では分からない部分を見定めて改善されるよう教育・指導するのが、試用期間の大きな目的だと考えます。試用期間中に見定めるべき項目の具体例としては、次のことが挙げられます。
・申告済みの経歴やスキルといった情報に違いはないか
・採用時の年収や待遇、ポジションにあった仕事をこなせるかどうか
・上司の指示や会社の慣行に従うことができるのか
・遅刻や欠席などの勤怠不良はないか
・仕事に対する意欲や向上心があるか
・同じ部署や関連部署、取引先と円滑なコミュニケーションがとれるかどうか
・申告済みの経歴やスキルといった情報に違いはないか
・採用時の年収や待遇、ポジションにあった仕事をこなせるかどうか
・上司の指示や会社の慣行に従うことができるのか
・遅刻や欠席などの勤怠不良はないか
・仕事に対する意欲や向上心があるか
・同じ部署や関連部署、取引先と円滑なコミュニケーションがとれるかどうか
小野弁護士
ただし、解雇というのは従業員の生活や利益にとても大きな影響を与えます。そのため、試用期間中の教育・指導にあたっては『当該従業員が本採用に至ることができるよう相当の努力を尽くしたこと』が求められる点には注意が必要です。なお、ここでいう「相当な努力」とは当該従業員の採用枠(新卒/中途、未経験/経験等)やポジション、年収等によって決まりますので、個別に判断することになります。
以上のことを踏まえて、会社として行う取り組みとポイントを以下にまとめましたので、参考にしてくださいね。
以上のことを踏まえて、会社として行う取り組みとポイントを以下にまとめましたので、参考にしてくださいね。
小野弁護士
日報の提出
従業員から日報を提出してもらい、従業員への職務への姿勢を見る方法もあります。日報に対して上司からフィードバックを行うことで、従業員とのコミュニケーションも活発化し、通常の業務に関する悩みや疑問に対しても、速やかに対応することが可能になります。
また、もしも本採用を拒否して争いに発展した場合には、日報やフィードバックが、合理的理由や改善を促したことの証拠になるというメリットもありますよ。
また、もしも本採用を拒否して争いに発展した場合には、日報やフィードバックが、合理的理由や改善を促したことの証拠になるというメリットもありますよ。
小野弁護士
定期面談
定期面談を行うことも試用期間を有効活用する方法のひとつです。本採用で求める業務遂行能力や業務理解度のレベルと、従業員の現在のレベルを比べて、従業員に対して本採用の可能性や、改善点についてフィードバックしましょう。従業員も自分のすべきことが明確になり、前向きに職務に取り組むことが期待できます。
小野弁護士
on the job training(=OJT、実務を通して教えていく)
試用期間中はOJTを行い、実務を経験させつつ、業務を学んでもらうことも重要です。また、新卒の場合には、そもそも企業側が相手に対する育成を前提にして採用(試用期間)しているため、off the job training(=OFF-JT実務外の教育・研修等)までしておく方が安心です。
一般的には中途採用の場合にはOFF-JTまではしなくてもよいと判断されることもありますが、異種業界からの転職やポテンシャル採用などの場合には、新卒の場合と同じように相手に対する育成を前提に採用しているとも考えられます。その場合には、採用ポジションや年収等も考慮しつつ、ケースによってはOFF-JTまでしておく方が望ましいです。
一般的には中途採用の場合にはOFF-JTまではしなくてもよいと判断されることもありますが、異種業界からの転職やポテンシャル採用などの場合には、新卒の場合と同じように相手に対する育成を前提に採用しているとも考えられます。その場合には、採用ポジションや年収等も考慮しつつ、ケースによってはOFF-JTまでしておく方が望ましいです。
小野弁護士
T社長
試用期間中といっても、会社としてできることが多いのですね!
試用期間中の従業員といっても、試用期間中は他の企業への就労のチャンスを放棄してもらっている以上、本採用されるかどうかは従業員側にとって重要な問題です。そのため、企業としては従業員が本採用に至れるように、真摯に指導・サポートすることが、将来のトラブル防止に繋がると考えます。
小野弁護士
退職勧奨
T社長
試用期間中に見込みがないと判断した場合には、試用期間満了を待って、本採用の見送りをした方がいいのでしょうか?
試用期間中に退職勧奨を行うという方法もありますよ。退職勧奨は解雇とは違い、従業員に対して自発的な退職を促し、従業員と合意のうえでの退職を目指す方法です。企業側のメリットとしてはリスクの大きい解雇を行わなくてよい点があります。
小野弁護士
T社長
退職勧奨ですか。そういった可能性も考慮して、試用期間中の様々な取り組みを通して、従業員と円滑な人間関係を築いていきたいです!
- 試用期間にある従業員を解雇する際に解雇予告通知は必要か?
 T社長退職勧奨が失敗に終わってしまった場合、試用期間中に従業員を解雇する際に気を付ける点はありますか?
T社長退職勧奨が失敗に終わってしまった場合、試用期間中に従業員を解雇する際に気を付ける点はありますか?
試用期間中にある従業員を解雇する場合には、本採用と同様に解雇予告通知が必要です。労働基準法20条、21条4項において『試用期間中の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。』と定められています。『14日を超えて』というのは、15日以上を指します。 小野弁護士
小野弁護士
本採用に関する法的チェックや制度設計について、弁護士に相談できますか?
(法律事務所に対し、採用に関するリーガルチェックを依頼・問い合わせることのメリット)
T社長
試用期間と本採用について理解が深まった気がします!しかし、実際の採用活動をどのように運用するか、本採用を見送る理由の見極めについて不安があります。できれば、弁護士に相談したいと考えているのですが可能でしょうか?
はい、もちろん可能です!本採用に関する法的チェックをはじめとした、安全なビジネスの手助けを法律面からサポートいたします。また、社内の制度設計などのビジネス面からのサポートも可能です。ぜひ、ご相談ください。
小野弁護士
- 求人・採用の時の対応で違法な本採用見送りを低減できるか?
- 本採用見送りをめぐるトラブルは、当該企業で本採用されるには何に対するどの程度のレベルの業務遂行能力が求められるのか、どのような面で周りとの協調性が重視されるのか等について、しっかりと共有できていない所から生じてしまいます。
 小野弁護士
小野弁護士
 T社長なるほど、わが社も必要な経験や資格、従事してもらう業務内容をとりあえず並べる形式で求人票を出しているので、相手にとって具体的にどのような内容・種類のスキル・ノウハウ、人間性が求められているのかが若干曖昧になってしまっているかもしれません。
T社長なるほど、わが社も必要な経験や資格、従事してもらう業務内容をとりあえず並べる形式で求人票を出しているので、相手にとって具体的にどのような内容・種類のスキル・ノウハウ、人間性が求められているのかが若干曖昧になってしまっているかもしれません。
確かに、相手に伝えるべき事が詳細になればなるほど、それを適切に言語化することは難しくなってしまいますので、ある程度は曖昧にならざるを得ない面もあるかと思います。ですが、相手も他の企業での就職を横に置いて働いてくれようとしているわけですから、できるだけ相手の利益にも配慮しておけるとトラブルの少ない人材獲得に繋がっていくかと思います。
求人の際の労働条件通知については2024年から職業安定法が改正されて明示すべき事項が増えました。この点については弊所で別にコラム を書いていますので、ぜひ読んでみてください。 小野弁護士
小野弁護士▪2024年4月以降も職業安定法並びに施行規則に違反せずに求人を行うにはどうすればいいですか?
まとめ
試用期間を設けることは、人材を見極め、慎重な採用を可能にするメリットがあります。一方で、試用期間とはいえ、雇用契約は有効に締結されており、労働基準法をはじめとした法令が適用されます。また、求人を出す際にも、職業安定法を守る必要があります。
適法に試用期間を活用し、真摯に従業員と向き合うことで、人材採用がより安全に、スムーズに進むと考えます。今回お話しした以外のことについても、たくさんお手伝いできることがありますから、是非ご相談くださいね。T社長の目指すビジネスの実現に向けて、一緒に取り組んでいきましょう!
適法に試用期間を活用し、真摯に従業員と向き合うことで、人材採用がより安全に、スムーズに進むと考えます。今回お話しした以外のことについても、たくさんお手伝いできることがありますから、是非ご相談くださいね。T社長の目指すビジネスの実現に向けて、一緒に取り組んでいきましょう!
小野弁護士
T社長
最初は試用期間を『お試し期間』のように捉えてしまっていましたが、なんだか気が引き締まる思いです。試用期間とはいえ、従業員を雇用している意識をもって取り組んで参ります。先生、本日はありがとうございました!
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611
WRITER

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」