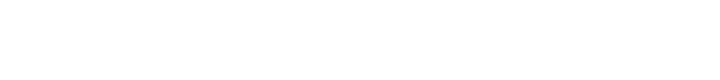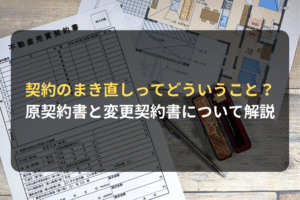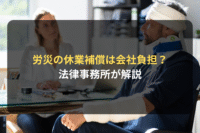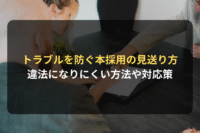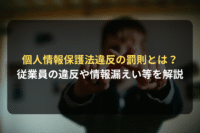- 2024.08.22
譲渡担保を使って債権回収し、泣き寝入りを防げますか?(譲渡担保を活用するメリット、その手続や注意点について解説)
譲渡担保って何ですか?という社長のご質問に対し、弁護士がお答えします。譲渡担保の内容、民法上の質権や抵当権との違い、譲渡担保の目的物(対象)、対抗要件などをわかりやすく解説しています。
目次
譲渡担保って何ですか?
(譲渡担保の概要、抵当権や質権との違いについて、わかりやすく解説)
譲渡担保の概要
▪譲渡担保を設定する者(債務者)・・・設定者
▪譲渡担保を取得する者(債権者)・・・譲渡担保権者
譲渡担保と、抵当権・質権との違い
譲渡担保と抵当権の異同
他方、譲渡担保は『動産』にも設定できますが、抵当権は『動産』には設定できません(民法369条1項、398条の2など参照)。例えば、PC、プリンター、事業用機械などの動産に担保を設定するケースでは、譲渡担保は使えるが、抵当権は使えないということですね。
譲渡担保と質権の異同
ですが、両者は、担保物件を設定者に管理させることができるか否かで違います。要するに、譲渡担保の場合には、担保物件を設定者に管理・使用させたままでもokですが、質権ではダメということですね(民法344条、345条)。
- 担保物件の所有権は誰に帰属する?
-
「譲渡担保を設定する場合、担保の所有権が誰に帰属するのか」という点について、大きく『担保的構成』『所有権的構成』という2つの考え方があります。
担保的構成によると、担保の所有権は実質上は『設定者』に帰属するものとして取り扱われる一方で、所有権的構成によると、所有権は『譲渡担保権者』に帰属するものとして取り扱われることになります。これらの2つの考え方の違いは、次のような点で結論に差異を生じさせ得ます。
▪設定者が無断で担保物件を処分した場合における当該処分の有効性
▪設定者が破産した場合における取戻権の発生時期など
従来の判例ではやや所有権的構成を重視する傾向にありましたが、近年では「譲渡担保も担保の一種である」という側面に鑑みて、担保的構成にも配慮する傾向が強まっています。
譲渡担保は、どんなものに活用(設定)できる?
ですが、かかる特約が付いていることを重大な不注意で知らなかった譲渡担保権者は、債務者の任意の支払がない限り、債権回収できないことに注意です(民法466条3項参照)。ですから、T社長が譲渡担保を取得する側の立場の時は、必ず担保とする債権に譲渡禁止特約が付いているかを確認するようにしましょう。
- 譲渡担保と著作権
-
譲渡担保の対象にできるものは、物や権利その他の経済的利益など多岐に渡り、その中には、著作権(著作権法17条1項参照)も含まれます。
具体的には、『プログラムに関するアイデア・技術はあるが、お金のないベンダー』や『本を書くネタはあるが、お金がない作家』に対して、開発や出版に必要な費用を融資する代わりに、プログラムや書籍の著作権に譲渡担保を設定すること等が考えられます。
ただし、著作権を有効な担保として取得するには、プログラムや書籍等に著作権が成立している必要がありますので、専門の弁護士などに相談しながら検討することをお勧めします。
譲渡担保を設定する際に、どんなことに気をつける?
(譲渡担保契約作成上の注意点、対抗要件などについて解説)
担保対象の特定
その他にも、一部の譲渡担保(集合動産譲渡担保、集合債権譲渡担保)においては担保の対象・範囲を適切に特定することが有効要件となります(最判昭和54年2月15日、最判平成11年1月29日など)。
譲渡担保を設定する際には担保の対象・範囲が適切に特定されているか、またこの点について譲渡担保当事者の認識にズレがないかをきちんと確認しておきましょう。
対抗要件を備えること
担保物件が動産の場合
しかしながら、もしもこうなってしまうと、即時取得(民法192条)というルールが適用される可能性があり、この場合、譲渡担保が消滅してしまうリスクがあります。
例えば、担保物件にラベル等を貼り付け、それが譲渡担保の対象である旨をはっきりとさせたり、こうしたラベル等が勝手に剥がされないように『(担保物件の状態について)報告を求めたり、立入検査ができる』旨の条項を譲渡担保契約書に盛り込んでおくことが有効な方法として挙げられます。
担保が不動産の場合
なお、この辺りの判断は、実際のビジネスを踏まえた複眼的な判断が必要となりますので、もし迷ったら、専門の弁護士に相談するといいですよ。
担保が債権の場合
債権の対抗要件の備え方は、大きく2つあります。1つは、確定日付のある証書(内容証明郵便など)で通知してもらう方法です。もう1つは、債権譲渡登録制度に則って、債権譲渡登記ファイルに記録する方法です。以下、順に紹介していきますね。
① 確定日付のある証書で通知してもらう方法について
この方法を採る場合には、まず、『誰から誰に対し』通知する必要があるのかを、しっかりと押さえておくことがポイントです。
この点について、民法467条は、債権譲渡の第三者対抗要件について、『譲渡人』から『債務者(=譲渡した債権の債務者)』に対し通知すべきことを、求めています。
ですから、T社長が譲渡担保権者の場合には、相手の会社(設定者)から譲渡債権の債務者に対し「T社長の会社に、こちらの債権を譲り渡しました」というメッセージを、確定日付のある証書をもって通知してもらう必要があります。なお、一般的には確定日付のある証書として内容証明郵便を用いることが多いです。
次に、債権譲渡登記ファイルに記録することで、対抗要件を備える方法ですね。この手続は法務局で債権者と債務者が協力して行う必要があり、この際に登録免許税がかかります。なお、「登録免許税」の額については、法務省の公式ホームページをわかりやすく書かれていますので、ご一覧下さい。
▶参考情報:(法務省ホームページ「登記申請の手続」)
債務者がこの協力を拒んでくるケースもあります。ですから、T社長が債権者の立場で、譲渡担保を活用する場合には、譲渡担保契約書の中に、「債務者は、債権者の求めに応じて、誠実に内容証明郵便の通知や債権譲渡登記手続に協力すべき」旨の条項を盛り込んでおきましょう。
- 設定者の不適切な行為への対応策
-
譲渡担保においては、設定者の不適切な管理により担保が滅失・毀損したり、設定者が勝手に担保物件を他の誰かに処分してしまうという事態が起きることがあります。万一にもこうした事態に陥ると、担保を失ってしまったり、その譲受人が判明しても返還を求めることが難しくなってしまうおそれがあります。そのため、実務では、このようなリスクを防ぐ手段として、占有移転禁止の仮処分の申立て(民事保全法23条1項)や、債務者に対する担保物件の引渡請求といった方法を用いることがあります。ただし、これらの手段は対応が遅れると適切に機能しないので、できるだけ早めに弁護士に相談するようにしましょう。
譲渡担保を実行するときは、どんな手続を踏むの?
(譲渡担保の手続きの流れ、実行の方法)
次に、相手は、担保物件(例えば、車や不動産など)を譲渡担保権者に引き渡します。ただし、すでに譲渡担保権者の下に担保物件がある場合には、この引渡しは不要です。
最後に、譲渡担保権者は、次の2つの方法のどちらかで清算を行うことになります。
① 処分清算方式:担保物件を他の人に処分して、その金額から本来弁済してもらうべきお金を回収し、差額があれば相手に返すという方法
② 帰属清算方式:担保物件を処分せずに自分のものにして、差額を相手に返すという方法
なお、どちらの方法によるかは、譲渡担保権者と設定者との合意で決めることになります。
譲渡担保について弁護士に相談できますか?
(外部弁護士に依頼することのメリット)
ですが、譲渡担保は、使いやすさの反面で、その有効な取得や、安全でスムーズな担保実行を確保するために、個別のビジネスごとに、将来起こり得るリスクを想像しながら、きちんとした対策を練った上で活用していくことが、とても大切です。
そして、この判断を適切に行うには、専門的な法律知識や豊かなビジネス戦略の経験が必要となりますので、専門の弁護士に相談しながら、譲渡担保の活用の有無やその内容・方法について決めていくことを、おすすめします。
まとめ
しかしながら、その一方で、抵当権や質権などと比べると、若干保護が弱くなってしまう場合もあり、また、状況によって複雑な判断が必要になることもあります。
ですから、少しでも迷ったり、不安に思ったときには、弁護士と連携しながら、譲渡担保の活用や対応策を練っておくことを、おすすめします。
また、このように譲渡担保を適切に使うよう心がけることで、会社としてもリスクヘッジが強くなりますので、色々なビジネスに挑戦していけるんです。
譲渡担保を上手く使って、将来のビジネス成功に繋げていきましょう。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」