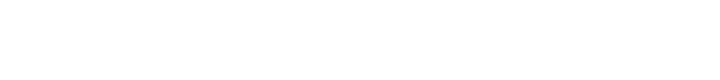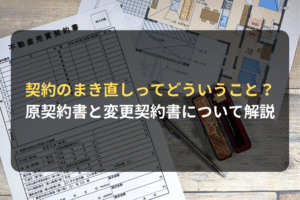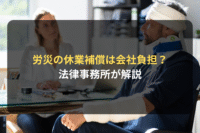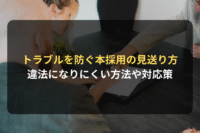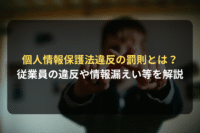- 2024.07.31
2024年4月以降も職業安定法並びに施行規則に違反せずに求人を行うにはどうすればいいですか?(改正のポイントと、企業がすべきことを弁護士がわかりやすく解説)
改正後の職業安定法(2024年4月1日施行)に違反しないため、求人の際に会社でやっておくべき事項って何ですか?という社長のご質問に対し、弁護士がお答えします。法改正のポイントについて、わかりやすく解説しています。
目次
職業安定法とは、どんな法律?
(職業安定法の概要や今回の法改正の背景について、簡単に解説)
▪求人の際に明示しなければならない労働条件の追加
▪手数料表等の情報提供の方法
なお、法改正の背景には、労働基準法施行規則の改正があります。職業安定法と労働基準法は、適用のタイミングに若干の違いはあるものの、ともに雇われる側を保護する法律であり、『明示すべき労働条件』については一部共通する規定を置いています。そこで、予定されていた労働基準法施行規則の改正に合わせて職業安定法施行規則も改正しておこうという流れになったわけです。
- 派遣元に対し労働条件を明示すべき義務があるか?
 T社長わが社で派遣社員を募集したい時にも同様に労働条件の明示が必要でしょうか?
T社長わが社で派遣社員を募集したい時にも同様に労働条件の明示が必要でしょうか?
労働者派遣法では、派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結するに際して、派遣労働者の業務の内容や就業場所、就業時間などを定めることを規定しています。(労働者派遣法第26条1項)また、派遣元は派遣労働者に対して、上記の内容を含む就業条件等を明示することが義務付けられています。(労働者派遣法第34条1項)
つまり、派遣先(T社長の会社)から派遣労働者に対しては労働条件を明示すべき義務はありませんが、実質的には、派遣労働者に対し『どのような環境で働くことになるのか』という点についてしっかりと伝えられる仕組みになっているということですね。 小野弁護士
小野弁護士
2024年4月以降の変更点
(職業安定法の施行規則の改正により追加されたルールについてわかりやすく解説)
2024年4月施行の法改正で追加された相手に明示すべき労働条件とは?
(同法施行規則4条の2第3項)
①従事すべき業務・就業場所の変更の範囲
②有期労働契約を更新する際の基準・更新回数の上限
以下、順に説明しますね。
①従事すべき業務・就業場所の変更の範囲
たとえば、雇用後に異動で業務内容が変わったり、転勤や出向によって就業場所が変わることが考えられますよね。そこで、雇い入れ直後だけでなく、今後の見込みも含めた業務内容や就業場所を明示することが義務付けられたんです。
確かに、おっしゃるように、雇う側からすればやや負担でもあります。しかし、変更の範囲を適切に労働者に知らせておくと、雇われる側もそのことを理解したうえで入社するわけですから、腰を据えて働いてもらうことが期待できます。
②有期労働契約を更新する際の基準・更新回数の上限について
従来は、無期雇用契約(期間の定めなし)であるかそれとも有期労働契約(期間の定めあり)であるか、また、有期労働契約の場合には契約の開始日と終了日という点について明示すればよいとされていました(「厚生労働省令第89号」参照)。
しかし、今回の改正によって、更新基準に関する事項(労働基準法18条1項の通算契約期間のこと)、および、更新回数に上限を設けた場合にはその上限を明記することが義務付けられました。
なお、実務では、更新基準を明示するときは、『契約更新の際にどのようなことが考慮されるのか』という点について、なるべく具体的に明示することが望ましいとしています。下記のQ&Aも参考にしてみてくださいね。
https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf
(厚生労働省ホームページ「令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)」)
具体的な明示例
(記載例)
|
業務内容 |
(雇い入れ直後)営業事務(変更の範囲)想定される業務内容を記載 |
|
就業場所 |
(雇い入れ直後)○○支社 (変更の範囲)想定される支社・営業所名を記載 |
(記載例)
|
契約期間 |
期間の定めあり(2024年5月1日~2025年4月30日) |
|
|
契約の更新 パターン① |
更新あり(契約期間満了時の業務量・勤務成績により判断) 通算契約期間は4年を上限とする |
|
|
契約の更新 パターン② |
更新あり(自動更新とする) 契約の更新回数は3回を上限とする |
|
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
(厚生労働省ホームページ「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」)
- 有料職業紹介事業者の手数料等の掲示方法の追加について
-
有料職業紹介事業者は、職業紹介にあたって求人企業や求職者から徴収する手数料について、手数料表を作成して厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられています(職業安定法第32条の3第1項)。従来は、この手数料表を事務所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示することが義務化されていましたが、今回の改正により、事務所内の掲示に加えて、インターネットやその他の適切な方法によって掲示・情報提供することが可能になりました(職業安定法施行規則第24条の5第4項)。人材紹介会社を検討する際には、その会社のホームページ等から紹介手数料を確認してみるとよいでしょう。
▪https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf(3ページ目)
(厚生労働省ホームページ「令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)」)
労働条件を明示すべきタイミングや方法
求人の際には職業安定法に定める労働条件を、そして雇い入れ・契約更新の際には労働基準法に定める労働条件を明示することになります。今回の改正で追加された労働条件も忘れずに明示しましょう。
もう1つ注意したいのは、自社ホームページで求人を出す際にも労働条件の明示しなければならないということです。
自社HPに求人を出す行為は「労働者の募集」に該当するため、職業安定法の規制の対象となり得るんですよ(職業安定法第4条、4条の3)。
▪詳細は面接時に話す旨をきちんと伝えること
▪面接時に記載できなかった一部の労働条件を伝えること
(「令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A」参照)
▪早い段階でその旨を伝えること
▪書面など残る形で伝えること
▪求人票や求人サイト、自社HPの内容、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等の該当部分についても忘れずに変更すること
適切に労働条件を明示しなかった場合のペナルティやその他のリスク
たとえば、明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法15条2項)。要するに、予告なく突然に退職されてしまうということです。予期せぬ欠員は、社内の雰囲気の悪化・業務が回らないといった事態を招くおそれがあります。加えて、退職の原因を作ったのは求人企業側なので、人材紹介会社の返戻金制度も適用されず、採用にかけた費用が無駄になってしまうリスクもあります。
また、たとえ退職問題にまでならなくても、労働者と会社との間で大きなトラブルに発展してしまうことも想定されます。
その他にも最近だと、労働条件が異なることで裏切られた気持ちになり、労働者が退職後にSNSや口コミで悪評を書き込み、それが拡散してしまうケースもあります。そうすると、応募者が減りまたは退職者が増えて業務に必要な人員を確保できなくなったり、取引先からの信用が低下するなど、様々な不利益に晒されてしまう可能性もあります。
会社が求人を行う際の法的チェックについて、弁護士に相談できますか?
(法律事務所に対し、会社の求人に関するリーガルチェックを依頼・問い合わせることのメリット)
まとめ
気になる点はもちろん、労働条件の相場といったビジネス的な部分についても、遠慮なくご相談くださいね。適切な求人は優秀な人材の確保、人材の安定につながり、T社長のビジネスの発展の助けになると考えます。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」