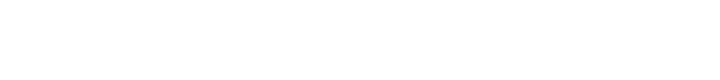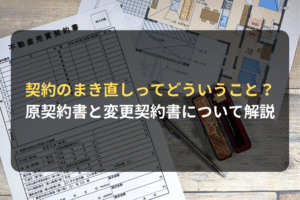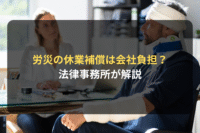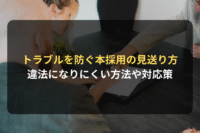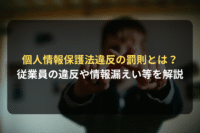- 2024.06.21
法律を知ることで、会社の広告を使った収入を増やすことができますか?(景品表示法の定める優良誤認表示・有利誤認表示とは)
景品表示法で規制される表示・広告って何ですか?という社長のご質問に対し、弁護士が会話形式でお答えします。景品表示法のいう優良誤認・有利誤認の内容や、両者の違いなどを、具体例を使って、わかりやすく解説しています。
目次
- 1 優良誤認や有利誤認って、何ですか? (景品表示法の目的を踏まえて、同法の規制する「表示」の範囲、優良誤認表示・有利誤認表示の定義や内容および両者の違いについて、簡単に解説)
- 2 優良誤認や有利誤認には、例えば、どんなものがある? (優良誤認表示・有利誤認表示の要件や事例について、簡単に説明)
- 3 景品表示法に違反したらどうなる? (景品表示法への違反時のリスク・ペナルティー)
- 4 景品表示法への違反リスクを下げるには、どんな方法がある? (社内コンプライアンス体制の見直しや行政(消費者庁)側の見解のチェックを利用した、法令遵守に向けた対策について、簡単に紹介)
- 5 会社の広告の法的チェックについて、弁護士に相談できますか? (法律事務所に対し、会社の広告のリーガルチェックを依頼・問い合わせることのメリット)
- 6 まとめ
優良誤認や有利誤認って、何ですか?
(景品表示法の目的を踏まえて、同法の規制する「表示」の範囲、優良誤認表示・有利誤認表示の定義や内容および両者の違いについて、簡単に解説)
景品表示法が規制する「表示」とは?
T社長がお考えのように、景品表示法のポイントをしっかりと押さえることができると、安心して広告を活用できるようになるので、ビジネスを拡大していくことができますね。また、適切な広告を心がけることは、会社の信用を守ることにも繋がるんですよ。
お客さんを呼び込むために行われる、自社の商品・サービス(役務)の取引に関する事項について行う広告・表示であって、内閣総理大臣が指定する方法または媒体を使っているもの(景品表示法2条4項参照)。
この点については、行政のホームページに詳しく書いてあるので、下記リンクから、一覧しておくといいですよ。
※消費者庁ホームページ「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」
優良誤認とは?
優良誤認表示とは、商品・サービスの品質、規格その他の内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると示したり、嘘をついて同種・類似の他社の商品やサービスよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを指します。(景品表示法5条1項)
たとえば、ビタミンCのサプリメントを販売するA社が『他社のビタミンC配合のサプリメントとは違って、うちの会社のビタミンCサプリメントには若返り効果がありますよ!白髪がなくなります!』とうたって、商品を消費者に売り込むとしましょう。
この場合、消費者は『もう少し、いろいろと吟味して商品を選ぼう。』という自主的な判断も、『ビタミンCのみで白髪がなくなるとは限らないし、ビタミンCの含有量をチェックしないと、本当によいサプリメントか分からないよね。』という合理的な判断もできなくなってしまうかもしれません。
ですから、景品表示法では実際よりも商品を良いものだと表示したり、嘘をついてほかの会社の同じような商品より良いものだと表示したりして、消費者の正しい商品選びを邪魔する優良誤認表示を禁止しているんです。
有利誤認とは?
有利誤認表示とは、商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものや、他社の同種・類似の商品・サービスよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを指します。(景品表示法5条2項)
たとえば、引っ越し業者A社が消費者に対し、実際の引っ越し料金を明らかにしないで、見積書で『半額の100万円で運びます!』と提示するとしましょう。でも実際には、本来の引っ越し料金が200万円と認められない場合、A社が消費者に対して提示(表示)した見積書は有利誤認表示に該当する可能性があります。
その他に内閣総理大臣が指定する表示とは?
この点については、実際に指定されているものを紹介しましょう。
⑴商品の原産国に関する不当な表示
⑵無果汁の清涼飲料水等についての表示
⑶消費者信用の融資費用に関する不当な表示
⑷不動産のおとり広告に関する表示
⑸有料老人ホームに関する不当な表示
⑹一般消費者が事業者の表示であることを判断することが困難である表示
※消費者庁ホームページ「景品表示法、表示関係 告示」参照)
また、価格やサービス内容、商品の質について消費者が正しく吟味し選択をするようになると、企業同士の競争の主戦場は『より良い消費品やサービスを追求すること』に集中します。このことは、結果として、お客さんの満足度を高めることに繋がり、企業は売上(成績)として返ってきます。
|
|
優良誤認 |
有利誤認 |
|
対象 |
商品やサービスの品質や規格(商品やサービスそのもの) |
商品やサービスの価格や取引条件(消費者が商品やサービスを選択する判断過程) |
|
(例)牛肉の販売 |
実際はそうでないのに高級ブランド牛と表示する。 |
実際はそうでないのに、他社より50%安く購入できると表示する。 |
|
(例)マッサージ店の施術 |
実際はそうでないのに、全員がマッサージに関連する資格を持って施術すると表示する。 |
実際はそうでないのに、近隣マッサージ店の相場を高く表示し、自社なら安く施術を受けられると表示する。 |
- 景品類に対する規制について(景品表示法4条)
- 実は、景品表示法は、不当な広告・表示のほかにも規制しているものがあるんですよ。
 小野弁護士
小野弁護士
 T社長そうなんですか?ぜひ、教えて欲しいです。
T社長そうなんですか?ぜひ、教えて欲しいです。
もちろんです。結論から言うと、それは『景品類』ですね。 小野弁護士
小野弁護士
 T社長いわゆる、粗品・おまけ・商品といった類いのものでしょうか?
T社長いわゆる、粗品・おまけ・商品といった類いのものでしょうか?
はい、それらのものも景品類にあたります。ですが、景品表示法では、もう少し広く規制対象としているんですよ(消費者庁ホームページ「景品規制の概要」参照)。具体的には、景品類は、以下の3つの種類に分類することができます。 小野弁護士
小野弁護士
⑴ 一般懸賞:商品・サービスの利用者に対して、くじ等の偶然性や特定行為の優劣等によって景品類を提供することを『懸賞』といいます。⑵で紹介する『共同懸賞』以外のものは『一般懸賞』といいます。(例:抽選やじゃんけんによって提供されるもの)
⑵ 共同懸賞:複数の事業者が参加して行う懸賞を指します。(例:ショッピングモールで行われる抽選会)
⑶ 総付景品(そうづけ景品):『ベタ付け景品』とも呼ばれ、懸賞によらずに一般消費者に提供される景品類を指します。懸賞とは違い、サービス利用者や来店者に対してもれなく提供されるのが特徴です。(例:ペットボトル飲料に添付されているおまけのグッズ)」
その他にも、下記の通り、提供できる景品類の限度額が決められています。 小野弁護士
小野弁護士懸賞による取引価格
最高額
総額
一般懸賞(5,000円未満)
取引価格の20倍
懸賞に係る売上予定総額の2%
一般懸賞(5,000円以上)
10万円
懸賞に係る売上予定総額の2%
共同懸賞
取引価格にかかわらず30万円
懸賞に係る売上予定総額の3%
総付景品(1,000円未満)
200円
総付景品(1,000円以上)
取引価格の10分の2
(消費者庁ホームページ「景品規制の概要」参照)
 T社長かなり細かく、提供できる景品について決められているんですね。
T社長かなり細かく、提供できる景品について決められているんですね。
はい。景品と聞くと、みんな魅力的に感じてしまいますよね。ですから、消費者が景品類の方に夢中になってしまい、質の悪い商品やサービスを購入してしまうことがないように、詳細なルールを定めているんです。 小野弁護士
小野弁護士
優良誤認や有利誤認には、例えば、どんなものがある?
(優良誤認表示・有利誤認表示の要件や事例について、簡単に説明)
優良誤認の要件・具体例
優良誤認表示の要件は、①商品やサービスの品質・規格その他の内容について、②一般消費者に対し、実際よりも著しく優良であると・実際はそうでないのに競合他社よりも著しく優良であると示す表示であって、③不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的で合理的な選択を阻害する恐れのあるもの、この3点です。
|
対象商品・サービス |
表示 |
実際 |
|
料理・メニュー・店頭看板・ウェブサイト |
『松坂牛入荷いたしました』『最高級の松坂牛をお楽しみください』等と記載することにより、あたかも、提供する料理に松坂牛を使用しているかのように表示した |
提供する料理には、松坂牛でない和牛が使用されていた |
|
一般照明用電球型LEDランプ・店頭POP |
あたかも、白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることができるかのように表示 |
用途によっては、白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることができないものだった |
|
粉末飲料・パンフレット |
あたかも、独立行政法人国民生活センターによる試験の結果、対象商品がポリフェノール含有量日本一のお茶であると認められたかのように表示 |
独立行政法人国民生活センターが対象商品のポリフェノール含有量について、試験を行ったという事実はなかった |
(消費者庁ホームページ「景品表示法における違反事例集」参照)
有利誤認の要件・具体例
有利誤認の要件は、①商品やサービスの価格その他の取引条件について、②実際のもの、競合他社よりも取引の相手に著しく有利であると一般消費者に勘違いさせる表示であって、③不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的で合理的な選択を阻害する恐れがあると認められるもの、この3点です。
|
対象商品・サービス |
表示 |
実際 |
|
スーパーで販売する食品・チラシ |
実際の販売価格と一緒に『当店価格』という比較対照価格を表示し、あたかも実際の販売価格が『当店価格』に比べて安いかのように表示 |
『当店価格』という比較対照価格は、実際に販売する予定・販売されていた値段ではなかった |
|
精肉に関するチラシ・CM |
『毎月29日は肉の日』『牛肉が半額!当日表示価格より』等の映像や音声を放送し、あたかも特売日の売出しにおいて、精肉を通常時の半額で販売するかのように表示 |
特売日の売出しにおいて、対象となる精肉のパッケージに記載された通常価格の多くは、本来の通常価格をいったん引き上げた価格であって、実際は通常時の半額ではなかった |
|
振袖に附属品等を組み合わせたセット商品に関する冊子 |
『コーディネート価格』という実際の販売価格と一緒に『標準小売セット価格』という比較対照価格を表示し、あたかも、実際の販売価格(コーディネート価格)が標準小売セット価格より安いかのように表示 |
『標準小売セット価格』という比較対照価格は、架空の価格であった |
(消費者庁ホームページで『景品表示法における違反事例集』参照)
▪景品表示法における違反事例集
景品表示法に違反したらどうなる?
(景品表示法への違反時のリスク・ペナルティー)
課徴金の対象となる行為は①優良誤認表示②有利誤認表示です。不当表示行為の防止や、不当表示行為の被害の回復を目的としています。
課徴金額の算定方法は、原則不当表示行為から一定期間内(6ヵ月)において対象となる商品やサービスの売上金額の3%です。
1つは、わざと不当表示をしたわけではない事業者であっても、措置命令や課徴金納付命令の対象になるということです。
もう1つは、不実証広告規制というルールについてですね(景品表示法7条2項、8条3項)。
具体的に言うと、行政から『不当表示の疑いがあるので、もし違うなら裏付けとなる資料を提出してください』と求められた場合、これを無視すると、不当表示があったものとして取り扱われてしまうリスクがあるということです。
特に、措置命令との関係で言うと、どれだけ不当表示でないことを裏付ける有力な証拠を持っていようと、ひとたび無視してしまうと、反論する余地すらもらえなくなってしまいます。
なお、これらの点についての具体的な対策は、後ほど、説明しますね(「4.景品表示法への違反リスクを下げるには、どんな方法がある?」参照)。
▪不実証広告規制に関する指針
- 適格消費者団体からの差止請求等を受けるケースとは?(景品表示法30条)
-
景品表示法に違反しまたは違反するおそれがある場合は、適格消費者団体から差止請求を受けるケースもあります。
また、一定の場合には、適格消費者団体から事業者に対して、表示の根拠となる資料の開示を要求できる旨が、2024年施行予定の法改正で決められました。事業者には、この要求に応じる努力義務が課されます。
加えて、一般の消費者を契約の相手とする以上、後になって取り消されないよう、表示・広告をする際には、商品・サービスの品質・用途・価格などについて正しくはっきりと書いておくことや、契約書もわかりやすく書いてあるものを使うことが望ましいことにも、留意しておくとよいでしょう(消費者契約法4条、3条1項等参照)。
なお、適格消費者団体とは、消費者の利益を保護するため、消費者契約法上の差止請求権を行使できることを、内閣総理大臣から認定された消費者団体で、全国に26団体あります。
景品表示法への違反リスクを下げるには、どんな方法がある?
(社内コンプライアンス体制の見直しや行政(消費者庁)側の見解のチェックを利用した、法令遵守に向けた対策について、簡単に紹介)
具体的な対策については、
・広告業務に関係する従業員に対し、景品表示法の考え方を共有し、その広告に関するお客様からの問い合わせに対応できるように備えること
・関係部門(商品・サービスの製造・開発・企画を担当する部門、広告・営業を担当する部門、法務を担当する部門など)の間で連携し、認識の違いを防いで、誤ったセールスをしないようにすること。例えば、製造業の場合、材料の調達・供給といった、実際に製造に関わる部門と、商品販売を行う営業部門などが商品知識を共有する等
・効果・効能について表示・広告をする場合には、その効果・効能の根拠となる資料(公的機関の調査結果、専門家の意見)を保管しておくこと
(令和4年6月29日内閣府告示 『事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針』参照)
などが挙げられますが、まだまだ社内コンプライアンス体制の見直しとして、取れる対策はたくさんありますよ。
▪景品表示法等関係ガイドライン
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline
▪よくある質問コーナー(景品表示法関係)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/index.html
- 官公庁への相談・問合せ
 T社長先生!見解チェックを見てみたのですが、いまいち疑問が解決しない部分もあります…そんなときはどうしたらいいのでしょうか?
T社長先生!見解チェックを見てみたのですが、いまいち疑問が解決しない部分もあります…そんなときはどうしたらいいのでしょうか?
そういった場合には、消費者庁の表示対策課・指導係に、事業者がこれから行う企画について相談できる窓口がありますよ。回答に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって問い合わせをすることがポイントです。 小野弁護士
小野弁護士
▪景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/
会社の広告の法的チェックについて、弁護士に相談できますか?
(法律事務所に対し、会社の広告のリーガルチェックを依頼・問い合わせることのメリット)
まとめ
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」