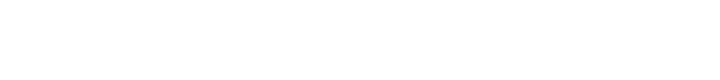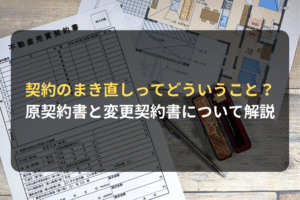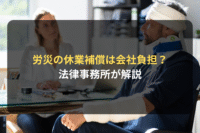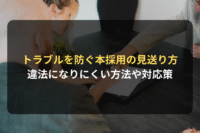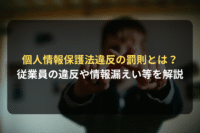- 2024.06.10
法律を活用して社内のトラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?(予防法務の具体例と、臨床法務・戦略法務との違いを解説)
目次
予防法務って何ですか?
健全な会社経営を行うには、先手を打って法令に沿った体制・運用を構築しておくことが大切です。予防法務を活用して、社内のトラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?という社長のご質問に対し、弁護士が会話形式でお答えします。
たとえば、T社長の会社が、ほかの会社と何か商売をするとき、契約書を交わしますよね。その契約書に自分の会社がしたいことが書かれていなかったり、不利な条件になっていないかどうかをしっかりチェックしていないと、後になって「取引が思っていたものと違うから、契約内容を変えて欲しい」と相手に言っても、「無理です」って言われてしまうこともあります。
また、従業員がたくさんいる会社では、従業員がうっかり社外に大切な情報を漏らしてしまうなどの事件を、新聞やニュースで目にすることもありますよね。
ですから、こういったトラブルが起きないように、契約書をきちんとチェックしたり、社内ルールを確認したりするんです。
ですから、会社が安心で気持ちのいいビジネスをしていくためには、予防法務は欠かせません。
また、社員の残業時間を適切に管理するなど、労働法違反にならないように労務管理を行うことで、社内トラブルや、行政からお叱りを受けないようにすることも、具体例として挙げられますね。
- 臨床法務・戦略法務とは
-
会社の法務には、『予防法務』の他にも、『臨床法務』、『戦略法務』という2つの大切なポイントがあります。まず、予防法務とは、病気に例えると、風邪をひかないように予防接種をするようなもので、トラブルが起きないようにするための手段です。これに対して、臨床法務とは、病気になった後の治療のようなもので、すでにトラブルが起きてしまった後に、それを解決するための手段になります。そして、戦略法務とは、これらとは少し違って、会社がビジネスを広げて、利益を増やすために、法律をうまく活用することをいいます。たとえば、新しい商品について特許を取得して、ライバルたちに差をつけて会社の儲けを増やす、といったことです。これらの3つの法務を、上手に連携させることで、予防法務の効果をより会社の望むものへと高めていくことができます。

予防法務には、他にもメリットがありますか?
(コンプライアンス体制強化の重要性)
予防法務って、何をすれば良いですか?
(予防法務の具体例とおすすめ)
契約書のチェック
適切な社内ルールの作成
たとえば、SNSの使い方や、ハラスメントを防ぐルール、契約書の管理方法など、会社の経営のためのさまざまなルールを作ります。
アイデア・デザインなどを守る
たとえば、自社の特許やデザインが他の会社に勝手に使われないようにしたり、逆に、他人の特許を間違って使わないように気をつけたりします。これを怠ると、会社の売上が落ちてしまったり、他の会社からクレームを入れられてしまうこともあります。
社員の働くルール
たとえば、有給休暇の取り方などを法律に合わせて管理します。法律に違反すると、会社や従業員にトラブルが起こることもあるので、これも大切です。
株主総会のサポート
株主は、会社にお金を出してくれている人たちですので、株主に親切に対応することは、会社の経営を安定させることにもつながります。
官公庁への問い合わせ
- グレーゾーン解消制度とは
-
「グレーゾーン解消制度」とは、産業競争力強化法に基づいて、会社などが安心して新しい事業活動を行えるように、具体的な事業計画にそって、あらかじめ法律や規制が適用されるかどうかを、行政に確認できる制度です。
予防法務は社内の誰に任せるのが良いですか?
(法務担当者に求められる適性)
経験
知識
柔軟性
予防法務を弁護士に相談することはできますか?
また、新しい法律が制定されたり、すでにある法律が改正されるときなど、自分の会社だけでは『会社として何をすればよいのか』を調べるのが難しい場合もあります。そんなときにも、外部の弁護士にお願いしておくと、会社の代わりにきちんと調べて教えてくれるので、とても安心です。
このように外部の専門家にも協力してもらうと、会社は新しいビジネスにもっと挑戦できるようになるので、会社の利益にもつなげることができます。
AIを予防法務に使うことはできますか?
また、特に日本のように、紛争はできるだけ避けて、お互いにとって公平な取引を大切にする文化のもとでは、AIの提案をそのまま使うのではなく、目の前のビジネスの内容、相場、相手の立場などを考えて、お互いの利益を調整することが、大切なポイントでもあります。もっとも、この判断には、法的に豊かな経験・知識が必要になります。
ですから、会社でAIを使うにしても、AIも詳しい弁護士などの外部の専門家と協力しながら、ビジネスを進める方が、安心だと思いますよ。
まとめ
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」