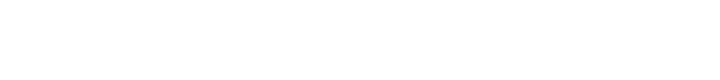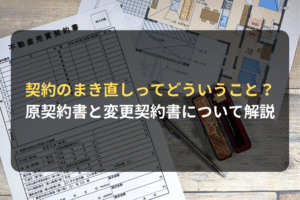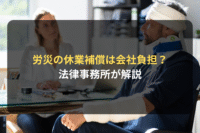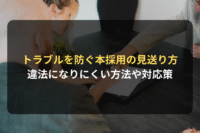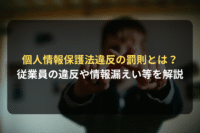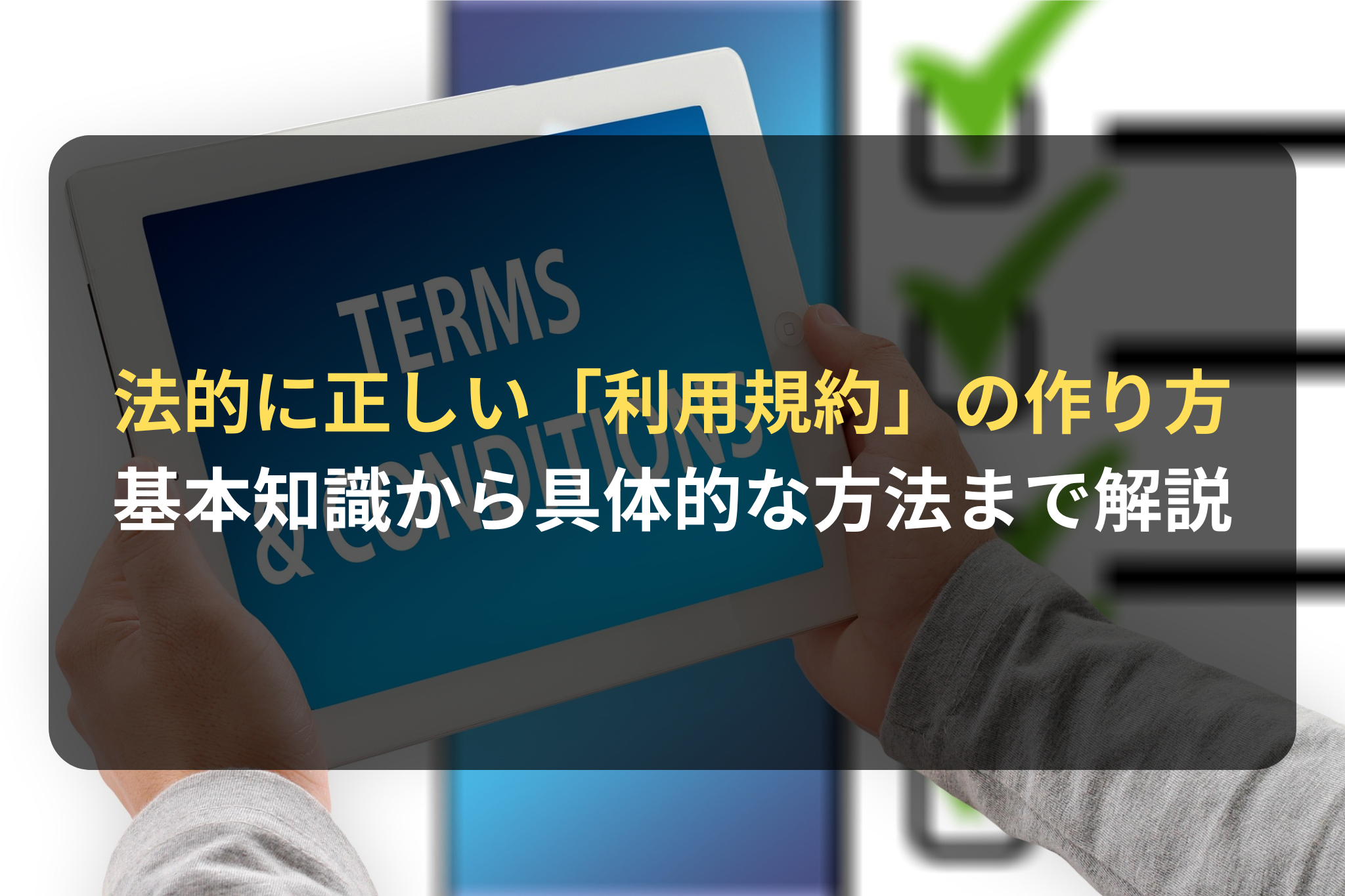
- 2024.06.10
「利用規約」を法的に正しく作るために必要な知識は?(基本知識から必要項目、「契約」との違いや具体的な作り方まで解説)
インターネット経由で多数のユーザーへ自社サービスを提供する場合には、しっかりとした「利用規約」を作り、ユーザーにはその内容に同意してもらうことが重要です。今回は「利用規約を作りたいけれど作り方が分からない」という社長のご相談に、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
「利用規約」を作るときにまず必要なことを教えてください。(利用規約の基本知識)

実際にそのサービスを利用するためには、同意することが必須となっているケースがほとんどですね。特にネットサービスの場合、ユーザーが利用方法などについて交渉をしたうえで個別の約束ごとで利用開始する、というようなことは現実的に起こらないため、利用開始したユーザーは、すなわち規約内容を理解したうえで利用開始したというふうに扱われるのです。
もし利用規約がないままサービスを提供したらどうなりますか?(利用規約の必要性)

法的には、利用規約というものは絶対に作らなければならないというものではありません。
しかし特にネットサービスは、顧客と対面したり契約書を交わすこともないまま、大量の利用者に即時的にサービスを提供するというものですから、万が一ユーザーとの間で後々トラブルがあった際に、『規約への同意をもらっていた』という経緯を予め踏まえていないと、対処やトラブルの解決が難しくなるでしょう。
例えば、ネット上の掲示板のようなサービスを提供していて、ユーザーから不適切な投稿や、自社や第三者に著しく不利益になるような投稿があったとします。約束ごとがなかったわけですから逆に考えれば、事業者側の判断でその書き込みを削除することもできなくはないですが、ユーザー側に『自分の貴重な発信内容を勝手に削除された』と反感を持たれてしまうこともあります。
その場合、状況によっては民法が適用され、ユーザー側が事業者側の行為によって損害を受けた場合には、債務不履行や不法行為にあたるおそれがでてきてしまいます。そこまでいかなかったとしても、理不尽な対応をされたと受けとられたまま、悪評を広められるなど無用なトラブルにも発展してしまいかねません。
しかし、利用規約があってそこに『投稿が法令に違反した場合や、事業者が不適切と判断した場合は利用者の了解を得ることなく削除できる』と書かれていれば、事業者判断で削除できますし、削除の行為も正当化できるのです。
これは実際の判例であったケースなのですが、このようなデータ消失でのユーザーからの損害賠償請求にあたって、とあるサーバー事業者は2,000万円以上もの損害賠償を裁判所から命じられました。一方で違うサーバー事業者の例では、同じような状況でも事業者側が完全勝訴となり、賠償責任を負うようなことはありませんでした。
この違いは何かというと、後者の勝訴した事業者は、利用規約上で『ユーザーのデータが消失しても、賠償責任を負わない』ということを明記していたのです。
- 民法に基づく債務不履行・不法行為
-
もし利用規約がなかった状態で前述のようなトラブル・損害賠償請求などが起きた場合には、“私人(国や行政以外のこと。事業者含む)”間の生活関係において適用される法律である、「民法」で裁かれることとなります。
利用規約で損害賠償責任の有無や賠償責任の上限などを契約できていない状態で民法が適用されると、債務不履行(民法第415条)や不法行為(民法第709条)にあたってしまった場合に、大きなリスクを負うこととなります。参考:e-Gov法令検索 民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
「規約」と「契約」の違いとは何でしょうか?

利用規約は、不特定多数のユーザーに対して共通の内容として適用される、サービス利用上のルール説明のようなイメージですね。利用規約は一般的にはサービスの提供者側が一方的に作成するものなので、ユーザーとの個別交渉で内容が変わるようなことはありません。
契約のほうは、約束ごとの内容について契約当事者どうしが自由に交渉・判断などを行ったうえで、最終的に合意のうえで結ぶものです。また、口頭での合意契約が成立する一部の場合を除き、基本的には契約書を作成して契約書上で契約を締結します。
いないとは言いきれませんね。ただしその場合でも、画面上で規約内容に同意する意思を示す操作をしていれば、基本的に『読んでいなかったから無効』というような言いぶんは通用しません。『契約書をよく読まずに契約を結んだ』ということが基本的に通用しないのと同様です。
ただし、『明確に規約内容を伝えてユーザーの同意を得たのだ』と事業者側が主張するためには、例えば規約内容を全部表示したうえで同意ボタンへ遷移するつくりにしてるなど、いくつかの注意点があります。この点は後ほど、利用規約の作り方や注意点としてまとめてご説明しますね。
- 規約と「約款(やっかん)」は同じもの?
-
約款も規約と同じように、不特定多数のユーザーへサービス提供する場合などに、その利用ルールを一律の内容として明文化しておくものを指します。明確な違いとしては、約款が定型的な契約条項を不特定多数に対して明示するものであるという定義があるのに対して、規約のほうは、ほぼ同じ目的で利用されるものの、法律上は厳密な定義がなく言葉としては「提供するサービスのルールを明示するもの」という程度の意味合いにとどまっているという点があります。
ただし実質的に一般社会では、「規約」も「約款」も同じ意義で使われることが多い言葉です。利用規約(定型約款)の法的効力
実は2020年の民法改正までは、利用規約には厳密な法的効力はありませんでした。特に、利用規約の内容をしっかり認識していなかった場合や、内容を変更する場合の取扱いについて明確ではなく、裁判所も事例ごとに個別に解釈を示していたのです。
民法改正後、主に以下の要件を満たす約款が「定型約款」と定義され、明確に法的効力を持つものとして定義されました。詳しくは、民法第548条「定型約款」を参照ください。- ある特定の者(事業者)が不特定多数を相手方として行う取引であること
- 取引の内容の全部または一部が画一的であり、双方にとって合理的なものであること
- 契約の内容とすることを目的としており、その特定の者(事業者)により準備されたものであること
参考:e-Gov法令検索 民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
利用規約に記載すべき項目

はい、ご説明します。利用規約というものは、サービスのルール説明になりますから、どうしても自社サービスの独自性を踏まえたうえでオリジナルのものを作成する必要があります。そのため、どのケースにもあてはまる雛形というかたちではお伝えできないのですが、主に共通する重要な構造や項目について解説しますね。
まずは何より、利用規約の内容がユーザーとのしっかりした契約内容であると主張できるようにするためには、規約内容を契約の内容とする旨をしっかり表示し、ユーザーがその内容を確認したうえで同意したと解釈できるつくりにする必要があります。
具体的には利用規約の全文が同意まえに表示されるつくりにし、利用規約への同意を行わなければ申し込みに進めない仕組みにします。
仰るとおりです。また、『利用規約が契約内容となることに同意しました』というようなチェックボックスが配置されていて、そこにチェックを入れないと先に進めないというようなつくりも、よく目にしますね。
規約内容で用意すべき項目については、まずは提供するサービスについての分かりやすい説明が必要です。特に有料でサービスを提供する場合には、料金の対価として具体的にどういったサービスを提供するのか、サービスの範囲まで含めて明確に示しておきます。
もしこの部分が不明確になっていると、自社がどういったサービスを継続すべきかということが曖昧になってしまったり、ユーザー側からも過大なサービスを要求されたり、といった問題につながりかねません。
御社のように商品を販売するサイトであればサービス内容は明確で、対価についても商品代と引き換えに商品を送付、ということになるかと思いますが、商品のラインナップとして自社商品のすべてをネット販売する予定なのか、一部の種類のみなのか、ネット販売限定商品があるのかといったことも決まっている範囲で、説明しておいたほうがよいでしょう。
また商品代金以外に、例えばサイト利用自体を有料にして、別途付加価値を付けたりする場合にはその内容についても説明しておく必要がありますね。
そうですね。利用規約でそういったサービス内容も、提供が決まっている範囲で記載することになります。
あわせて、利用料金の額や支払い方法も重要です。一度の支払いで済むのか月額など定期的な支払いになるのか、クレジットカード決済や口座引き落とし、請求書払いやコンビニ払いなどどういった決済方法が可能なのかも明示します。
そのほか大切となるのは、自社サービスの利用に関するルール、禁止事項やサービスの利用停止条件などですね。例えばですが、御社の商品を高額転売目的で大量に購入するようなユーザーがいて品切れが続出したとしたら、純粋な御社の一般ユーザーが困ってしまいます。そういった事態を避けるために、転売発覚時に利用停止となる旨や、ひとりの人物が複数IDで別人になりすました場合の対応などを、規約で明記しておくのです。
そのほか、すでにご説明した企業側の損害賠償責任範囲やその他義務・権利等も事細かに明確にしておく必要があります。
- 利用規約上で明記される代表的な項目
-
-
- サービスの利用には利用規約への同意が必要であることの明記
明記するだけでなく、同意を示す操作をしないとサービス利用開始できないようなつくりにしておくことが大切です。 - 同意した規約内容が契約内容として取り扱われることの明記
利用規約を法的効力をもつ「契約」として取り扱うために必須となります。 - 利用規約内でもちいられる用語の定義
利用規約内では、同じ意味を指す場合は必ず同じ用語をもちいるように予め用語を整理しておき、その用語定義を利用規約の冒頭で明記しておきます。 - 提供サービス内容
ユーザーが利用登録をすること、および有料サービスの場合には料金を支払うことによって、具体的にどのような範囲でどのようなサービスを提供するかを明記します。 - 利用料金の額、支払方法
利用料金や可能な決済手段、支払いのタイミングなどを明記します。複数のサービスプランで違いがある場合は、プランごとの一覧などで明記します。 - サービス利用に関するルール、禁止事項
サービスを利用するにあたって、ユーザーに守ってもらいたいルールをしっかり明記します。 - 利用規約違反者に生じるペナルティ
規約違反があったユーザーに対してどのような措置をとる可能性があるのかを明記します。 - サービス内コンテンツについての権利の帰属
サービスサイト内の文章や画像などのコンテンツ、そのほか利用方法を限定するダウンロード配布コンテンツなどがある場合にはそれらも含めて、権利の帰属を明記します。 - 損害賠償、免責に関する事項
利用ユーザーに損害を与える事態がサービス内で起きてしまった場合の損害賠償有無や範囲、および提供情報の正確性や完全性、リスクなどに関しての免責事項や、個人情報の取扱範囲などを明記します。 - サービスの中止、変更や終了に関する事項
提供サービスの中止や変更、終了に関して事業者側の権利や予告義務、およびその際の料金の取扱いなどを明記します。 - 紛争時の裁判管轄
サービスの利用にあたって事業者と利用者の間に紛争が起きた場合に、どの裁判所が管轄となるかを明記します。
- サービスの利用には利用規約への同意が必要であることの明記
-
利用規約の作り方はどのような流れになりますか?

そうですね、実際に着手するとなったらぜひまたご相談いただきたいのですが、大まかに言いますと、まずは提供するサービス内容、事業者の権利とユーザーの権利など前提となる内容を整理することから始めます。
それらの詳細が決まったら、それぞれの権利をもとにユーザー側の禁止事項とすべき行為を整理しておくとよいでしょう。あわせて、違反があった場合の対応を整理します。
そして具体的な利用規約内容を精査しながら作っていくことになりますが、利用規約上で同じことを指す別の表現などがあるととても混乱を招きますし、トラブル時にも無効な記載と扱われかねないため、利用規約内でもちいる用語の定義もしっかりしておくことが大切ですね。
利用規約を作る際の注意点を教えてください。

そうですね、既にご説明した、利用規約を契約内容とする旨の明記に注意すること、『利用規約をすべて読み、同意します』というようなチェックボックスなどの対応のほかには、ユーザーが、利用開始時だけでなくいつでも容易に利用規約を閲覧しなおせるようにしておく必要があります。
また、利用規約の内容は、一方的に相手方の権利を制限するような内容であってはなりません。極端な例ですが、例えば『サービス提供者はどのようなことがあっても一切損害賠償責任を負わない』などと規定したとしても、紛争になった際に民法や特定商取引法上、効力を認められない可能性があります。
また法人ではなく個人ユーザーへのサービス提供の場合、消費者契約法において『消費者の利益を一方的に害する』とされる内容は無効になります。
法的な解釈は置いておいても、ユーザーに『細部まで読まないことを逆手にとって、完全に不意打ち的に変な約束ごとをさせられた』ととられてしまうような内容は、炎上騒ぎや企業イメージ失墜のリスクが大変高くなりますので、内容精査時にそのような記載がないか充分に注意を払ったほうがよいでしょう。
ちなみに利用規約を作るにあたって、Web上などで見つかる雛形を参考にするのはよいことですが、雛型だけで大部分を作ってしまうと、自社サービスの独自性が踏まえられていなかったり、有事の備えとして必要な項目がまったく盛り込まれていなかったりという状態になりやすいため、あくまで雛形は、ただき台として活用するにとどめることをおすすめします。
利用規約はいつでも自由に内容変更できるのですか?(利用規約変更時の注意点)

利用規約の変更や改定は時期に制限はありませんし、実際に必要に応じて利用規約が変更されることもごく一般的ですが、原則として利用者の合意が必要となります。変更や改定時にすでに登録解除しているような過去のユーザーは無関係ですので、その時点での利用者、利用登録をしているユーザー、ということになりますね。
ただし利用規約が民法でいうところの『定型約款』に該当していて、さらにいくつかの条件に合致すれば、変更内容や変更時期などをWebサイト上で掲載するだけでOK、つまりたくさんのユーザーへ個別に合意を求めなくても大丈夫ということになります。
いくつかの条件というのは例えば、変更の内容がサービス利用者にとって一般的に利益と考えられるような場合や、もともと契約をした目的に大きく反しない内容であり、変更の必要性や相当性がある、といったようなことです。
T社長がお考えのような、付加価値を付けるための変更ということであれば問題はなさそうですね。またその際は、細かくアドバイスさせていただきますのでご相談ください。
ちなみにもともとの利用規約にて『〇〇などの理由で利用者の合意なしに利用規約を変更することがある』という旨は記載しておいたほうがよいですね。そして実際に規約内容の変更をする際には、必ず改訂の履歴を自社で保持しておくことも大切です。例えばユーザーに利用規約違反があったときに、『その時点で利用規約がどの版であったか』を証明する必要があるためです。
- 利用規約の変更を利用者の合意なしにできる条件
- 民法第548条「定型約款の変更」にて定められています。以下リンクよりご参照ください。
参考:e-Gov法令検索 民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
利用規約の内容は、事業者とユーザーの利益を担保し、予期せぬトラブルを避けるためにも大変重要です。作り方に迷われた際には弁護士へご相談ください。
利用規約については、サービス提供する際に絶対に必要というものではありませんが、特にインターネット上で不特定多数のユーザーに提供するサービスの場合は、事業者とユーザー双方の利益を担保したり、万が一のトラブル時に解決の材料となったりという面でとても重要です。
利用規約を、法的な効力を持つ正しい内容で作るためには、今日ご説明した様々な事項を含め、入念な準備が必要になるでしょう。
実際に利用規約の作成に着手される際には、ぜひ弁護士などの法律専門家へご相談ください。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすれば良いか」にフォーカスして作成しています。そのため、細かい部分は法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」