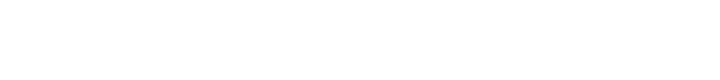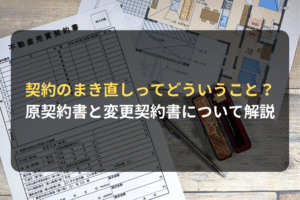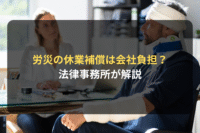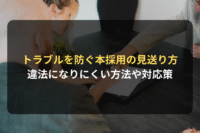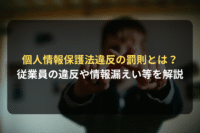- 2024.06.10
個人情報保護法に違反した場合、会社や従業員にどのような罰則になりますか?(従業員の違反や従業員の個人情報漏えい等を解説)
万が一、個人情報保護法に違反する事態が起きてしまった場合、企業はどのような罰則を受けてしまうでしょうか。本記事では、社長さんからの質問にお答えしながら、従業員が違反してしまった場合、企業が従業員の個人情報を保護できなかった場合等について弁護士が説明します。
目次
- 1 従業員が個人情報保護法に違反してしまった場合、その従業員や会社にはどのような罰則がありますか?
- 2 そもそも個人情報ってどのような情報が含まれますか?(個人情報保護法における個人情報の定義)
- 3 逆に、会社側が従業員に関する個人情報を漏らしてしまったらどうなりますか?
- 4 「本人の同意なしに個人情報を第三者に渡しても問題ないケース」にはどのようなものがありますか?
- 5 個人情報保護法の罰則以外に、会社が被るデメリットはありますか?
- 6 個人情報保護のために、従業員へ教育すべきことは何ですか?
- 7 違反や情報漏えいを防止するため、他に会社が行っておくべきことはありますか?
- 8 個人情報保護法の対象となる情報や違反時の罰則については、常に最新の情報を学んでおきましょう。
従業員が個人情報保護法に違反してしまった場合、その従業員や会社にはどのような罰則がありますか?

今回は大事にいたらずに済みましたが、今後の万が一のことを考えて、いろいろあらためて理解しておきたいと思いまして。
それは企業にとってとても大切なことですね。分かりました。
もし個人情報保護法の違反があった場合や、違反したおそれがある場合などは、まず最初のステップとして会社から個人情報保護委員会へ、報告をする必要があります。個人情報保護委員会は、国が運営する機関ですね。
報告の内容としては「どのような事態が起きたのか」をありのまま報告するかたちです。もしですが、この報告をしないでいた場合は『50万円以下の罰金』という罰則を会社が受けてしまう可能性があります。
はい。厳密に言うと、個人情報保護委員会の規則で定められているケースだったら、という感じなのですが、そのあたりは後ほどまとめて解説しましょう。
尚、報告が済んだとして、違反があったこと自体に対してなにかしらの罰則がすぐに適用されるというわけではありません。報告した内容、状況に応じて、まずは個人情報保護委員会から会社に対して、指導や勧告が行われます。例えば、違反のおそれ程度であれば『今後はこういう対策をとっておいてくださいね』という『指導』になり、法律違反レベルの状況であればより具体的に、対応やその後の報告までを求める『勧告』、というかたちになることが多いようです。そしてもし、その勧告にきちんと従わなかった場合は、該当する違反をした従業員は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、そして会社は1億円以下の罰金など、とても重い罰則が科されてしまいます。
また、特に勧告のほうでですが、指導の場合も含めて、起きた事態がとても重大で消費者への影響が大きかったり、悪質な部分があると判断されてしまった場合には、『こういった事案が発生し、こういう指導や勧告をしました』ということを個人情報保護委員会が世間へ公表することもあります。
- 個人情報保護委員会が定める「個人情報保護違反のおそれ」にあたるケース
-
個人情報保護法の第26条(第1項)にて「報告対象となる事態」として定められています。
概要としては以下となりますが、詳しくは個人情報保護委員会の公式ホームページを参照ください。- 高度な暗号化や保護措置をしていない状態での、個人データの漏えいや滅失が発生した、または発生したおそれがある
- クレジットカード情報や決済可能なID/パスワードなど、不正利用された場合に財産的被害が生じる可能性がある個人データの漏えいなどが発生した、または発生したおそれがある
- 個人データの漏えいや滅失が、不正アクセスやランサムウェア、従業員の故意など、不正の目的をもって行われた行為の結果だった
- 1,000人を超える人数ぶんの個人データ漏えいが発生した、または発生したおそれがある
参考:個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a3-5違反について会社が報告を怠っていても、従業員や役員が個人情報保護委員会へ報告することがある
個人情報保護違反の発生やおそれがある場合に、仮に企業が「報告をしなくともよい程度」という判断をした場合でも、従業員や役員が個人情報保護委員会へ別途報告する可能性があります。
個人情報保護委員会では、従業員や役員が状況を報告するための「公益通報」という窓口(インターネット入力フォーム、および郵送窓口)を設置しています。参考:個人情報保護委員会 公益通報の受付について
https://www.ppc.go.jp/application/internalreport/従業員が情報を漏えいさせてしまった場合の「個人情報保護法以外」での対応
企業の従業員が個人データ漏えいなどにつながる行為をしてしまった場合、個人情報保護法上での委員会からの罰則以外に、企業が別途、当該従業員へ罰則を科す場合があります。企業と従業員の間で秘密保持契約書を締結している場合や、懲戒規定にて定められている場合などがこれにあたります。
そもそも個人情報ってどのような情報が含まれますか?(個人情報保護法における個人情報の定義)

まず前提として、法人や団体は『個人』に該当しないため、例えば取引先の企業さんに関する会社情報などは、個人情報には該当しません。
個人のお客さんと取引している場合、その顧客の氏名・住所をはじめとした、取引上で得られた情報はすべて個人情報となります。これまでに購入した商品の情報、自社のどんなサービスを利用中かといった情報のほか、例えばお客さんからアンケートで答えてもらった『いま興味があること』『サービスへの要望』などなど、あらゆる『その人についての個別の情報』が個人情報になると思ってよいでしょう。
ちなみに個人情報には、例えばサポート窓口へ問い合わせした際の通話音声や自社へ訪れた際の防犯カメラの映像といった、本人を識別できる音声や画像・映像も含まれます。
- 亡くなった方に関する情報は個人情報保護の対象?
-
個人情報保護法の対象は、生存する個人に関する情報に限られています。ただし、その情報が、生存する遺族などにも関係する情報である場合にはその遺族などに関する「個人情報」と判断されます。詳しくは、個人情報保護委員会の公式ホームページを参照ください。
参考:個人情報保護委員会 法令・ガイドライン等
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
逆に、会社側が従業員に関する個人情報を漏らしてしまったらどうなりますか?

例えばですが、従業員の家族と名乗る人から電話があって、『今日は出社してますか?』『朝具合が悪そうだったけど、元気にやってますか?』などと聞かれたとしても、本人の同意無しに答えてしまうことは、原則NGです。
よい着眼点ですね。個人情報保護法においては、会社内での個人情報のやりとりは第三者提供には該当しないため、必ずしも本人の同意は必要ないと定められています。ただし、業務上必要な範囲を超えて個人情報が利用されてしまった場合には、本人の同意が必要です。
また、個人情報保護法における違反に該当するかどうかという話とは別に、もし業務上必然性がない範囲で従業員の情報を社内へ周知してしまった場合には、企業の不法行為に該当してしまう可能性があります。具体的には民法の『不法行為責任』や刑法の『名誉毀損』を負う可能性があるでしょう。
とはいえ、社内のことであれば程度によると思いますが、例えば従業員が自分の給料について同僚に知られたくなかったのに、業務上の理由もなく明かされてしまった……ということがあれば、従業員に精神的損害をあたえたということになりますので、その従業員から訴えられてしまう可能性もあるでしょう。
「本人の同意なしに個人情報を第三者に渡しても問題ないケース」にはどのようなものがありますか?

仰るとおり、そのようなケースはありますね。例えば個人の名誉を棄損する書き込みであったり、犯罪予告を書き込んだ事例などですね。
個人情報保護法においては、『法令に基づき、適した相手へ情報を開示する場合』は本人の同意なしに、外部へ情報を公開してよいことになっています。
仰ったようなインターネットサービスプロバイダの対応もそれにあたりますが、それ以外の企業にとっても、人の生命や健康、財産の保護などの重大な目的がある状況なのに本人の同意を得るのは困難、という場合には、同意を得ないまま外部へ情報を開示することが認められています。例えば、従業員が大けがをして意識を失い、治療のために血液型を医師に教える必要があるが、本人に許可を得ていなかったな……というようなことがあっても、その場合は生命や健康が優先されますので、治療に必要な個人情報を開示できます。
また、国の機関や地方公共団体などが、あくまで法令で定められたまっとうな目的で会社に問い合わせしてきた場合なども、企業は従業員の個人情報を開示できます。
例えば、警察や検察などの捜査機関から『従業員〇〇さんのいついつの行動を知りたい』『顧客の〇〇さんがなにを買ったのか知りたい』といった問い合わせがきた場合、その問い合わせが刑事訴訟法に適切に基づくものであれば、その範囲に限っては、『法令に基づいている』ということになるので、開示しても問題ありません。
ただしこのあたりはあくまで一例であり、話が複雑になってきますので、もしそういった異常事態があった場合には、会社の法務担当者や弁護士と相談しながら、慎重に対応を検討してください。
- 「法令に基づき、適した相手へ情報を開示する場合」については、個人情報保護法の第27条(第1項)にて明記されています。
-
詳しくは、個人情報保護委員会の公式ホームページを参照ください。
参考:個人情報保護委員会 法令・法第27条(第1項)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a3-6-1
個人情報保護法の罰則以外に、会社が被るデメリットはありますか?
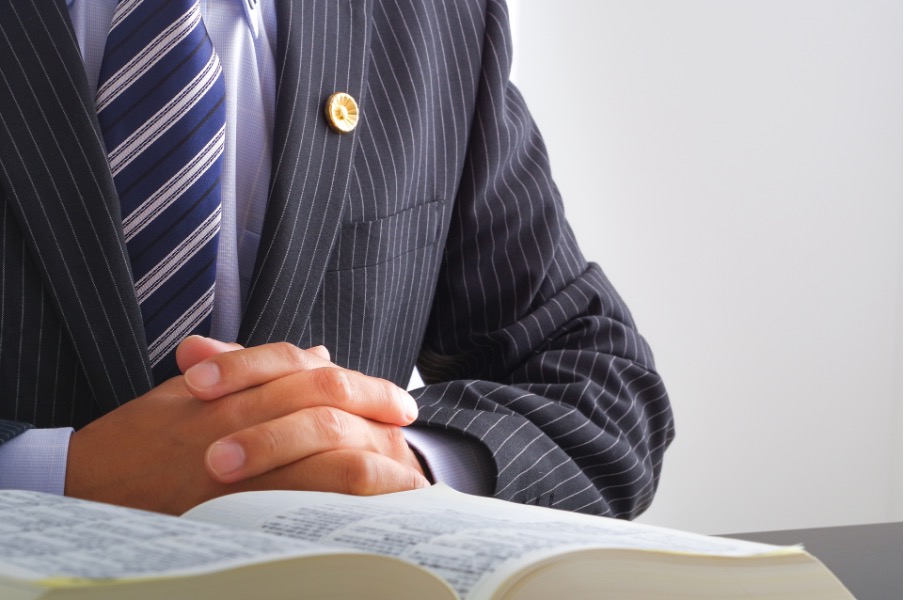
個人情報保護のために、従業員へ教育すべきことは何ですか?

もしPマーク(プライバシーマーク)を取得している企業であれば、もともと最低でも年に1回の従業員教育が義務付けられていますが、御社はPマークを取得されていますか?
仰るとおりです。Pマークは外部に対して、『うちの会社は個人情報についてしっかりと適切な保護措置を講じていますよ』という大きなアピールになりますし、取得のために必然的に保護の体制を整備できますから、取得を検討してもよいかもしれませんね。
Pマークのことは置いておいても、個人情報保護について従業員へ徹底した教育を行うためには、少なくとも年に1回など定期的な講義やテキスト配布を行うことが理想です。一か所の研修室などに集合せずとも、従業員が個々のデスクのパソコンで勉強できるeラーニングという方法もありますので、そういった手段で、どういったことが情報保護違反にあたるのか、万が一にも違反した際にはどのような事態になってしまうのか、について深く理解してもらうことが大切です。
また、会社が個人情報保護について理解したり、正しい教育を行うためには、『個人情報保護法は数年ごとに改正される』ということも忘れてはいけない点です。法律が施行されたのは2003年とだいぶ昔になりますが、時代の変化や情報伝達手段の変化にあわせて改正が重ねられていますので、古いガイドブックをもとに教育しているという状況では大変危険です。
先ほど挙げたeラーニングであれば、改正された内容も常に反映されていると思いますので、そういった面でも面倒が少なくおすすめですよ。
違反や情報漏えいを防止するため、他に会社が行っておくべきことはありますか?

会社のルールづくりや業務の仕組みづくりで未然に防止できる部分もあります。今日のご相談のきっかけは、社員さんがUSBメモリを持ち帰ったというお話でしたが、まさにUSBメモリやパソコン、業務用スマートフォン、そのほかeメールやSNSなどでも、情報を取り扱う手段や媒体について運用のルールをしっかり決めたうえで、全従業員が徹底するということが大切です。
また、万が一情報保護法の違反のおそれが出た場合に、その事実自体を早急に察知し、適した対応をしっかりととるための管理チームを社内で整備しておくことも有効です。
個人情報保護法の対象となる情報や違反時の罰則については、常に最新の情報を学んでおきましょう。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすれば良いか」にフォーカスして作成しています。そのため、細かい部分は法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」