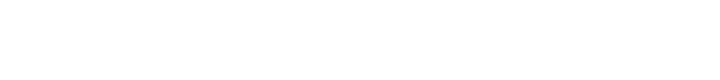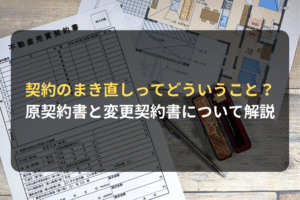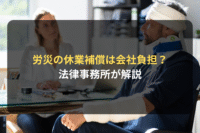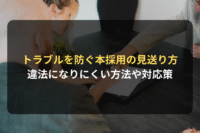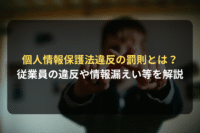- 2024.06.10
契約の「まき直し」って具体的にどのようなことですか?(「原契約書」と「変更契約書」などについてイチから解説)
契約関連の話で「まき直し」という言葉を聞くことがありますが、このまき直しの意味について正しく理解されてらっしゃいますか?社長さんからの具体的な質問にお答えしながら、弁護士が分かりやすく解説します。契約書のまき直しが迫っている経営者、社長様はぜひご参考ください。
目次
そもそも契約の「まき直し」って何を表すのですか?(基礎知識と発生する事例や項目)

簡単に言うとまず普通の契約書というものがあって、その契約書に例えば契約金額であったり、単価であったり、物件の引渡方法や引渡期日、契約期間などなど、こういう契約をしますという細かな約束ごとが書かれていますよね。『まき直し』というのは、そういった契約書に書かれている内容のうちのどこかの部分を、あとから変更することを指します。もちろん、契約者のうちの片方が勝手に変えるということではなく、両方が変更に合意したうえで変えるということになりますね。
ちなみに、契約書のなかに単に誤字脱字が見つかって訂正したい場合や、訂正箇所がごくわずかな場合には訂正印と捨印を押したうえで正しい内容を追記するということも多いですが、契約内容自体の何らかの見直しの場合には、まき直しという方法がとられます。
そうですね。不動産の契約書はもともと登記、手付金、住宅ローン関連、売買価格や土地の境界など様々な、とても細かい内容を記載するものですから、ときにはどうしても双方の思い違いや誤解で、内容の一部を見直す必要が出てくることは多いと思います。また、例えば建売住宅の販売などで建物の仕様や納期などの細かな面が契約後、実際の建築が進んでから変わってくることも一般的ですから、そういった場合の対応として契約のまき直しは正当な手段です。よくないことだと心配する必要はありません。
それに、まき直しで作成した覚書も通常の契約書と同じように法的な効力を持っています。つまり、決して“なあなあ”の内輪での解決方法というわけではなくて、きちんとした契約内容に関する手続きということですね。例外として、もともとの契約時に『覚書は法的効力を持たない』という旨が記されたうえで契約されていたのであれば話は別ですが、そういったケースは一般的にあまり無いでしょう。
- 「まきなおし」を漢字で書くときは「巻き直し」?「蒔き直し」?
-
まきなおしという表現は、もともとは農業で種をもう一度まく、最初からやりなおすということで「蒔き直し」が語源であるという説が一般的に有力です。
しかし現代のビジネス上、契約締結関連の話において「まきなおし」という文言を文書やメールなどで書くときには、慣例的に「巻き直し」あるいは漢字をひらいて分かりやすく「まき直し」としている場合が多いでしょう。まき直しが発生する契約書上の項目の例
最初の契約でまき直しに関する制限をしていない場合は、契約内容にある項目のすべてがまき直しの可能性がある項目といえますが、主な例としては以下のような項目が挙げられます。- 請負の内容 / 期日または期限
- 目的物の引渡方法
- 契約金額
- 取扱数量 / 単価
- 契約金額の支払方法 / 支払期日
- 契約期間
- 契約に付される停止条件 / 解除条件
- 債務不履行があった場合の損害賠償方法
まき直しにはどのような書類が関係するのですか?(「原契約書」と「変更契約書」、および「新旧対照表」について)

原契約書の契約内容をまるまるなかったことにする場合は、まずその原契約書に書かれている内容の効力をなくしてしまう必要があります。具体的には、新しく作る変更契約書の前文に『●●日付で、▲▲に関する契約書は失効する』という旨を記載するといった方法になります。
原契約書を残したまま覚書としての変更契約書を作成する場合には、変更契約書のほうに変更前の契約書の締結日や具体的な変更箇所、変更がいつから有効になるのかなどを記載し、契約者の双方が合意のうえで署名捺印して、1通ずつ保管するという流れになります。
この場合はさらに、『新旧対照表』という書類を用意して、どこが変更箇所で、どういった変更が生じたかということを誰がみても分かりやすいような一覧にしておくことも多いですね。
- 変更契約書には決まった書式はない
- 一般的な変更契約書の記述の仕方として、以下に一例をご紹介します。
甲と乙は、以下の定めを変更する目的で、覚書を締結する。
令和*年*月*日に甲乙間で締結された「不動産売買契約書」の「不動産売買契約条項」において、「第*条〇〇〇に関する定め」を以下の通り変更する。変更前:【第*条〇〇〇】□□□□□
変更後:【第*条〇〇〇】△△△△△尚、原契約書の内容を失効させる場合には、変更契約書に以下のような前文を記します。
本契約の成立によって、令和*年*月*日に甲乙間で締結された「不動産売買契約書」を失効するものとする。 新旧対照表の作成例
新旧対照表は見やすい表形式にして、ざっと見で変更箇所や変更内容を確認できるようにしておきます。特に、具体的に変更が生じる文言・数値などの部分は、下線付きで目立つように表記しておくとよいでしょう。改正前
改正後
第*条〇〇〇
第*条〇〇〇
所有権移転・引渡し・登記手続きの日
:令和6年4月1日
所有権移転・引渡し・登記手続きの日
:令和6年4月20日
課税対象の変更については収入印紙が必要
原契約書の内容に課税対象となる事項があった場合(課税文書に該当した場合)は収入印紙の貼付をおこなっているはずですが、その課税対象となる事項にまき直しが発生した場合は、変更契約書も同様に課税文書となり、収入印紙の貼付が必要となります。
変更内容が課税対象となるかどうかは、印紙税法における「重要な事項」にあたるかどうかで変わります。例えば不動産売買契約書や不動産交換契約書は印紙税法において「第1号の1文書」にあたり、そこに書かれた契約金額や支払い方法、契約期間などは「重要な事項」にあたります。
詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。参考:国税庁 法令解釈通達 別表第2 重要な事項の一覧表
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm
まき直しは決まったタイミングでおこなわれるのですか?(まき直しが起こるタイミングの例)

契約のまき直しがおこなわれるのは、あくまで、契約内容になにかしらの行き違いや誤解があって、『そのまま進めてしまっては不利益が生じる』などの明確な理由で双方が合意した場合になりますね。例えば『単に気が変わったから』『読み落としていたから』といった理由では、一般的に双方の合意にいたらないと思いますので、まき直しもおこなわれないでしょう。
まき直しがおこなわれるタイミングについては決まったタイミングがあるわけではありませんので、例えば変更はまったく想定していないような契約書を作成し、締結日を迎えたあとでも、双方合意という条件がそろえば、いつでも変更契約書を交わすことができます。
また、最初から『実際の作業を始めてみないと細かな作業量や金額が出せない』という状況もあり、その場合には仮の内容でいったん契約をしておき、契約書上で『報酬額、工数や業務の範囲は別途協議のうえで定める』などと記載することもよくあります。この場合も、あとから具体的な契約条項を定めるときに、契約のまき直しがおこなわれます。
- 契約書の「締結日」の意味
- 締結日とは、契約書上で当事者全員が署名あるいは押印を完了した日のことを指します。例えば契約者二者のうち一者が契約書を作成し、押印し郵送した場合には、受け取った相手方が契約書に署名・押印をした日が締結日となります。従って「記入日」や「契約書作成日」とは異なることもあります。
また、契約書に「本契約は、**年*月*日から適用する」といった条項を入れ、実際の効力が発生するタイミングを締結日より未来にする場合もあります。
契約のまき直しをおこなう際の注意点は何ですか?

というのも、変更契約書が例えばパソコンで作成し印刷しただけのものや、代理人が署名したものだった場合には、裁判などの厳格な場面や手続きで効力を発揮しない文書となってしまうからです。万が一の後々のトラブルが発生した場合でも正当な対応をおこなえるよう、当事者がしっかり目を通したうえで署名・捺印することが大切です。
契約のまき直しについては、変更する内容をしっかり話し合い双方が合意することが大切です。解釈の違いでトラブルになる場合は弁護士へご相談ください。
これまでお話したように、契約のまき直しは契約書の内容について、なんらかの理由で見直しが必要となった場合におこなわれる手続きであり、正しく変更契約書を作成すればその変更内容が法的にも有効となります。
まき直しをおこなう際に作成する書類については決まった書式があるわけではありませんが、押さえなければならないポイントがいくつかあり、また変更する内容によってはあらためて収入印紙が必要となる場合もありますので、慎重に進めることが大切です。万が一にも、まき直しにあたってトラブルが起こりそうな場合などには、ぜひ弁護士等の法律専門家に、状況をご相談ください。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすれば良いか」にフォーカスして作成しています。そのため、細かい部分は法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」