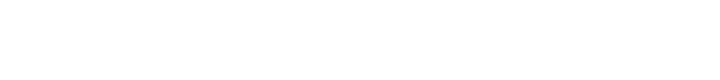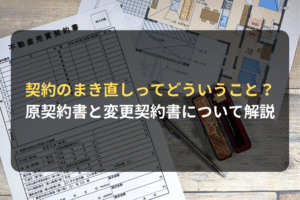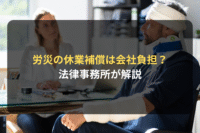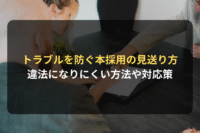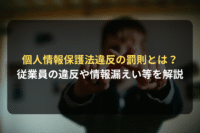- 2024.06.10
委任契約と請負契約のどちらを選べば良いですか?(委任契約と請負契約の特徴や違いをわかりやすく解説)
目次
委任契約や請負契約ってどんな契約ですか?
(委任契約と請負契約の特徴、準委任契約やその他に関連する契約についても明確に解説)
委任契約と請負契約のどちらを選べば良いですか?という社長のご質問に対し、弁護士が違いや特徴を会話形式で分かりやすくお答えします。
委任契約について
要するに、T社長の会社が、他の会社に対し、本来は自社で行うであろう法律行為を『わが社の代わりにやってくれない?』とお願いして、相手が『okです』と言うことですね。
でも、厳密に言うと、法的にそれは委任ではなく、「準委任」(民法656条)と言います。
委任とは本来自分がすべき『法律行為』を誰かにお願いすることをいい、他方、準委任とは本来自分がすべき『事実行為』を誰かにお願いすることをいいます。要するに、誰かにお願いすると言う点においては同じですが、お願いする内容に違いがあるんですよ。
『販売』と『問合せ対応』のどちらも、相手にお願いするという点においては、同じですよね。
ですが、『販売』というのは民法で言う所の「売買」(民法555条)にあたるので、もし、『販売』したとすれば、商品を買った人はT社長の会社に対し代金を支払う義務が生じますし、反対にT社長の会社は買った人に対し商品を引渡す義務が生じます。つまり、『販売』とは、それにより法律上の効力が生じる行為(=『法律行為』)なんです。
他方、代理店会社がお客さんに対し『問合せ対応』を行ったとしても、そのことをもって直ちに、お客さんやT社長の会社において法的な義務を負うことはないでしょう? つまり、『問合せ対応』とは、それにより法律上の効力が生じない行為(=『事実行為』)なんです。
要約すると、『販売』を依頼すれば、それは『法律行為』をお願いしたことになるので、「委任」と言えますし、他方で、『問合せ対応』を依頼すれば、それは『事実行為』をお願いしたことになるので、「準委任」にあたるということですね。
ところで、委任と準委任って、その法的な取扱いに違いがあるんでしょうか?
ですから一般的には、契約を締結する際に、「委任」「準委任」の違いについて、それほどは悩まなくていいですよ。
むしろ、大切なのは、その内容(=『誰に対し、何を、どれくらいの料金を支払って、その他どういう条件のもとで、お願いするのか』)が、自分のやりたいビジネスに適っているかということです。
請負契約について
簡単に言うと、T社長の会社が相手の会社に対し『報酬を払うから、こういう仕事を完成させてくれない?』とお願いして、相手の会社が『okです』と言うことですね。
代表的な所で言うと、『建設工事(請負)契約』とか、『製造物供給契約』(=他の会社に商品等の製造・納入をお願いするという契約)とかが挙げられますね。
- 労働者派遣契約とは?
-
労働者派遣契約(派遣契約)は、派遣社員を雇用する派遣元会社(=派遣元)と、これらの派遣社員に一定期間自社で働いてもらいたいと考える派遣先会社(=派遣先)との間で結ばれる契約です。この契約によって、派遣先は、派遣元から派遣社員の提供を受けることができ、派遣社員に対して業務を指示命令し動いてもらうことができます。
こうした労働者派遣は、特定のスキルが必要なプロジェクトを進めたり、近年の人材不足に対応するための手段として有用ではありますが、労働者派遣法によって、一定の規制(例えば、派遣可能な業種、派遣期間の上限、派遣社員の労働条件など)が設けられています。
なお、委任契約や請負契約の場合、原則としては労働者派遣契約とは異なる契約類型として扱われますが、その内容によっては、労働者派遣法などに違反してしまうケースもあります。
同法に違反するか否かには複雑な判断が伴いますので、念のため専門の弁護士に相談するなど、適切なリスクヘッジを行いながら、ビジネスを進めていくことを、おすすめします。
委任契約と請負契約ってどこが違いますか?
(委任契約と請負契約の違いと注意点)
結局の所、『委任と請負の違い』とは、何でしょうか?
委任だからといって、無形的なもの(サービスなど)のみが対象になるわけではなく、有形(物の製造など)を対象とすることもできます。同様に、請負も、有形的なもの、無形的なもの、そのどちらも対象とすることができるんですよ。ですから、実の所、法律上は、委任か請負のどちらを締結してもよいケースは結構あるんですよ。
例えば、T社長が病院で診療を受ける場合、病院側とT社長との間で診療契約を結ぶことになります。こうした診療契約については、実務上は、『(準)委任』として扱われますが、『請負』として扱うことが絶対ダメってことはないんですよ。
まずは、請負について見ていきましょう。
民法632条には、「仕事を完成することを約し」と書いてあります。このことから、請負においては、仕事の『結果』について責任を負うという解釈が導かれます。簡単に言ってしまうと、請負の場合、「結果良ければすべて善し」ってことですね。
次に、委任についてですね。
請負(=民法632条)とは違い、委任について定義した民法643条には、「仕事を完成すること」をその要件として書いておらず、また、民法644条は、受任者に対して、適切な注意を払いながら委託された事務(=委任事務)を遂行するよう義務づけています。このことから、委任においては、原則として、仕事の『結果』ではなく、その『プロセス』について責任を負うという解釈が導かれます。簡単に言ってしまうと、委任の場合、「プロセス良ければすべて善し」ってことですね。
でも、人間っていうのは本当に複雑な構造により生命・健康を維持しています。病院側の治療が適切であっても、患者さんの心身や免疫に弱い所があったり等すると、結果として治療が成功しない場合もあります。このように『結果』(=治療の成功)を保証しにくい事情のもとでは、「あなたの症状を、絶対に回復・改善させます」と約束するって、難しいでしょう?
さらに、もし、病院側に対して、『結果』についてまで責任を負うよう強いるならば、医師は商売あがったりなわけですから、現場から離れる医師や廃業する病院が増え、かえって病院で診療を受けることが難しくなってしまうことも予想されます。
ですから、実務上、診療契約については『(準)委任』として扱われるんですよ。
ですから、とりあえず自社のリスクを相手に転嫁しようとするのではなく、『自社のビジネスの内容を踏まえた上で、相手にどこまで責任を負ってもらう必要があるのか』とか『それが相手にとって納得できる内容なのか』といった点について、しっかりと意識することが大切なんですよ。
これまでお話ししたように、請負は『結果』について責任を負う契約類型です。ですから、契約不適合責任(民法559条、562条以下、636条~637条など)の適用があります。
他方で、委任については請負と違い、原則としては、契約不適合責任の適用がないと考えられています。
民法のルールの下では、「債務不履行(=約束を破ること)はないものの、不公平な結果になってしまう」といったケースも起こり得ます。契約不適合責任っていのうは、こういった不公平な『結果』を解消する手段でもあるんです。
裏から言うと、契約不適合責任が適用される取引っていうのは、「その取引が、不公平な『結果』を善しとしない(要するに、『結果』に対し責任を負っている)類型の契約である場合」と説明することもできます。
ですが、委任は(原則としては、)『結果』に対し責任を負わない契約類型です。ですから、契約不適合責任の適用がないと考えることができるんですよ。
ただし、民法改正に伴い、『成果物(=ある種の結果)を提供する委任』(つまり、成果型or成果提供型)が台頭し、実務でも、この成果型が使われるケースも少なくないです。
そして、この成果型は、より請負に近い内容となることから、『請負に準じて契約不適合責任が適用されうる』との見方も根強くあります。
ですから、もし、『成果型』の委任を締結される際には、契約不適合責任の適用についても検討しておけると、ベストですね。
簡単に言ってしまうと、成果型とは、一定の成果(=ある種の結果)に対し報酬を支払う形式のもとで締結される委任契約ってことです。
請負においては「結果良ければすべて善し」であり、プロセスは問われないので、下請を活用するか否かは、原則として、請負人の自由な判断に委ねられます。
他方、委任は、特定の相手を信頼して依頼するわけですから、依頼をした側(委任者)の同意がないと、依頼を受けた側(受任者)において再委託を活用できないことになるんです。例えば、T社長の会社が、法律事務所に契約書のチェックをお願いしたにもかかわらず、法律事務所がことわりなく、外部の(=法律事務所に所属しない)まったく法的知識のない人にそのチェックをさせてしまったら、困るでしょう?
- 印紙代の違い(委任と請負)
-
印紙税は、契約書や領収書などの文書に対して課税されるもので、その課税の対象や必要な印紙の金額は、該当する文書の種類や金額によって違います。委任の場合、請負と違い、課税文書として印紙税法に明文化されておらず、原則としては印紙は不要ですが、委任であっても、その契約内容によっては課税文書(1号文書、7号文書)に該当するケースもあり、その場合、印紙が必要となります。他方、請負の場合、課税文書(2号文書、7号文書など)として印紙税法に明文化されているので、報酬額に応じて適切な印紙が必要となります。もし、印紙代について迷ったときは、専門の弁護士に相談するとよいでしょう。
委任契約と請負契約は、それぞれどんな場面で結ぶとよいですか?
(委任契約と請負契約のメリットとデメリットを、ケースを交え解説)
ですから、例えば、法律やマーケティングのコンサルティングなど、一義的に『正解はこれです』とは言いづらく、様々な事情を総合的に考えながらする専門知識が必要な仕事については、一般的には委任の方が馴染みやすいと言えます。
このことから、依頼する側(委任者、注文者)からすると、両契約ともに、社外の人の力を借りるので人件費の節約や労災コストの低減ができたり、また、ベースとしては相手に仕事を委ねることになるので日々の管理コストを削減できるといった点において、メリットがあります。
反対に、両契約ともに、社外との連携を前提とするので双方の認識の食い違いが生じやすく、自社のみでビジネスを進めるよりもトラブルが起きる可能性が高かったり、また、社外の人にやらせるので自社にノウハウが溜まりにくいという点において、デメリットがありますね。
委任契約や請負契約を締結するときに、注意することってありますか?
(委任契約書や請負契約書を作成する際のポイント)
共通のポイント
改正後の民法では、委任においても成果型が認められることになりました。そして、この「成果」には依頼者に対し何らかの納品を行う場合も含まれます。例えば、報告書・資料を作成して、それを依頼者に納品するなどがありますね。また、商品やシステムの制作といった依頼の場合、請負をベースにして契約を締結することも多いですが、『委任』をベースにして締結するのに適したケースもあります。この場合、依頼された商品・システムの納品が「成果」ってことになりますね。
このように、請負・委任のどちらのパターンでも、『納品』って想定されるんです。
でも、委任って『結果』に対し責任を負わないという契約類型なんでしょ? それなのに、『成果』(=納品されるものの内容など)について一定の水準を求めるってことは、ある意味『結果』に対し責任を求めていることになるような気もします。それって、何か矛盾しているような…。
というのも、成果型の委任の場合、ビジネス上『誰かから依頼を受けて、一定の成果を遂げて、それに対し報酬をもらう』という流れになります。これって、請負のビジネスの流れと比べて、それほどは変わりませんよね。こういったことからも、民法では成果型の委任に対し、請負に関する規定の一部を準用するよう定めています(民648条の2条参照)。
要するに、成果型の委任の場合、実質的には請負に近い契約類型となっているので、請負と同じく、『結果』に対しても一定の責任を負ってもらう旨を双方で合意しても、それ自体が法的にダメってわけではないんですよ。
ですから、請負と委任のどちらを選択しても、「成果」の内容についてきちんと合意しておくことが、大切なポイントの1つですね。
例えば、3ヵ月後に新たに店をオープンするので、そこで売るための商品の製造を依頼したのに、半年後に納品されても困るでしょう? このように実際のビジネスにおいては、委任や請負は会社で行うビジネスの一部として活用されることが多く、納期が遅れるとビジネス全体にずれ込みが生じ、会社にとって損失が出てしまうリスクがあるんです。
ですが、近年では知的財産権が強く意識されるようになり、所有権以外の権利(特許権、著作権、ノウハウに関する権利など)の帰属についても別途考える必要性が高まっています。
例えば、⑴ 納品されるものに対し、依頼を受けた側(受任者、請負人)の独自の技術が使われた場合、依頼をした側(委任者、注文者)が『どういった範囲で、どんな条件のもとで、その技術に関する権利を取得または利用できるのか』について考える必要がありますし、また、⑵ 納品するものがレポートや資料、動画といった場合においては、『これらの著作権も依頼をした側に移るのか』について考える必要があるということです。
もし、こうした考慮をせずに、やみくもに自社の利益ばかりを追求してしまうと、独占禁止法違反となってしまうリスクがあり、この場合、行政からお咎めを受けてしまうことにもなるので、注意しましょう。
もちろん、これらの損害賠償等についてのルールが書いてないときでも、その場合、法律に従って解決していくことになるので、合理的範囲において損害を回復することは可能です。
しかしながら、お金が絡むということは、それだけ揉めやすいということに繋がりますから、できる限り双方の認識にズレが生じないよう、損害賠償・違約金についてもルールを書いておけると望ましいですね。
委任におけるポイント
ところで、委任の場合に特に気をつけた方がいいポイントとかってあるのでしょうか?
というのも、委任契約が締結されると、依頼を受けた側(受任者)は依頼をした側(委任者)に対し、委託されたこと(=委任事務)を遂行すべき義務を負いますが、『委任事務とは、どういった内容のものを指すか』については、民法には特に定めがないです。つまり、双方の合意によって、「委任事務」の内容・範囲が決まるということですね。
裏から言うと、これに漏れがあると、後になって『○○についても、遂行してください』と相手に請求しても、その相手から『○○については、わが社において遂行すべき「委任事務」に含まれないので、追加料金が必要ですよ』と言われてしまい、予想外の負担を強いられるリスクがあります。
特に、委任の場合、サービス利用契約など、目に見えないものを提供・利用するときにもよく活用されます。ですから、『依頼をする側が望むこと』と『依頼される側が提供しようと考えていること』との間にズレが生じることが、実際にも多くあり、トラブルに発展してしまうケースも多いです。
ですから、「委任事務」とは何を指すのかについて、きちんと書いておきましょう。
請負におけるポイント
請負とは、「結果良ければすべて善し」という契約類型です。ですから、その過程(プロセス)については、原則として、依頼される側(請負人)の自由に任せられます。要するに、請負人は、『どういった行動をすべき、またはすべきでない』とか『別の会社や人を使って、仕事を進める』などの(仕事の)プロセスについて、特に縛りがないということです。
ですから、もし、T社長の会社が依頼する側(注文者)の立場にあり、かつ、結果だけでなく『プロセス』に対しても要望があるときは、そのことについて契約書にしっかりと書いておきましょう。
というのも、ビルやショッピングモールは、そこを活用したビジネス(例えば、お店を出す、テナントとして賃貸する等)を念頭に置いて建築されることになりますので、納期にズレが生じると、当該ビジネスに関連する他の取引に対しても影響が生じるリスクがあるので、こういったリスクをできる限り早い段階で感知できるようにし、早急かつ適切に対応する必要があるからです。
そこで、請負人に対し、各工程ごとや注文者の要求があったときに、納期との関係での進捗状況や、工事を進める中で新たに浮上した懸念点などについて、注文者に報告するように書いておいたり、注文者の要求に応じミーティングを開くよう書くなどして、お互いに現状を確認し合える形にしておくことがあります。
- 下請代金支払遅延等防止法(下請法)とは?
-
「下請代金支払遅延等防止法」(=下請法)とは、強い立場にある「親事業者」(同法2条7項)から弱い立場にある「下請事業者」(同法2条8項)を保護することで、ビジネスの公平を図ることを目的とした法律です。この法律では、例えば、下請事業者に対する代金の支払期日については、親事業者が委託した物の給付や役務の提供を受けた日から60日を超えることができず、また、過度に低い価格での契約強要や、不当な責任の転嫁などを禁止しています(同法2条の2、4条参照)。その他に、事後的なトラブルを防ぐ趣旨のもと、親事業者は、下請事業者に対し、契約条件(給付内容、代金額、支払期日およびその方法など)について定めた書面を交付することが義務化されています(同法3条1項)。
請負や委任を行うときは、その取引について下請法の適用があるのかをチェックし、もし適用がある場合には、同法の定める義務をきちんと遵守しながらビジネスを進めましょう。
外部リーガルに依頼するメリット
(外部弁護士に作成やチェックを依頼するメリット)
確かに、T社長のご認識のように、それぞれの契約(委任、請負)の特徴をよく理解しておくと、委任や請負を使ってビジネスを進めていくハードルは低減されるかと思います。
ですが、委任や請負を選択してビジネスを進めるときって、依頼する側(委任者、注文者)と依頼される側(受任者、請負人)とで大きな利害対立が生じることが多いので、T社長の会社では『委任を選択したい』と思っても、相手から『請負でお願いします』と言われてしまうこともあります。
委任でも請負でも、その内容については双方の合意によって、付け加えたり、減らしたりできるのが、法の原則です(民法521条1項参照)。ですから、「あなたの会社の意向を尊重して、請負契約でいいけれど、今回のビジネスはこういった内容だから、この点についてはこうして欲しい」といったように、交渉していくことができますし、また、ビジネス実務においても、こうした交渉を適切に行っていくことがすごく大事なんです。
しかしながら、この交渉は、委任と請負の有利・不利を形式的に覚えるだけでは適切かつ十分に行うことは難しく、予定するビジネスの全体像およびリスクの所在、その取引の性質や重要性、相場感など、多くの要素のバランスを見ながら行っていく必要があります。そして、これには広い専門知識や経験が必要になります。
まとめ
しかしながら、請負と委任のどちらも『外部』に依頼する形式という点では同じであり、これに伴って「どういった仕事をいつまでにどんな方法すべきか、その報酬はどれくらいか、トラブルがあったときにはどう対応すればよいか」など、ビジネス上双方にとって大切な点について、認識のズレが生じやすく、揉めるきっかけとなってしまうことがとても多いんです。
ですから、委任であっても請負であっても、『仕事の内容、報酬の支払い条件、仕事の期間、どのような場合に契約が終了するか、トラブルがあったときはどう対応すべきか』などについて、できる限り詳細にはっきりと契約書に書いておくことが、とても大切なポイントです。そうすることで、万一、トラブルが起こったとしても、スムーズに解決へと導くことができるんですよ。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」