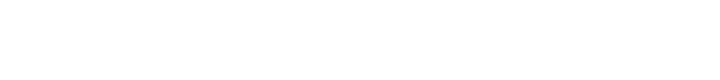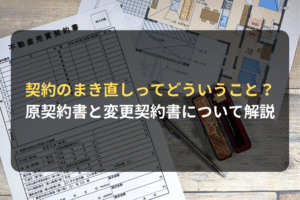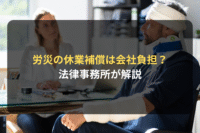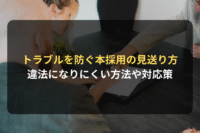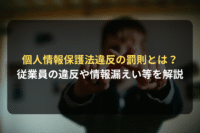- 2024.06.10
秘密保持契約を締結する意味って何ですか?(秘密保持契約(NDA)を締結するメリットや、作成のポイントなどを解説)
秘密保持契約(NDA)を締結する意味って何ですか?という社長のご質問に対し、弁護士がお答えします。秘密保持契約(NDA)の内容や、締結するメリット、締結のタイミング、作成のポイントなどを、会話形式でわかりやすく解説しています。
目次
- 1 秘密保持契約って何ですか? (秘密保持契約(NDA)の内容と目的)
- 2 秘密保持契約を締結する意味とは何ですか? (秘密保持契約を締結するメリット、情報漏えいに対するリスクヘッジ)
- 3 秘密保持契約は、どのタイミングで締結すればいいですか? (秘密保持契約(NDA)の締結のケースやタイミングの紹介)
- 4 秘密保持契約には、どんなことを書きますか? (秘密保持契約における主な条項や事項、およびその締結のポイントの解説)
- 5 秘密保持契約に収入印紙は必要ですか? (秘密保持契約における収入印紙の必要性)
- 6 秘密保持契約は、PDFやインターネットなどでも締結できますか? (電子契約での締結の可能性)
- 7 弁護士によるチェックは必要ですか? (外部弁護士にチェックを依頼するメリット)
- 8 まとめ
秘密保持契約って何ですか?
(秘密保持契約(NDA)の内容と目的)
T社長
先生、秘密保持契約(NDA、nda)って何ですか?
なるほど、今日は『NDA』の相談ですね。
小野弁護士
例えば、T社長の会社が、他の会社と取引を検討する際、お互いに会社の情報を見せ合う場面をイメージしてみましょう。この場合、相手の会社に見せる情報には、開発予定の製品情報や、特別な製造方法など、外に漏れると会社にとって不利益となる情報が含まれることもあるでしょう?
秘密保持契約、略して『NDA』(=Non-Disclosure Agreement)っていうのは、相手の会社において、自社の大切な情報が、予想外の使われ方をしたり又は漏えいしてまったりといったリスクを抑えるために結ぶ契約のことです。
NDAを締結しておくと、安心して他の会社と力を合わせて、色々なビジネスに挑戦することができ、また、これに伴って、会社の利益を増やしていくことができるんですよ。
秘密保持契約、略して『NDA』(=Non-Disclosure Agreement)っていうのは、相手の会社において、自社の大切な情報が、予想外の使われ方をしたり又は漏えいしてまったりといったリスクを抑えるために結ぶ契約のことです。
NDAを締結しておくと、安心して他の会社と力を合わせて、色々なビジネスに挑戦することができ、また、これに伴って、会社の利益を増やしていくことができるんですよ。
小野弁護士
T社長
なるほど、それは嬉しいですね。ところで、NDAって、どんな場面で締結すればいいんですか?
代表例として、T社長の会社が他の会社を買収する場合であったり、他の会社と技術を持ち寄って商品開発を行う場合などが挙げられますね。
ただ、実際のビジネスでは、本当に色々な場面でNDAは締結されます。
というのも、いましがた代表例として挙げた『買収』や『共同開発』といった複雑な取引だけでなく、自社の商品・サービスを他の会社に売るなどのありふれた取引であっても、自社にとって大切な情報(商品情報、技術情報、実例、販売価格など)を提供することが多いからです。
ですから、仮に、NDAを締結する代表例(買収など)以外のビジネスシーンであっても、できる限り取引ごとに『自社からどんな大切な情報を開示し、反対に相手の会社から預かる可能性があるのか』という点をチェックして、NDAを締結すべきかを検討しておくことを、おすすめします。
ただ、実際のビジネスでは、本当に色々な場面でNDAは締結されます。
というのも、いましがた代表例として挙げた『買収』や『共同開発』といった複雑な取引だけでなく、自社の商品・サービスを他の会社に売るなどのありふれた取引であっても、自社にとって大切な情報(商品情報、技術情報、実例、販売価格など)を提供することが多いからです。
ですから、仮に、NDAを締結する代表例(買収など)以外のビジネスシーンであっても、できる限り取引ごとに『自社からどんな大切な情報を開示し、反対に相手の会社から預かる可能性があるのか』という点をチェックして、NDAを締結すべきかを検討しておくことを、おすすめします。
小野弁護士
T社長
なるほど、わかりました。ところで、わが社において『大切な情報』って、どんなものを指すんですか?
シンプルに言ってしまうと、『大切な情報』っていうのは、T社長の会社が保有している、他の会社には知られたくない情報全般のことです。
小野弁護士
T社長
わかったような気もするけど…。念のため、もう少し詳しく教えてもらってもいいでしょうか?
もちろんです。わかりやすいよう、具体例を交えながら、説明してみましょう。
例えば、自社の商品について、独自のこだわりや特徴、技術を用いていて、これを取引先に販売する際に、この商品の詳しい情報の一部を取引先に渡したとします。
この場合、T社長としては、取引先に対し、どういったことに注意して、これらの情報を取扱って欲しいですか?
例えば、自社の商品について、独自のこだわりや特徴、技術を用いていて、これを取引先に販売する際に、この商品の詳しい情報の一部を取引先に渡したとします。
この場合、T社長としては、取引先に対し、どういったことに注意して、これらの情報を取扱って欲しいですか?
小野弁護士
T社長
自社の商品・サービスのこだわりや特徴、技術などを、ライバル会社などに知られすぎてしまうと、この情報を上手く使われて、わが社のシェアを奪われてしまうことにもなると思います。だから、他の誰か(=第三者)に勝手に見せないように、取り扱って欲しいですね。
そうですよね。その他にも、取引先自身において、この情報を勝手に使って競合品を作るなど、約束した用途以外に使われることも嫌ですよね。
『大切な情報』とは、このように、会社として、誰かに知られたくない情報であったり、勝手に使われたくない情報と置き換えて理解しておくといいですよ。
『大切な情報』とは、このように、会社として、誰かに知られたくない情報であったり、勝手に使われたくない情報と置き換えて理解しておくといいですよ。
小野弁護士
T社長
よくわかりました。
ところで、『機密保持契約』っていう言葉も耳にすることあるんですが、ここまで説明してもらった『秘密保持契約』とは何か違うんですか?
ところで、『機密保持契約』っていう言葉も耳にすることあるんですが、ここまで説明してもらった『秘密保持契約』とは何か違うんですか?
確かに、一文字違いの契約名なので、気になりますよね。
実は、『秘密保持契約』と『機密保持契約』は、基本的には同じものを指します。どちらも、取引において、お互いの大事な情報を守るための契約です。つまり、両者の違いは言い方だけです。
実は、『秘密保持契約』と『機密保持契約』は、基本的には同じものを指します。どちらも、取引において、お互いの大事な情報を守るための契約です。つまり、両者の違いは言い方だけです。
小野弁護士
T社長
なんだ、同じ契約なのか。
そうです。ですから、どちらの呼び方であっても、大事なのはその内容です。会社の重要な情報が、取引の相手の下で、適切に保護される契約内容となっているかを、きちんとチェックしましょう。
小野弁護士
T社長
はい、わかりました。
秘密保持契約を締結する意味とは何ですか?
(秘密保持契約を締結するメリット、情報漏えいに対するリスクヘッジ)
T社長
NDA(秘密保持契約)を締結すると、どんなメリットがあるんですか?
NDAを締結するメリットとしては、一般的に、次の4つが挙げられます。
① 相手に渡した自社の大切な情報の漏えいリスクを低減できる
② 漏えいがあった場合に、相手にNDAに基づき損害賠償を求めることができる
③ 法律よりも広い範囲で自社の情報を保護できる
④ 相手の信頼を獲得することに繋がる
順を追って、この①~④について、解説していきましょう。
① 相手に渡した自社の大切な情報の漏えいリスクを低減できる
② 漏えいがあった場合に、相手にNDAに基づき損害賠償を求めることができる
③ 法律よりも広い範囲で自社の情報を保護できる
④ 相手の信頼を獲得することに繋がる
順を追って、この①~④について、解説していきましょう。
小野弁護士
相手に渡した自社の大切な情報の漏えいリスクを低減できる
1つ目のメリットは、『漏えいリスクを低減すること』ですね。
とても大切なことの1つとして、NDAの最大の狙いは、お互いに「相手から渡された情報をきちんと管理しよう」という意識を芽生えさせることで、漏えいを『未然に』防ぐことなんですよ。
例えば、漏えいが発生することなく、取引がスムーズに進むと、会社の商品・サービスも普及するし、会社の評判もより良くなっていくでしょう? そうしていくと、取引先が多くなって会社の利益が増えたり、その増えた利益を使って事業をもっと強くしたり、その他にも、別の会社から『わが社と提携して新しいビジネスに挑戦しませんか?』と誘ってもらえる等、会社を大きくしていけるんです。
反対に、情報が漏えいが発生してしまうと、最悪ビジネスが中断することになり、会社は将来においてたくさん稼ぐチャンスを逃してしまうリスクがあります。加えて、例えば、この漏えいが相手の会社のもとで起きたとして、相手に責任追及しても、これらのチャンスによって得られたはずの利益の全部を回収することには、法的に難しい面もあります。
ですから、ビジネスを着々と成長させていけるよう、お互いに大切な情報を交換したり、将来において大きな利益を見込める取引においては特に、しっかりとNDAを締結しておくことを、おすすめします。
とても大切なことの1つとして、NDAの最大の狙いは、お互いに「相手から渡された情報をきちんと管理しよう」という意識を芽生えさせることで、漏えいを『未然に』防ぐことなんですよ。
例えば、漏えいが発生することなく、取引がスムーズに進むと、会社の商品・サービスも普及するし、会社の評判もより良くなっていくでしょう? そうしていくと、取引先が多くなって会社の利益が増えたり、その増えた利益を使って事業をもっと強くしたり、その他にも、別の会社から『わが社と提携して新しいビジネスに挑戦しませんか?』と誘ってもらえる等、会社を大きくしていけるんです。
反対に、情報が漏えいが発生してしまうと、最悪ビジネスが中断することになり、会社は将来においてたくさん稼ぐチャンスを逃してしまうリスクがあります。加えて、例えば、この漏えいが相手の会社のもとで起きたとして、相手に責任追及しても、これらのチャンスによって得られたはずの利益の全部を回収することには、法的に難しい面もあります。
ですから、ビジネスを着々と成長させていけるよう、お互いに大切な情報を交換したり、将来において大きな利益を見込める取引においては特に、しっかりとNDAを締結しておくことを、おすすめします。
小野弁護士
- NDAと特許や個人情報との関係について
- 実は、情報漏えいを防ぐことは、特許や個人情報との関係でも、とても重要な意味を持っているんですよ。
 小野弁護士
小野弁護士
 T社長そうなんですか? もう少し詳しく教えてもらいたいです。もちろんです。まずは、特許法との関係について説明しましょう。
T社長そうなんですか? もう少し詳しく教えてもらいたいです。もちろんです。まずは、特許法との関係について説明しましょう。
特許を取得するには、その対象となる発明(技術・アイデアなど)が『国内外において、知られていないこと』(新規性)を満たしている必要があります(特許法29条1項1号参照)。
ですから、もし、漏えいした情報の中に、将来において特許取得を考えている技術・アイデアなどが含まれていると、この『新規性』をクリアできず、特許を取得できなくなってしまうリスクがあるんです。 小野弁護士また、いったん特許出願すると、仮にその出願が失敗しても、1年半後に出願内容が公開されてしまうので、この場合にも『新規性』をクリアできず、再び同一の特許取得に挑戦することが難しくなってしまうことにも、注意が必要です。
小野弁護士また、いったん特許出願すると、仮にその出願が失敗しても、1年半後に出願内容が公開されてしまうので、この場合にも『新規性』をクリアできず、再び同一の特許取得に挑戦することが難しくなってしまうことにも、注意が必要です。
こうした特許実務との関係から、特に将来の特許取得が想定されるビジネスでは、NDAをしっかりと締結し、その中に『漏えい防止に向けて、秘密情報をどう管理し、取扱うべきか』や『特許出願する際には、誰が、どういった内容で行うのか』を書いておくことが、とても大事なんです。
さらに、仮に特許取得が成功したときは、その権利をめぐって双方で揉めてしまう可能性もゼロではありませんので、NDAの中に『その権利が、どちらに、どれくらいの割合で帰属するのか』について書いておくことも、多いですね。
会社にとってビジネスの軸になる特許であればあるほど、それを取得することは、双方にとって、とてもメリットがあります。ですから、ここで話したことを踏まえて、適切な内容でNDAを締結しておくことが大切なんです。
 小野弁護士
小野弁護士 T社長なるほど。次に、個人情報保護法との関係について説明しますね。
T社長なるほど。次に、個人情報保護法との関係について説明しますね。
例えば、T社長の会社が、『自社のサービスを代理店を通し販売すると決め、担当してもらう地域の顧客リストを、その代理店に渡した』というシーンを想像してみてください。
代理店への依頼は民法上の「委託」(民法643条)にあたると考えられますので、T社長の会社には、個人情報保護法に従い、その代理店がきちんと顧客リストを管理しているかをチェックすべき義務が課されます(個人情報保護法25条)。
NDAを締結して、代理店側に対し顧客リストを適切かつ安全に取扱うよう求めておくと、このチェックをきちんと行っていた(=つまり、義務違反はなかった)という事情の1つになります。
また、漏えいが起きると、不安になってしまった顧客から、同法に則り『わたしの個人情報を使わないで欲しい』とか『わたしの個人情報を顧客リストから削除して欲しい』のクレームを入れられてしまい、会社のビジネスに支障が生じるリスクもあります。
こうした個人情報をめぐる問題との関係からも、相手の会社とNDAを締結しておく意味があるんですよ。
なお、実際のビジネスでは、『秘密情報』(技術情報、営業情報など)と『個人情報』とでNDAを分けて締結せずに、1本のNDAとして、まとめて締結してしまうケースが多いですね。 小野弁護士
小野弁護士 T社長NDAって、ビジネスの色々な所と繋がっているんですね。そのとおりです! ですから、個々の場面でNDAを締結する意味をきちんと把握しておくことは、会社にとって、とても重要なことなんですよ。
T社長NDAって、ビジネスの色々な所と繋がっているんですね。そのとおりです! ですから、個々の場面でNDAを締結する意味をきちんと把握しておくことは、会社にとって、とても重要なことなんですよ。 小野弁護士
小野弁護士
漏えいがあった場合に、相手にNDAに基づき損害賠償を求めることができる
2つ目のメリットは、『相手に対する責任追及のハードルを下げること』ですね。
適切な損害賠償条項を入れておくと、万一、自社情報の漏えいが起きても、相手に対し『わが社が受けた損失を補償してください』って言いやすくなるんですよ。
また、この場合、相手としては『損害賠償を受けるって怖いなぁ。ちゃんと管理しないと!』っていう気持ちになるので、結果として、漏えいリスクを下げることにも繋がります。
なお、NDAを締結していないと、相手に対し賠償を求める手段がまったくないというわけではないですが、ややハードルが高くなる面もありますし、できるだけ責任追及できるパターンを多く持っておいた方が、状況によって使い分けられるので、適切なNDAを締結しておくことは会社にとって安心なんですよ。
適切な損害賠償条項を入れておくと、万一、自社情報の漏えいが起きても、相手に対し『わが社が受けた損失を補償してください』って言いやすくなるんですよ。
また、この場合、相手としては『損害賠償を受けるって怖いなぁ。ちゃんと管理しないと!』っていう気持ちになるので、結果として、漏えいリスクを下げることにも繋がります。
なお、NDAを締結していないと、相手に対し賠償を求める手段がまったくないというわけではないですが、ややハードルが高くなる面もありますし、できるだけ責任追及できるパターンを多く持っておいた方が、状況によって使い分けられるので、適切なNDAを締結しておくことは会社にとって安心なんですよ。
小野弁護士
法律よりも広い範囲で自社の情報を保護できる
3つ目のメリットは、『法律よりも広い範囲で、秘密情報を保護すること』ですね。
会社の情報を保護する法律の1つに、『不正競争防止法』があります。ただ、この法律によって保護される会社の情報には制限があります。
ですから、この法律によって保護できない会社の情報については、NDAを使って保護しておくんですよ。
会社の情報を保護する法律の1つに、『不正競争防止法』があります。ただ、この法律によって保護される会社の情報には制限があります。
ですから、この法律によって保護できない会社の情報については、NDAを使って保護しておくんですよ。
小野弁護士
T社長
なるほど、法律でカバーできない所を契約で補うのか。
まさにそのとおりです。法律とNDAの両方を使って、会社の利益をしっかりと保護しましょう。
小野弁護士
- 不正競争防止法の適用ケース(一例)
 T社長不正競争防止法が適用されるケースとして、例えば、どんなものがあるんでしょうか?それでは、いくつか例を挙げてみましょうか。
T社長不正競争防止法が適用されるケースとして、例えば、どんなものがあるんでしょうか?それでは、いくつか例を挙げてみましょうか。
一例ですが、① A社が、T社長の会社の情報を、直接不正な方法で入手したり、または、T社長の会社の従業員を唆して入手した場合、② 『他の人(会社)に勝手に教えない』という約束のもと、T社長の会社がA社に対し情報を開示した所、A社がこの約束を破って、この情報をB社に教えてしまった場合などがあります。
シンプルに言ってしまうと、不正競争防止法が適用されるのは「不正(≒違法)」と言える方法によって情報が漏えいした場合ということですね。
なお、仮に不正競争防止法が適用されるとすれば、T社長の会社は、同法を根拠にして、A社やB社に対し、『わが社の情報を使わないでください』と請求したり、『わが社が被った損害を支払ってください』と請求することができます(不正競争防止法2条~4条参照)。
その他にも、損害賠償を請求するときは、民法の原則だと、漏えいによってA社が被った損失がいくらなのかは、A社で証明する必要があり、一般的には、その証明のハードルが高いと言えます。ですが、不正競争防止法を適用できると、A社において、この証明のハードルがグッと下へることができます(不正競争防止法5条)。 小野弁護士
小野弁護士 T社長へぇ、不正競争防止法ってすごいんですね。はい。でも、同法が適用されるには、その前提として、漏えいした情報が「営業秘密」にあたることが求められます。
T社長へぇ、不正競争防止法ってすごいんですね。はい。でも、同法が適用されるには、その前提として、漏えいした情報が「営業秘密」にあたることが求められます。 小野弁護士
小野弁護士 T社長その「営業秘密」ってなんですか?「営業秘密」っていうのは、⑴秘密管理性、⑵有用性、⑶非公知性、という3つの要件を満たすものを言います(不正競争防止法2条6項)。
T社長その「営業秘密」ってなんですか?「営業秘密」っていうのは、⑴秘密管理性、⑵有用性、⑶非公知性、という3つの要件を満たすものを言います(不正競争防止法2条6項)。
もう少しかみ砕くと、『⑴ 会社においてきちんとしたセキュリティ体制の下で外に漏れないよう管理されているもので、⑵ それが、商品・サービスの製造または販売の方法、経営戦略・顧客情報などの会社の事業上・営業上の情報にあたり、かつ⑶ 世間においてまだ知られていないもの』ということですね。
要するに、不正競争防止法によって保護される情報とは、『その会社にとって』大切であると同時に、『世間的にも』そのことが認められるものっていうことです。 小野弁護士
小野弁護士 T社長そう聞くと、法律に頼るばかりでなく、自社においてもNDAを締結するなどして、しっかりと会社の情報を保護していかないとって思いますね。まさにそのとおりです。その意識が大切です。
T社長そう聞くと、法律に頼るばかりでなく、自社においてもNDAを締結するなどして、しっかりと会社の情報を保護していかないとって思いますね。まさにそのとおりです。その意識が大切です。 小野弁護士
小野弁護士
相手の信頼を獲得することに繋がる
「4つ目のメリットは、『取引の相手の信頼を獲得すること』についてですね。
自社の情報を大切に扱って欲しいと思うのは、相手の会社も同じです。
ですから、T社長の会社が適切な内容のNDAを締結する姿勢を持っていると、『T社長の会社は、情報管理について関心のある会社だから、安心して取引できるな』というように、相手の会社から信頼してもらうきっかけにもなるんです。
自社の情報を大切に扱って欲しいと思うのは、相手の会社も同じです。
ですから、T社長の会社が適切な内容のNDAを締結する姿勢を持っていると、『T社長の会社は、情報管理について関心のある会社だから、安心して取引できるな』というように、相手の会社から信頼してもらうきっかけにもなるんです。
小野弁護士
T社長
NDAって、心理的な面においても、会社のビジネスをサポートしてくれるんだなぁ。
秘密保持契約は、どのタイミングで締結すればいいですか?
(秘密保持契約(NDA)の締結のケースやタイミングの紹介)
では次に、どんなタイミングでNDAを締結するのがよいかについてお話しましょう。
小野弁護士
T社長
この辺りはよくわかっていないので助かります。
NDAの締結場面としては、①取引成立可能性(=相手と取引を行うか)について検討するとき、②すでに成立した取引を始めるとき、③M&Aを行うとき、④他の会社と手を組んでビジネスを行うとき、などが挙げられます。
せっかくですから、①~④について、簡単に紹介しておきましょうか。
わかりやすいように、何かストーリーを仮定して、それに沿ってお話していきましょう。
例えば、「T社長の会社が、一般のボールペンと比べて『軽さと頑丈さ』を重視したボールペン(新型ボールペン)を販売するという事業計画を立て、これに沿ってビジネスを進めていく」といったストーリーなんかどうでしょう?
せっかくですから、①~④について、簡単に紹介しておきましょうか。
わかりやすいように、何かストーリーを仮定して、それに沿ってお話していきましょう。
例えば、「T社長の会社が、一般のボールペンと比べて『軽さと頑丈さ』を重視したボールペン(新型ボールペン)を販売するという事業計画を立て、これに沿ってビジネスを進めていく」といったストーリーなんかどうでしょう?
小野弁護士
T社長
面白そうですね。それでお願いします!
1つ目は、『取引成立可能性(=相手と取引を行うか)について検討するとき』ですね。
先ほどのストーリーに沿うと、T社長の会社としては、まず、新型ボールペンを製造する必要がありますよね。そうすると、製造に必要な原料・部品などを他の会社から仕入れるため、仕入先候補との間で、商談や打ち合わせを行うことになるかと思います。
この商談等においては、T社長の会社から『新型ボールペンを軸にしたビジネスの概要』といった自社の営業戦略を伝えたり、または『そのボールペンの図面や構造の一部』などを教えることが予想されます。
反対に、仕入先候補の会社からは『提供する原料・部品が新型ボールペンの特徴(=軽さと頑丈さ)に適合する可能性』『過去の実例』といった技術的な情報であったり、『その原料等をいくらで販売しているか』といった営業情報などを教えてもらうことが予想されます。
これらの情報は、もしライバル会社に利用されると、会社の売上が落ちてしまうおそれがあります。つまり、双方にとって、他社に知られたくない情報ということです。
ですから、『取引成立可能性を検討するとき』には、NDAを締結しておくことを、おすすめします。
先ほどのストーリーに沿うと、T社長の会社としては、まず、新型ボールペンを製造する必要がありますよね。そうすると、製造に必要な原料・部品などを他の会社から仕入れるため、仕入先候補との間で、商談や打ち合わせを行うことになるかと思います。
この商談等においては、T社長の会社から『新型ボールペンを軸にしたビジネスの概要』といった自社の営業戦略を伝えたり、または『そのボールペンの図面や構造の一部』などを教えることが予想されます。
反対に、仕入先候補の会社からは『提供する原料・部品が新型ボールペンの特徴(=軽さと頑丈さ)に適合する可能性』『過去の実例』といった技術的な情報であったり、『その原料等をいくらで販売しているか』といった営業情報などを教えてもらうことが予想されます。
これらの情報は、もしライバル会社に利用されると、会社の売上が落ちてしまうおそれがあります。つまり、双方にとって、他社に知られたくない情報ということです。
ですから、『取引成立可能性を検討するとき』には、NDAを締結しておくことを、おすすめします。
小野弁護士
2つ目は、『すでに成立した取引を始めるとき』ですね。
小野弁護士
T社長
『すでに成立した取引を始めるとき』にもNDAを締結するんですか? ①の場面においては、仕入先候補の会社と色々な情報を交換するのはわかったけど、取引開始後って、商品やサービスを提供するだけだし、相手に何か大切な情報を渡したりするかなぁ。
よい質問ですね。ところが、取引開始後においても、大切な情報を取引先に渡すこともあるんですよ。
例えば、T社長の会社で予定していたとおり、無事に、「軽さと頑丈さ」を備えた新型ボールペンを製造でき、A社(買主)との間で、このボールペンの売買契約を締結できたとします。そうすると、これからA社に対し、新型ボールペンを納品していくことになりますよね?
ですが、このボールペンには、T社長の会社の技術やアイデアなどが詰まっているわけです。ですから、もし、A社がこれを勝手に分解・分析して、それにより知った情報を活用し、類似品を製造したり、または、ライバル会社にこの情報を教えたりすると、新型ボールペンの売れ筋が悪くなり、予定していたビジネスが頓挫するリスクがあります。
他にも、実際のビジネスでは、相手の会社との連絡をスムーズに行うために、連絡担当を任せる従業員の氏名などを教えることもあります。
ですから、『すでに成立した取引を開始するとき』にも、きちんとNDAを締結しておくんですよ。
例えば、T社長の会社で予定していたとおり、無事に、「軽さと頑丈さ」を備えた新型ボールペンを製造でき、A社(買主)との間で、このボールペンの売買契約を締結できたとします。そうすると、これからA社に対し、新型ボールペンを納品していくことになりますよね?
ですが、このボールペンには、T社長の会社の技術やアイデアなどが詰まっているわけです。ですから、もし、A社がこれを勝手に分解・分析して、それにより知った情報を活用し、類似品を製造したり、または、ライバル会社にこの情報を教えたりすると、新型ボールペンの売れ筋が悪くなり、予定していたビジネスが頓挫するリスクがあります。
他にも、実際のビジネスでは、相手の会社との連絡をスムーズに行うために、連絡担当を任せる従業員の氏名などを教えることもあります。
ですから、『すでに成立した取引を開始するとき』にも、きちんとNDAを締結しておくんですよ。
小野弁護士
T社長
こうして見ると、取引開始後においても、大切な情報を相手に渡したり、教えたりしているものなんだなぁ。この場合にも、しっかりとNDAを締結しておこう。
3つ目は、『M&Aを行うとき』ですね。
例えば、新型ボールペンの売れ行きが良くて、T社長の会社において『在庫切れしないよう、もっとたくさん作りたい』と思ったとします。そうすると、このボールペンをたくさん製造できるよう、他の会社の工場を買収するなどを検討することもあるでしょう。
この場合、T社長としては、例えば、どんなことに注意して買収したいですか?
例えば、新型ボールペンの売れ行きが良くて、T社長の会社において『在庫切れしないよう、もっとたくさん作りたい』と思ったとします。そうすると、このボールペンをたくさん製造できるよう、他の会社の工場を買収するなどを検討することもあるでしょう。
この場合、T社長としては、例えば、どんなことに注意して買収したいですか?
小野弁護士
T社長
えーと、工場を買収する目的は「新型ボールペンの増産」だから…、『その工場において、新たに製造できる新型ボールペンの数が、わが社が希望している増産数をカバーできるのかどうか』とかに注意するかなぁ。
いいですね! それは最も大切なことの1つだと思います。
その他にも、工場において『新商品の特徴である「軽さと丈夫さ」を実現するのに適した設備を保有しているか』や、現場で働く従業員ごと買収するときには『これらの従業員がボールペンやその素材・構造について、適切な知識やノウハウを持っているか』なども、注意しておくとよいかもしれないですね。
そうすると、この買収に際し、『事業戦略』や『新商品の素材や構造、加工方法』、『新型ボールペンを作る上で求める知識やノウハウ』などを、(T社長の会社から)工場側に教えることも想定されます。
ですが、これらの情報は、このボールペンを軸にしたビジネスを成功させるうえで、とても大切な情報ですよね? つまり、T社長からすると、特に外に知られたくない情報ということです。
ですから、買収・合併などの『M&Aを行うとき』は、しっかりとNDAを締結しておくといいですよ。
その他にも、工場において『新商品の特徴である「軽さと丈夫さ」を実現するのに適した設備を保有しているか』や、現場で働く従業員ごと買収するときには『これらの従業員がボールペンやその素材・構造について、適切な知識やノウハウを持っているか』なども、注意しておくとよいかもしれないですね。
そうすると、この買収に際し、『事業戦略』や『新商品の素材や構造、加工方法』、『新型ボールペンを作る上で求める知識やノウハウ』などを、(T社長の会社から)工場側に教えることも想定されます。
ですが、これらの情報は、このボールペンを軸にしたビジネスを成功させるうえで、とても大切な情報ですよね? つまり、T社長からすると、特に外に知られたくない情報ということです。
ですから、買収・合併などの『M&Aを行うとき』は、しっかりとNDAを締結しておくといいですよ。
小野弁護士
4つ目は、『他の会社と手を組んでビジネスを行うとき』ですね。
さて、工場の買収も成功し、T社長の会社で販売する新型ボールペンが、広い地域に普及するようになり、これに伴って、お客さんから『ボールペンの素材がやや固くて、手に馴染みにくい所を改良してほしい』との要望が多く寄せられたとします。
そうすると、このフィードバックに応えるべく、例えば、『頑丈で加工しやすい素材を取り扱っているメーカー』や『握り心地について追及してきたボールペンメーカー』などとタッグを組んで、改良品に挑戦することもあるでしょう。
この場合、お互いに、自社の大切な武器である技術やノウハウなどについて、交換し合うことになります。
ですから、『他の会社と手を組んでビジネスを行うとき』には、こういった大事な情報が外に漏れないようにするため、NDAを締結することがとても多いんですよ。
さて、工場の買収も成功し、T社長の会社で販売する新型ボールペンが、広い地域に普及するようになり、これに伴って、お客さんから『ボールペンの素材がやや固くて、手に馴染みにくい所を改良してほしい』との要望が多く寄せられたとします。
そうすると、このフィードバックに応えるべく、例えば、『頑丈で加工しやすい素材を取り扱っているメーカー』や『握り心地について追及してきたボールペンメーカー』などとタッグを組んで、改良品に挑戦することもあるでしょう。
この場合、お互いに、自社の大切な武器である技術やノウハウなどについて、交換し合うことになります。
ですから、『他の会社と手を組んでビジネスを行うとき』には、こういった大事な情報が外に漏れないようにするため、NDAを締結することがとても多いんですよ。
小野弁護士
さらに、ここまで解説した①~④のケースのすべてに共通して大切なことがあります。それは『相手に情報を教える前にNDAを締結すること』です。
契約っていうのは、お互いが合意した時から、双方を(その契約で定めた)ルールに拘束するんです。言い換えると、もし、NDAを締結する前に相手に大切な情報を教えてしまうと、相手はその情報については、そのNDAで決めたルールに則って取り扱わなくてもよいということになってしまうんです。
ですから、お互いに大事な情報を交換しようとする前にNDAを締結することが大切なポイントです。これにより、自社の情報を適切に保護してもらえるんですよ。
契約っていうのは、お互いが合意した時から、双方を(その契約で定めた)ルールに拘束するんです。言い換えると、もし、NDAを締結する前に相手に大切な情報を教えてしまうと、相手はその情報については、そのNDAで決めたルールに則って取り扱わなくてもよいということになってしまうんです。
ですから、お互いに大事な情報を交換しようとする前にNDAを締結することが大切なポイントです。これにより、自社の情報を適切に保護してもらえるんですよ。
小野弁護士
T社長
なるほど。ということは、もし、うっかりしてNDAの締結前の段階で、相手にわが社の情報を教えちゃったときには、手遅れっていうことですか?
必ずしも、そうとは言い切れないです。
というのも、教えてしまった後に締結する場合であっても、NDAの中に『締結前に教えた情報についても、さかのぼって守秘として扱うべき』旨の条項を入れておけば、締結前に教えた情報にもこのNDAに則った取扱いを求めることができるからです。実務でも、ビジネスのスピードを重視して、事後的にNDAを結ぶことで、対応するケースもあります。
でも、このように事後的に対応すると、相手としては、NDAを締結するまでの間、『預かった情報を守秘として扱うべき』という意識がもてないことになります。そうすると、ずさんに扱ってしまい、運が悪いと、NDAを締結した頃には、すでに漏えいが起きてしまっているといった可能性もゼロではありません。
ですから、できる限り情報を教える前にNDAを締結しておくよう、おすすめします。
というのも、教えてしまった後に締結する場合であっても、NDAの中に『締結前に教えた情報についても、さかのぼって守秘として扱うべき』旨の条項を入れておけば、締結前に教えた情報にもこのNDAに則った取扱いを求めることができるからです。実務でも、ビジネスのスピードを重視して、事後的にNDAを結ぶことで、対応するケースもあります。
でも、このように事後的に対応すると、相手としては、NDAを締結するまでの間、『預かった情報を守秘として扱うべき』という意識がもてないことになります。そうすると、ずさんに扱ってしまい、運が悪いと、NDAを締結した頃には、すでに漏えいが起きてしまっているといった可能性もゼロではありません。
ですから、できる限り情報を教える前にNDAを締結しておくよう、おすすめします。
小野弁護士
T社長
よくわかりました。
秘密保持契約には、どんなことを書きますか?
(秘密保持契約における主な条項や事項、およびその締結のポイントの解説)
T社長
NDA(秘密保持契約)には、どんなことを書いておくといいんでしょうか?
やや多くはありますが、一般には、NDAによく書かれる条項(規定)として、次の10項目を挙げることができます。
⑴ 当事者
⑵ NDAを締結する目的
⑶ 秘密情報の定義
⑷ 秘密保持義務の内容
⑸ 目的外使用の禁止
⑹ 返還・破棄など
⑺ 知財に関する取扱い
⑻ 契約の有効期限
⑼ 存続条項
⑽ 損害賠償その他トラブル解決のルール
以下、これらの条項を、順に見ていきましょう。
⑴ 当事者
⑵ NDAを締結する目的
⑶ 秘密情報の定義
⑷ 秘密保持義務の内容
⑸ 目的外使用の禁止
⑹ 返還・破棄など
⑺ 知財に関する取扱い
⑻ 契約の有効期限
⑼ 存続条項
⑽ 損害賠償その他トラブル解決のルール
以下、これらの条項を、順に見ていきましょう。
小野弁護士
当事者
1項目は、「当事者」ですね。シンプルに言うと、『このNDAに合意した人は誰なのか』ってことです。
契約の効力は、『その契約に合意した人に対してのみ及ぶ』というのが、法の原則です。
そうすると、もしも、相手の会社が「当事者」から抜け落ちていると、相手の会社に対し「締結したNDAに従って、預けた情報を丁寧に管理してください」とお願いしても、相手から「わが社はそもそも『当事者』ではないので、そのNDAに従うことはできません」と言われてしまうおそれがあるんです。
ですから、大切な情報を渡す相手の会社が「当事者」から抜け落ちていないかをチェックすることが、とても大切なんですよ。
契約の効力は、『その契約に合意した人に対してのみ及ぶ』というのが、法の原則です。
そうすると、もしも、相手の会社が「当事者」から抜け落ちていると、相手の会社に対し「締結したNDAに従って、預けた情報を丁寧に管理してください」とお願いしても、相手から「わが社はそもそも『当事者』ではないので、そのNDAに従うことはできません」と言われてしまうおそれがあるんです。
ですから、大切な情報を渡す相手の会社が「当事者」から抜け落ちていないかをチェックすることが、とても大切なんですよ。
小野弁護士
NDAを締結する目的
2項目は、「NDAを締結する目的」ですね。すべての契約に言えることではありますが、契約内容っていうのは、できれば単純明快である方が、当事者にとってみると『何ができて、何をしなければならないのか』がはっきりとするので、望ましいです。
NDAに置き換えると、『私の会社から提供する秘密情報は「情報A」「情報B」だけで、その他にはありません』といったように、もし、秘密とすべき情報を完全に特定できるならば、情報を預かる側の立場からすると負担が小さくて済む、ということです。
もっとも、実際のビジネスでは、取引を進めていく中で「締結段階では予定していなかったけど、「情報C」も追加で渡しておきたいな」と思うこともあるでしょう?
こうした場合に備えて、契約実務においては『今回の取引に関連して、あなたの会社に教える、営業上、事業上または技術上の情報の一切』といったように、秘密情報についてやや広めに定義しておくことが多いです。
こうした契約実務との関係から、「NDAを締結する目的」をしっかりと書いておくことがとても大切なんですよ。そうすることで、たとえ秘密情報についてやや幅のある定義がされていても、この目的を道しるべにして、「どの情報が秘密情報なのか」について判断できる状態にしておけるんです。
小野弁護士
T社長
なるほど。『ビジネス上の都合』と『法的な負担』とのバランスを図るために、「NDAを締結する目的」をきちんと書いておくということですね。
そのとおりです!
小野弁護士
秘密情報の定義
3項目は、「秘密情報の定義」ですね。
どの情報を守秘として扱うべきかがはっきりしないと、『いったいどの情報を「秘密情報」として守秘扱いすればよいのか』がわからないでしょう?
ですから、守秘とすべき情報(=「秘密情報」)について定義をきちんと書くことで、双方において、どの情報を守秘として扱うべきかをハッキリとさせるんです。また、こうしておくと、情報を預かっている側において、ガードすべき箇所が定まり、これによりガードが強固となるので、かえって漏えいリスクを低減することにも繋がります。
どの情報を守秘として扱うべきかがはっきりしないと、『いったいどの情報を「秘密情報」として守秘扱いすればよいのか』がわからないでしょう?
ですから、守秘とすべき情報(=「秘密情報」)について定義をきちんと書くことで、双方において、どの情報を守秘として扱うべきかをハッキリとさせるんです。また、こうしておくと、情報を預かっている側において、ガードすべき箇所が定まり、これによりガードが強固となるので、かえって漏えいリスクを低減することにも繋がります。
小野弁護士
T社長
確かに、そうですね。でも、2項目めで説明してもらったときは、『秘密情報を定義する際には、ある程度幅のある表現を使うことも多い』って教えてもらいましたよね? じゃあ、どうやって明確に定義するんですか?
よい質問ですね。実は、2項目めで説明した『「NDAを締結する目的」をきちんと書くこと』以外にも、秘密情報を明確に定義できる方法はあります。
シンプルに言うと、秘密情報を相手の会社に渡す際に、相手がしっかりと認識できる方法でハッキリと「この書面やメールに載っている(またはこのCD-ROM等に記録されている)情報は、『秘密情報』です」って書くというルールを作り、これを締結するNDAにきちんと書いておくことです。
シンプルに言うと、秘密情報を相手の会社に渡す際に、相手がしっかりと認識できる方法でハッキリと「この書面やメールに載っている(またはこのCD-ROM等に記録されている)情報は、『秘密情報』です」って書くというルールを作り、これを締結するNDAにきちんと書いておくことです。
小野弁護士
T社長
なるほど、確かにその方法を使えば、どの情報が秘密情報なのかが明確になりますね。でも、相手に情報を渡す際に、都度、書面やメールなどに『これは秘密情報ですよ』って明記するのも、少しめんどくさいなぁ。
おっしゃるように、このルールでは、情報を開示する側にもやや負担はあります。
でも、このように定めておくと、T社長の会社において相手から情報を預かる場合、とても楽になります。また、反対にT社の会社から相手に情報を渡す場合においても、相手にとって『どの情報を漏えいからしっかりガードすればいいのか』が一目瞭然となりますので、相手の会社のもとで、自社の大切な情報が漏えいするリスクを低減できます。
でも、このように定めておくと、T社長の会社において相手から情報を預かる場合、とても楽になります。また、反対にT社の会社から相手に情報を渡す場合においても、相手にとって『どの情報を漏えいからしっかりガードすればいいのか』が一目瞭然となりますので、相手の会社のもとで、自社の大切な情報が漏えいするリスクを低減できます。
小野弁護士
T社長
多少手間がかかっても、漏えいが起きてしまうよりはマシか。この方法についても、今後検討してみようかな。
秘密保持義務の内容
4項目は、「秘密保持義務の内容」ですね。
簡単に言うと、お互いの守秘情報を、『どういったセキュリティ水準・体制のもとで、どのように取扱うのか』についてルール化しておくということです。まさに、NDAにおいて最も大切なポイントの1つになる条項ですね。
このルールについては、「善良な管理者の注意義務をもって(厳に管理する)」といった法令の文言(民法644条など)を引用したり、この文言を少し噛み砕いて「職業人としての合理的な注意義務をもって適切に管理する」などど、シンプルに書いてしまうケースが多いですね。
簡単に言うと、お互いの守秘情報を、『どういったセキュリティ水準・体制のもとで、どのように取扱うのか』についてルール化しておくということです。まさに、NDAにおいて最も大切なポイントの1つになる条項ですね。
このルールについては、「善良な管理者の注意義務をもって(厳に管理する)」といった法令の文言(民法644条など)を引用したり、この文言を少し噛み砕いて「職業人としての合理的な注意義務をもって適切に管理する」などど、シンプルに書いてしまうケースが多いですね。
小野弁護士
その他にも、秘密保持義務の内容の1つとして、『わが社から教えた情報を、他の会社に見せてはダメですよ』っていうルールを書いておくことも、とても多いです。
小野弁護士
T社長
他の会社に見せてはいけないっていうと、例えば、わが社が相手の会社から商品を購入して、その販売を代理店に任せる場合、相手の会社から受け取った商品情報を、代理店との間で共有できないってことですか? それだと、代理店にお願いする意味が半減してしまうようにも感じます。
T社長がお考えのように、もし、代理店との間でその商品の特徴などについてシェアができないとしたら、新たに販路を広げたり、売上を伸ばすなどの見込みも立てにくく、1つ1つのビジネスが重くなってしまいますよね。
ですから、もし、相手から教えてもらった情報を、他の会社に見せる予定(つまり、再開示の予定)があるときは、例外的に再開示が認められるケースについて書いておくといいですよ。
ですから、もし、相手から教えてもらった情報を、他の会社に見せる予定(つまり、再開示の予定)があるときは、例外的に再開示が認められるケースについて書いておくといいですよ。
小野弁護士
T社長
相手の会社との取引だけでなく、そこに関連するビジネスも考えながら、再開示の範囲を決めていかないといけないのか。適切なNDAを作るのって、難しいんだなぁ。
目的外使用の禁止
5項目は、「目的外使用の禁止」ですね。
つまり、『わが社の守秘情報を、合意していない目的のために、勝手に使わないでください』ということを書いておくんです。
自分の会社の大切な情報である守秘情報を、相手に渡すのは、ひとえに相手との取引をスムーズに進めるためです。ですから、取引に必要な範囲でのみ、秘密情報を使える形にしておくんですよ。
つまり、『わが社の守秘情報を、合意していない目的のために、勝手に使わないでください』ということを書いておくんです。
自分の会社の大切な情報である守秘情報を、相手に渡すのは、ひとえに相手との取引をスムーズに進めるためです。ですから、取引に必要な範囲でのみ、秘密情報を使える形にしておくんですよ。
小野弁護士
返還・破棄など
6項目は、「返還・破棄など」ですね。
これは、相手の会社に預けている守秘情報について、返すよう求めたり、返す代わりに相手方で廃棄等してもらうよう求める場合のルールを決めるということですね。
これは、相手の会社に預けている守秘情報について、返すよう求めたり、返す代わりに相手方で廃棄等してもらうよう求める場合のルールを決めるということですね。
小野弁護士
T社長
相手に渡した情報なのに、「返してください」と言ったり、「廃棄してください」って言えるんですか?
はい、原則としては言えます。
というのも、NDAというのは『預けた』情報の取扱いルールを決めるものです。つまり、T社長の会社から相手に情報を渡しても、それは『預けた』のであり引続きT社長の会社のものです。ですから、「返せ」や「廃棄しろ」って言えるんですよ。
というのも、NDAというのは『預けた』情報の取扱いルールを決めるものです。つまり、T社長の会社から相手に情報を渡しても、それは『預けた』のであり引続きT社長の会社のものです。ですから、「返せ」や「廃棄しろ」って言えるんですよ。
小野弁護士
T社長
なるほど、それは道理ですね。
知財に関する取扱い
7項目は、「知財に関する取扱い」ですね。
要するに、相手の会社が、預かっている秘密情報を元ネタにして新しい発明や考案などをした場合に備えて、『(その発明等について)特許庁への申請は、誰が、どういった手続で行うのか』『仮に特許等を取得できた場合、どちらに、どれくらいの割合で帰属するのか』などのルールを決めておくということですね。
要するに、相手の会社が、預かっている秘密情報を元ネタにして新しい発明や考案などをした場合に備えて、『(その発明等について)特許庁への申請は、誰が、どういった手続で行うのか』『仮に特許等を取得できた場合、どちらに、どれくらいの割合で帰属するのか』などのルールを決めておくということですね。
小野弁護士
契約の有効期限
8項目は、「契約の有効期限」ですね。
要するに、『満期をいつにするか』ってことですね。
一般に、NDAは、例えば、売買、委託、買収などの主たる取引に付随して締結されることが多いです。ですから、こうした主たる取引(売買、委託、買収など)がいつまで続くのかを考慮して、これに合わせてNDAの満期を決めることが多いですね。
要するに、『満期をいつにするか』ってことですね。
一般に、NDAは、例えば、売買、委託、買収などの主たる取引に付随して締結されることが多いです。ですから、こうした主たる取引(売買、委託、買収など)がいつまで続くのかを考慮して、これに合わせてNDAの満期を決めることが多いですね。
小野弁護士
存続条項
9項目は、「存続条項」(=契約終了後も、その効力が続く条項)ですね。
契約が終了すると、原則として、その契約に書かれていた各条項の効力も消滅します。言い換えると、契約が終了してしまうと、例えば、「第○○条に基づいて、~してください」と請求できなくなってしまうということです。
でも、ケースによっては、契約終了後においても、終了前と同じように請求したいときもありますよね。
ですから、当該請求の根拠となる条項について、「存続条項」として契約書に書いておくんです。
契約が終了すると、原則として、その契約に書かれていた各条項の効力も消滅します。言い換えると、契約が終了してしまうと、例えば、「第○○条に基づいて、~してください」と請求できなくなってしまうということです。
でも、ケースによっては、契約終了後においても、終了前と同じように請求したいときもありますよね。
ですから、当該請求の根拠となる条項について、「存続条項」として契約書に書いておくんです。
小野弁護士
T社長
NDAにおいては、この存続条項を定めておかないと、どんなリスクがあるんでしょうか?
例えば、相手の会社から自社情報を返還してもらわないうちに、NDAが満期をすぎた場合をイメージしてみてください。この場合、もし、NDAに存続条項が定められていないと、状況としては、NDAを締結せずに、相手のもとに秘密情報を預けているのと同じになってしまいます。
そうすると、T社長の会社の情報を不適切に取り扱われて、漏えいしてしまうリスクが高まってしまいます。
そうすると、T社長の会社の情報を不適切に取り扱われて、漏えいしてしまうリスクが高まってしまいます。
小野弁護士
T社長
わが社から外秘情報を教えていることもあるだろうし、こういった情報を返してもらったり破棄してもらうまでは、きちんと管理していてもらいたいです。
そうですよね。ですから、秘密保持義務、目的外使用の禁止、返還・破棄や知財の取扱に関するルールを存族条項として定めておくことが多いんですよ。
その他にも、もしトラブルに発展した場合に備え、損害賠償ルールや裁判管轄、準拠法などを定めた条項についても、存続条項として書いておくとよいと思います。
ただし、『どの条項を、どれくらい、存続させておくのがよいのか』については、個々のビジネスごとに変わってきますので、外部の弁護士などに念のためチェックしてもらっておくと安心ですよ。
その他にも、もしトラブルに発展した場合に備え、損害賠償ルールや裁判管轄、準拠法などを定めた条項についても、存続条項として書いておくとよいと思います。
ただし、『どの条項を、どれくらい、存続させておくのがよいのか』については、個々のビジネスごとに変わってきますので、外部の弁護士などに念のためチェックしてもらっておくと安心ですよ。
小野弁護士
T社長
わかりました。そのときは、先生にチェックしてもらってもいいでしょうか?
もちろんです。いつでもどうぞ。
小野弁護士
損害賠償その他トラブル解決のルール
10項目は、「トラブル解決のルール(漏えい時の対応方法、損害賠償、合意管轄、準拠法など)」ですね。
例えば、相手の会社がサイバー攻撃を受けて、T社長の会社が預けている秘密情報が漏えいしてしまったというケースを想像しみてください。
まず、この場合、T社長としては、おそらく『直ちに最低限のセキュリティ対策を講じつつも、わが社に連絡して欲しい』、『すぐに協議して、被害拡大防止や再発防止のために、どのように対応していくべきかを話し合いたい』と思うのではないでしょうか。
そこで、こういったルールを「漏えい時の対応方法」として書いておくんです。そうすることで、トラブルに対し『どのように対応・解決していくべきか』がわかりやすくなって、双方において迅速かつ適切にトラブルに対応できるようになるんです。
例えば、相手の会社がサイバー攻撃を受けて、T社長の会社が預けている秘密情報が漏えいしてしまったというケースを想像しみてください。
まず、この場合、T社長としては、おそらく『直ちに最低限のセキュリティ対策を講じつつも、わが社に連絡して欲しい』、『すぐに協議して、被害拡大防止や再発防止のために、どのように対応していくべきかを話し合いたい』と思うのではないでしょうか。
そこで、こういったルールを「漏えい時の対応方法」として書いておくんです。そうすることで、トラブルに対し『どのように対応・解決していくべきか』がわかりやすくなって、双方において迅速かつ適切にトラブルに対応できるようになるんです。
小野弁護士
次に、このトラブルを収拾できても、T社長の会社が損失を被ってしまったときには、『わが社が受けた損失を補償してもらいたい』と思うでしょう? ですから、損害賠償ルールについても書いておくことも大切ですね。
なお、損害賠償ルールについて何も書かない場合であっても、法律に定めるルールの範囲で、損失を回復させることはできます(民法415条、416条など)。逆から言うと、法律とは別のルールで損害賠償を処理したいときには、契約書に書いておかないとダメってことです。
なお、損害賠償ルールについて何も書かない場合であっても、法律に定めるルールの範囲で、損失を回復させることはできます(民法415条、416条など)。逆から言うと、法律とは別のルールで損害賠償を処理したいときには、契約書に書いておかないとダメってことです。
小野弁護士
また、ケースによっては、話し合いでは解決できず、訴訟に発展してしまうこともあります。
こうした場合に備え、『訴訟になった場合、どこの裁判所で争うのか』『どこの国の法律で解決するのか』といったルールについても書いておくことが多いんですよ。
こうした場合に備え、『訴訟になった場合、どこの裁判所で争うのか』『どこの国の法律で解決するのか』といったルールについても書いておくことが多いんですよ。
小野弁護士
T社長
ありがとうございます。契約の段階で、訴訟になった時のルールを書くのは、相手の会社に対して若干遠慮してしまう気持ちもゼロではないけど、お互いのために、きちんと書いておくようにします。
それがいいですね。
小野弁護士
秘密保持契約に収入印紙は必要ですか?
(秘密保持契約における収入印紙の必要性)
T社長
そういえば、NDAを締結するときって、契約書に収入印紙を貼らないといけないんでしょうか?
原則としては、秘密保持契約書には収入印紙を貼る必要はないです。
というのも、収入印紙を貼る必要があるのは、印紙税がかかる特定の文書(=課税文書)に限られているんです。課税文書は20種類あるんですが、秘密保持契約書はそのどれにも該当しないから、印紙は不要なんですよ。
というのも、収入印紙を貼る必要があるのは、印紙税がかかる特定の文書(=課税文書)に限られているんです。課税文書は20種類あるんですが、秘密保持契約書はそのどれにも該当しないから、印紙は不要なんですよ。
小野弁護士
T社長
そうなんだ。じゃあ、印紙代を節約できるんだね。
そのとおりです。ですが、契約書の表題が『秘密保持義務(NDA)』となっていても、その契約内容によっては課税文書にあたると判断されてしまうケースもありますので、やや注意が必要です。
例えば、T社長の会社が相手の会社に対し『1年間、1月ごとに商品1000個を売ること』を目的として、売買基本取引とNDAを1通の契約書で締結したとします。
この場合、印紙税を削減する目的で、表題を『秘密保持契約(NDA)』としても、その中で売買に関するルールを書いてあったら、その契約書は「継続取引の基本となる契約書」(課税文書)にあたると判断されてしまい、最悪、印紙税法に違反してしまうリスクがあるんですよ。
印紙を貼るべきかを迷ったときは、そのNDAが他の契約(継続的売買、請負、営業譲渡、消費貸借など)とまとめて1通として作成された経緯があるのかを確認し、そして、こうした経緯がある場合には、その内容が課税文書にあたるものかをチェックしておくよう、お勧めします。
例えば、T社長の会社が相手の会社に対し『1年間、1月ごとに商品1000個を売ること』を目的として、売買基本取引とNDAを1通の契約書で締結したとします。
この場合、印紙税を削減する目的で、表題を『秘密保持契約(NDA)』としても、その中で売買に関するルールを書いてあったら、その契約書は「継続取引の基本となる契約書」(課税文書)にあたると判断されてしまい、最悪、印紙税法に違反してしまうリスクがあるんですよ。
印紙を貼るべきかを迷ったときは、そのNDAが他の契約(継続的売買、請負、営業譲渡、消費貸借など)とまとめて1通として作成された経緯があるのかを確認し、そして、こうした経緯がある場合には、その内容が課税文書にあたるものかをチェックしておくよう、お勧めします。
小野弁護士
T社長
なるほど、内容によるんですね。印紙を貼るべきか否かについて丁寧に教えてもらえたので、安心しました。
それはよかったです。
小野弁護士
秘密保持契約は、PDFやインターネットなどでも締結できますか?
(電子契約での締結の可能性)
T社長
最近、『契約は紙だけじゃなく電子データでも締結できる』っていう言葉をよく耳にします。これって本当ですか?
はい、そのとおりです。今は紙の書類でなくても、PDFやインターネットを使って締結できるんですよ。このことは、NDAの締結においても同様です。これを一般に『電子契約』って言うんですよ。
小野弁護士
T社長
へえ、そうなんですか。紙じゃないとダメだと思ってました。電子契約ってどんなメリットがあるんですか?
電子契約には、大きく分けて、①迅速な契約締結が可能になること、②契約書管理の負担が減ること、③コストの削減に繋がること、というメリットがあります。
まず、電子契約では、紙のやり取りや印鑑が要らないので、契約締結をスピーディーに行えます。また、企業の規模によらず、どんな会社でも利用できる所もポイントですね。
次に、電子契約の場合、契約書の管理するのがラクになります。紙の契約書と違って、場所を取りませんからね。
また、契約書の数が増えてくると、『あのビジネスに関する契約書はどこに置いたかな?』などと探すの時間が掛かってしまうこともありますよね。電子契約として保管すると、すぐに探している契約書を検索できますし、また1つのビジネスに関連する契約を紐付けて管理しておけるので、そのビジネスの全体像について把握しやすくなるという点でもメリットはありますね。
最後に、電子契約はコスト削減にもつながります。印刷や郵送などにかかる費用を抑えることができますからね。
まず、電子契約では、紙のやり取りや印鑑が要らないので、契約締結をスピーディーに行えます。また、企業の規模によらず、どんな会社でも利用できる所もポイントですね。
次に、電子契約の場合、契約書の管理するのがラクになります。紙の契約書と違って、場所を取りませんからね。
また、契約書の数が増えてくると、『あのビジネスに関する契約書はどこに置いたかな?』などと探すの時間が掛かってしまうこともありますよね。電子契約として保管すると、すぐに探している契約書を検索できますし、また1つのビジネスに関連する契約を紐付けて管理しておけるので、そのビジネスの全体像について把握しやすくなるという点でもメリットはありますね。
最後に、電子契約はコスト削減にもつながります。印刷や郵送などにかかる費用を抑えることができますからね。
小野弁護士
T社長
色々とメリットがありますね。ところで、セキュリティ面では問題ないんですか?
アクセス権限やパスワードの設定を適切に行えば、セキュリティ上の安全性も、ある程度は担保できますよ。
また、タイムスタンプ、電子サインを上手に使えば、電子契約の内容が不正に書き換えられたりしていないかについて、きちんとチェックできます。
また、タイムスタンプ、電子サインを上手に使えば、電子契約の内容が不正に書き換えられたりしていないかについて、きちんとチェックできます。
小野弁護士
T社長
なるほど。わが社でも電子契約の利用を検討してみようかなぁ。
それもいいかもしれませんね。
でも、契約書は、あくまで『自分のやりたいビジネスを実現するための手段である』ということを忘れてはいけませんよ。
契約というのは、決して、スピーディーに締結することが目的ではなく、大事なことは『⑴その契約が自社のやりたいビジネスにとって必要なものか、⑵遵守すべき義務が実際に履行可能な内容であるか、⑶ビジネス上のリスクが自社の予算の範囲内に収まっているか』ということです。
紙媒体にしろ、電子契約にしろ、契約内容をしっかりとチェックしておくよう、おすすめします。
でも、契約書は、あくまで『自分のやりたいビジネスを実現するための手段である』ということを忘れてはいけませんよ。
契約というのは、決して、スピーディーに締結することが目的ではなく、大事なことは『⑴その契約が自社のやりたいビジネスにとって必要なものか、⑵遵守すべき義務が実際に履行可能な内容であるか、⑶ビジネス上のリスクが自社の予算の範囲内に収まっているか』ということです。
紙媒体にしろ、電子契約にしろ、契約内容をしっかりとチェックしておくよう、おすすめします。
小野弁護士
T社長
便利さに目移りしてしまい、うっかり忘れていました。肝に銘じておきます。
弁護士によるチェックは必要ですか?
(外部弁護士にチェックを依頼するメリット)
T社長
NDAって、わが社の法務部で作成したり、チェックしても問題ないのでしょうか?
もちろんです。雛形などを使ってT社長の会社で新しく作ったり、また相手の会社から送られてきたNDAをチェックしていただいても、大丈夫ですよ。
ただ、NDAは、それ単体で結ぶことよりも、他の取引(売買、製造委託、共同開発、買収など)に伴って締結することの方がずっと多いです。
このことから、NDAには『こうしておけばいい』といったテンプレートはなく、個々のビジネスの内容、想定される商流、お互いの開示する情報の内容・性質及びその頻度・量など様々な事情によって、適切な内容が変わってきます。
確かに、NDAは一番多く締結される契約の1つではあるかと思いますが、そのことは決して『この契約が簡単である』ということを意味しているわけではありません。
ですから、外部の弁護士にビジネスの背景も踏まえて、しっかりとチェックしてもらう方が安心だと思います。
ただ、NDAは、それ単体で結ぶことよりも、他の取引(売買、製造委託、共同開発、買収など)に伴って締結することの方がずっと多いです。
このことから、NDAには『こうしておけばいい』といったテンプレートはなく、個々のビジネスの内容、想定される商流、お互いの開示する情報の内容・性質及びその頻度・量など様々な事情によって、適切な内容が変わってきます。
確かに、NDAは一番多く締結される契約の1つではあるかと思いますが、そのことは決して『この契約が簡単である』ということを意味しているわけではありません。
ですから、外部の弁護士にビジネスの背景も踏まえて、しっかりとチェックしてもらう方が安心だと思います。
小野弁護士
T社長
取引ごとにNDAが必要になる場面が多いということは、それだけ『重要な』契約ってことか。先生、NDAのチェックをお願いしてもいいでしょうか?
もちろんです。
小野弁護士
 T社長先生にNDAのチェックをお願いできれば、適切な内容でNDAを締結できるし、仮に相手の会社のもとで漏えいが起きても、損害賠償できるから安心だな。
T社長先生にNDAのチェックをお願いできれば、適切な内容でNDAを締結できるし、仮に相手の会社のもとで漏えいが起きても、損害賠償できるから安心だな。
確かに、適切な内容でNDAを結ぶことができると、漏えいリスクを下げることができますし、損失を適切に補填できる可能性も高まります。
しかしながら、漏えいが起きてしまうと、適切にNDAを締結していたとしても、常にその損失を十分にカバーできるとは限りません。
というのも、民法に基づいて損害賠償を請求する場合、原則としては、T社長の会社サイドにおいて、『その漏えいによって、会社が損失を被ったこと』を証明することになります。ですが、この証明のハードルは決して低いものではないからです。」
小野弁護士: 「やや間違えられやすい所ではありますが、情報漏えいのケースにおいて、実務上もっとも大切なポイントは『漏えい後の責任追及をいかに上手に行うか』ではなく『できる限り漏えいを起こさないようにすること』なんですよ。
ですから、適切にNDAを締結したからといって、安心してはいけませんよ。
そこに書かれたルールを軸にして、社内で『漏えい防止に向けて、どんな対策を講じ、それをどのように運用し、どう行動していくべきか』について、詳細かつ具体的に考えていくことがとても大切なんですよ。
この点については、「秘密情報の保護ハンドブック」(経済産業省)も参考になると思いますので、一度目を通してみるといいですよ。 小野弁護士
小野弁護士
 T社長NDAは、お互いの情報管理に対する大枠のルールを定めたものであって、その内容を具体的に検討していかないと、NDAを締結した真の狙い(=情報漏えいを防ぐこと)を達成することはできないんですね。まさにそうです! こういったポイントについても、これから一緒に考えていきましょう。
T社長NDAは、お互いの情報管理に対する大枠のルールを定めたものであって、その内容を具体的に検討していかないと、NDAを締結した真の狙い(=情報漏えいを防ぐこと)を達成することはできないんですね。まさにそうです! こういったポイントについても、これから一緒に考えていきましょう。 小野弁護士
小野弁護士 T社長ありがとうございます。心強いなぁ。
T社長ありがとうございます。心強いなぁ。「秘密情報の保護ハンドブック」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf
まとめ
NDAというのは、ビジネスにおいて、とても重要な契約ですから、個々のビジネスを踏まえたうえ、適切な内容やタイミングで締結していくことが大切です。また、締結後の情報管理の体制・運用についても、きちんと考えて実施したり、更新していくことも大切です。
目の前にビジネスに適ったNDAを締結していくことは、会社の事業を促進させ、安心かつ効果的に成長していくための「Important key」(=重要な鍵)です。
目の前にビジネスに適ったNDAを締結していくことは、会社の事業を促進させ、安心かつ効果的に成長していくための「Important key」(=重要な鍵)です。
小野弁護士
T社長
よくわかりました。今日はありがとうございました。
いつでも相談してください。NDAはビジネスを守るための大切な一歩です。お互いに信頼できる関係を築きながら、成功に向けて進んでいきましょう。
小野弁護士
T社長
ありがとうございます! これからもよろしくお願いします。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611
WRITER

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」