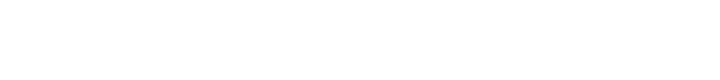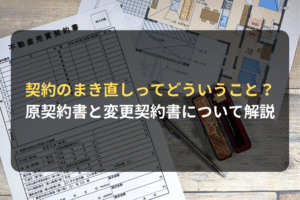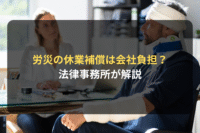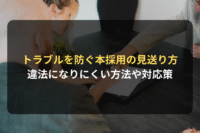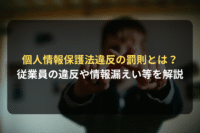- 2024.06.06
取締役会を設置するメリットは何ですか?(会社のビジネスをスムーズにする決議の事項や方法について解説)
目次
取締役会って何ですか?
(取締役会の設置及びその設置のメリット)
取締役会における承認や決議って何ですか?という社長のご質問に対し、弁護士がお答えします。取締役会の決議事項や決議の方法の流れ、決議と報告との違いなどをわかりやすく解説しています。
取締役会とは?
取締役会を置くメリット/デメリットについて
・融資を受けるかどうか、またいくら受けるか
・執行役員や支店長といった重要なポジションに就く人物をだれにするのか、また解任するのか
・支店を新しく設置するのか、またどこに設置するのか
こういった業務執行に必要な決定をする場面では、慎重に決定することも必要かもしれませんが、経営面では迅速な意思決定が必要不可欠ですよね。
ですが、事業の拡大に伴い、株主を広く募集することにより、株主が増えていくと、事業に携わらない一般の方が株主となるケースが増えて、株主の数が多くなってしまう可能性もありますよね。
このように株主が多数に上る状況で、会社の重要な意思決定を株主総会で行おうとすると、株主総会の開催、説明、承認等の手間が重くなってしまい、会社の迅速な意思決定の妨げとなるリスクがあります。
また、事業に携わらない一般の方の中には、配当などの投機を目的とし会社経営にあまり詳しくない株主も大勢います。こうした株主がたくさんいる場で、会社の重要な意思決定を行おうとすると、かえって混乱を招き、このこともまた迅速な意思決定を妨げるリスクの1つとなります。
ですから、取締役会を設置することにより、あらかじめ株主の承認を得ずに議決できる事項を定めておくことができるんですよ。
また、会社にとっては株主の承認なしで決定できる事項が増える半面、株主総会で決定できる事項が減ってしまうため、経営に積極的に参加したい、いわゆる口出しをしたい株主にとってもデメリットといえますね。
- 取締役会と株主総会との違い
-
取締役会と株主総会の違いをまとめると、下記の表となります。見比べてみると、両者は似て非なる機関ということが分かります。取締役会設置会社の場合は、経営に関する決定は取締役会が行い、その取締役会の監督を取締役の選任・解任する権利のある株主総会が行うイメージです。
取締役会 株主総会 構成 最低3名の取締役 株主 決議事項 業務執行に関する事項 会社に関する一切の事項(ただし、取締役会設置会社の場合、法律や定款定められた事項のみ決議) 決議要件 原則、過半数の出席、過半数の賛成 決議する議案によって異なる 招集手続き 原則として1週間前まで 非公開会社:ケースによっては、1週間前またはそれを下回ることができる
(会社法299条1項参照)議事録の残し方 本店に10年間保管
(本店:登記簿上の事業所を指します。
支店:本店から離れた場所にある事業所で、登記がされているものを指します。)本店に10年間保管+支店にも5年間コピーを保管
(本店:登記簿上の事業所を指します。
支店:本店から離れた場所にある事業所で、登記がされているものを指します。)
取締役会では、どんなことを決める?
(取締役会の決議事項の種類・内容)
法定決議事項
①業務執行の決定
②取締役の職務執行の監督
③代表取締役の選定と解職
しかし、実際の取締役会の仕事は多岐にわたります。特に①の業務執行の決定は、経営をしていくうえで決定しなければならない場面が多々あると思います。重要ではない議案まで、その都度、取締役会を開催し、取締役の同意を得るとなると、かえって迅速な経営判断が難しくなってしまいます。
1.重要な財産の処分および譲受け(会社法362条4項1号)
2.多額の借財(会社法362条4項2号)
3.支配人、その他の重要な使用人の選任と解任(会社法362条4項3号)
4.支店、その他の重要な組織の設置、変更、廃止(会社法362条4項4号)
5.社債の総 額、その他社債の募集に関する重要な事項
6.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(会社法362条4項6号)
7.定款の定めに基づく役員責任の免除(会社法362条4項7号)
8.その他の重要な業務執行 (会社法362条4項柱書)
上記で紹介した法定決議事項は、どれも会社の重要な意思決定であり、これらは取締役会で慎重に決定してくださいね。というものです。
例えば、公開会社でない場合の株式の譲渡は、株式を譲渡するときに株主総会で譲受人を決定(「承認」)し、決定をしない場合には株主総会が譲受人を指定する必要がありますが、取締役会設置会社の場合は取締役会が当該株式を取得する譲受人を決定し、決定しない場合には取締役会が譲受人を指定すると定められています(会社法136条以下参照)。
その他にも、株式の分割や、株式の発行、 株主総会の日時・開催場所・目的、取締役の競合取引の承認、取締役の責任の一部の免除(定款で定めのある場合) など、取締役会で決議できる事項はたくさんあります。
承諾と決議との違い
一般には『決議』も『承認』も同じような使い方がされるのですが、法律で明確に区分がされていないため、『決議』は取締役会だけで完結できる内容であり、『承認』は株主総会で承認されて初めて完結できる内容と使い分けられるケースもあります。
- 決議と報告との違い
-
ここまでは、決議事項や承認事項についてお話してきましたが、その他に『報告事項』というものもあります。報告事項とは、取締役会を構成する取締役が、取締役会に対して報告を義務付けられる事項です。会社法363条には、報告を行うべき取締役について、『代表取締役』と『取締役会の決議で選定された業務執行取締役』の2つが挙げられています。つまり、社長兼代表取締役であっても、取締役会への報告義務はあるということです。
『報告事項』は言葉のとおり、取締役会に報告しさえすればよく、その事項を取締役会等で決定する必要はありません。この点について、決議事項や承認事項とは取り扱いが異なります。
具体的には、取締役は、3か月に1回以上、自己の職務執行状況の報告を取締役会に対して行うよう、会社法363条2項で定められています。
取締役会で決議する際には、どういう手続を踏めばいい?
(取締役会決議に関連する会社法上のルール)
決議の要件
ちなみに、もし、10人中6人の取締役が出席して取締役会を開いた場合は、そのうち4人以上の賛成をもって可決することができます。
決議の要件を欠くと、どうなる?
決議って省略できる
(みなし決議、省略決議)
- 取締役会とリモート(オンライン)の活用
- オンラインを活用して、取締役会をリモートで行うことも可能です。次の章でご説明しますが、取締役会議事録の作成について定める会社法施行規則では、取締役会開催場所に存在しない取締役について明記されており、会社法は取締役会の開催場所に存在しないが、取締役会には参加する取締役を想定していると考えることができます。
(会社法施行規則101条3項1号括弧書き)
オンライン開催にあたっては、①協議や意見交換が自由にでき、相手の反応がよくわかること、②各取締役の音声や画像がすぐにほかの取締役に伝わる、この2点を実現でき、その時々に適した意思表明がお互いにできる仕組みが大切です。ビデオ開催が一般的ですが、例えば電話で取締役会を行う場合も、通話をスピーカー状態にして、取締役全員が発言を認識して、会議中意見交換がいつでもできれば問題がないと考えられます。
みなし決議はそもそも取締役会が開催されませんが、リモートの取締役会では取締役会が開催されている点が、両者の違いです。リモート開催を行うメリットとしては、移動費用の軽減や感染症予防、録画機能の活用、資料を各自がダウンロードすることによる、ペーパーレス化の促進などがあげられます。
取締役会における決議の方法や流れ
招集権者
議事進行・運営
議事録の作成・保管
- 取締役会への代理出席や、取締役以外の者の同席の可否
 T社長先程、弁護士が補助として参加できると伺いましたが、たとえば部下を代理人にすることは可能でしょうか?
T社長先程、弁護士が補助として参加できると伺いましたが、たとえば部下を代理人にすることは可能でしょうか?
残念ながら、取締役会において代理人を立てることはできません。取締役と会社の契約関係は委任契約で、会社のために取締役個人が任務を遂行することが必要です。会社の重要な意思決定は、取締役その人だからこそ、任されている業務なんです。あらかじめ賛成・反対の意思が固まっていたとしても、会議中の発言や意見交換も、取締役だからこそできる重要な業務であって、ほかの方に代理させることはできないんです。 小野弁護士
小野弁護士 T社長そうなんですね。だからこそ、みなし決議やオンライン開催を活用する意義がありそうです!
T社長そうなんですね。だからこそ、みなし決議やオンライン開催を活用する意義がありそうです!
議事録って何を書くの?
(議事録に残す情報の具体例、作った議事録の運用方法)
①日時と場所
②報告事項と質疑応答
③決議事項とその内容・結果
④監査役等の意見がある場合はその意見
⑤出席した取締役の氏名
⑥定款やそのほかの方法で議長を定め、議長が存在する場合には議長の氏名
⑦議事録を作成した者の氏名(一般社員でもOK)
など
が挙げられます。
特に、②と③はだれが後から見てもわかるように、できる限り具体的に残しておくことがポイントです。また、法律上の決まりはありませんが、わかりやすく表題をつけることが一般的です。
その他の取締役会設置会社には、取締役の職務を監査・監督 する監査役や監査委員がいるため、株主に簡単に取締役会議事録を見せなくても問題がないので、裁判所の許可を必要としていると考えることができますよ。
ですから、例えば、上場している会社は公開会社に該当するので、上場会社の株主が取締役会の閲覧・謄写をする際には、裁判所の許可が必要になるということですね。
取締役会について弁護士に相談できますか?
(外部弁護士に依頼することのメリット)
まとめ
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」