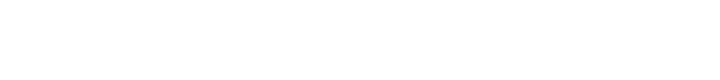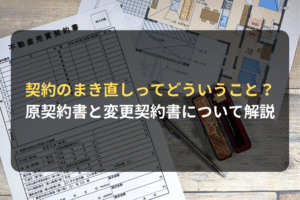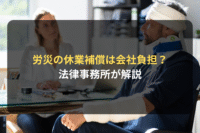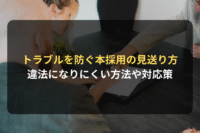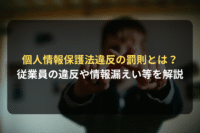- 2022.02.14
プライバシーポリシーはなぜ必要で、どんなメリットがありますか?
目次
- 1 プライバシーポリシーって何ですか? (プライバシーポリシーの個人情報保護法上の機能と、利用規約や免責条項との違い)
- 2 プライバシーポリシーは作った方がいいですか? (プライバシーポリシーの作成が必要な理由、作成しておくメリット)
- 3 プライバシーポリシーには何を書けばいいんですか? (プライバシーポリシーの中に、テンプレートとして記載されることの多い事項や項目)
- 4 その他に、プライバシーポリシーに書くことはありますか? (プライバシーポリシーの中に、追記されることのある事項や項目)
- 5 プライバシーポリシーを作成するときに注意することはありますか? (プライバシーポリシーの作成上の注意点)
- 6 プライバシーポリシーの作成について弁護士に相談できますか? (プライバシーポリシーの作り方やその方法)
- 7 まとめ
プライバシーポリシーって何ですか?
(プライバシーポリシーの個人情報保護法上の機能と、利用規約や免責条項との違い)
プライバシーポリシーはなぜ必要なの?どんなメリットがあるの? という社長のご質問に対し、弁護士が会話形式で分かりやすく解説します。

例えば、お客さんに向けて商品を売ったり、サービスの提供を行う場合には、お客さん側から、その氏名や住所、連絡先などの情報を預かるでしょうし、また、集客などの取引成立前の段階においても、相手の個人的な情報を預かることもありますよね。さらに、ウェブサイトを訪問した人から、サイト内でどう行動したか等の情報を収集していることもあります。
これらの情報は、会社のものではなく、『お客さん等から預かっているもの』として考えられています。ですから、プライバシーポリシーを通し、お客さんに向けて、これらの情報の取扱いについて会社側の方針を伝えておくんです。
さらに、こうした個人情報を、目次やリストなどを作りお客さんごとにまとめて、いつでも検索可能な状態にして取扱っている会社等については、「個人情報取扱事業者」と呼ばれています。個人情報を預かってビジネスを行う会社の多くは、この個人情報取扱事業者にあたると考えてよいでしょう。
- 個人情報をめぐる世界の動向
- インターネットの普及により、大量のデータ(個人情報を含む)が国境を超えてやり取りされる時代になり、これに伴い、個人情報が漏えいする事件も増えています。こうした状況の中、ヨーロッパでは、2016年4月27日、EUデータ保護指令(1985年発令)よりもさらに厳しい内容のEU一般データ保護規則(GDPR)が採択されました。また、この採択に続くように、日本の個人情報保護法改正(2022年4月1日施行)、アメリカ合衆国カルフォルニア州のCPRA(2023年1月1日一部施行)など、多くの国・地域で、個人情報保護ルールを厳しくする方向で見直す動きが見られます。
プライバシーポリシーは作った方がいいですか?
(プライバシーポリシーの作成が必要な理由、作成しておくメリット)
ビジネス1つを行うにしても、取引の履行や集客など様々な場面で、企業は、お客さんから個人情報を預かります。特に最近ですと、ウェブサイトにアクセスした人たちの行動パターンを分析するシステムを導入して、集客率アップを狙う会社が増えています。ですから、一般的には、個人情報を預かる機会が前よりも多くなったと言えるでしょう。
他方で、このことは、お客さん側にしてみると、『どのタイミングで、何のために、どういった情報が取得されて、それがどのように使われているのかが、前よりもわかりづらくなった』ということです。つまり、ビジネスのあり方が、お客さんにとって、不安を感じやすいものへと変わってきているということです。
プライバシーポリシーをしっかりと書くことは、『わが社では、お客さんの情報をむやみに入手したり使ったりしていませんので、安心して商品やサービスを購入してください』というメッセージを公表して、こういったお客さんの不安を解消してあげることなんです。
そして、これをしっかりとやっていくと、お客さんやリピーターを増すことができ、会社のビジネス基盤を固めていくことができます。
もし、プライバシーポリシーをきちんと書かないと、お客さんが会社に対し不安を持つようになり、クレームや問合せが入る回数が増えてしまい、ケースによっては、国から注意されてしまうこともあります。
このように個人情報の取扱いをめぐり、お客さんや行政への対応が増えてしまうと、従業員は疲れてしまったり、自分が働いている会社に自身を持てなくなってきたりなどしてモチベーションが低下してしまい、他の会社に転職するきっかけになってしまうこともあります。
逆から言うと、しっかりとしたプライバシーポリシーを用意しておくと、社員さんの『会社のために頑張りたい』というモチベーションをキープできるんです。
そして、社員さんのモチベーションのキープに成功すると、長く会社のために働いてもらえるので、T社長の会社にとって必要なノウハウやスキルを豊富に持っている社員さんをたくさん育てることができますし、これに伴い新しいビジネスに挑戦するハードルも下がります。
さらに、『この会社で働いていて楽しい』と思ってもらえる状態を維持していくと、会社の評判も上がるので、将来において、欲しい人材を獲得しやすくなるというメリットもあるんですよ。
シンプルに言ってしまうと、個人情報保護法には、『個人情報を守るためのルール』が書かれているんです。
そして、『個人情報を守る』ためには、会社とお客さんが協力して、お互いに適切な運用・管理ができているのかを確認していくことが望ましいと言えます。ですから、この法律では、会社に対し、お客さんに向けていくつかの項目を知らせておくことを義務付けており、お客さん側からも会社の運用等が適切かをチェックできるようにしています。
ですから、プライバシーポリシーには、この義務を果たすこと、つまり『個人情報保護法を守りながらビジネスを行う』という意味があるんですよ。
- プライバシーポリシーと利用規約や免責条項の違い
-
プライバシーポリシー、利用規約、免責条項は、いずれも事業上のリスクを管理したり、またユーザーとのトラブルを低減するものとして、ビジネスをしていく上でとても大切なものではありますが、その用途や法的拘束力に違いがあります。
「プライバシーポリシー」の公表というのは、法令遵守のために、『個人情報を適切に扱っています』という会社のメッセージをユーザーに伝えることにとどまります。ですから、仮に公表しても、直ちにプライバシーポリシーの内容が、事業者とユーザーとを拘束するルール(=合意)となるわけではありません。
他方で、「利用規約」「免責条項」というのは、サービス等の利用方法や遵守事項、利用規約の変更手続の内容や方法、損害賠償の有無や範囲などの詳細を定めたもので、ある種、こういったサービス等についての契約書のようなものです。ですから、事業者としては、サービス提供の際に、ユーザーにこれらの規約・条項に同意してもらったり、また、ユーザーに対しこれらの規約等を前もって表示しておくことが一般であり、これにより、規約等の内容が、事業者とユーザーとを拘束するルール(=合意)になります。なお、会社によっては、プライバシーポリシーを利用規約の一部として定めている所もあり、この場合には、プライバシーポリシーの内容も、事業者とユーザーとを拘束するルールになります。
プライバシーポリシーには何を書けばいいんですか?
(プライバシーポリシーの中に、テンプレートとして記載されることの多い事項や項目)
しっかりと理解するために、次の「プライバシーポリシー(案)」を見ながら、どの説明していきますね。
あとは…、そうですね。わかりやすいように、ここでは、このプライバシーポリシー(案)を「本ポリシー」と呼びましょう。
プライバシーポリシー(案)
当社は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。なお、令和5年法律第32号による改正、令和6年2月16日を施行日とする。)に基づく個人データの適切な取扱いを行えるよう、次のとおり、プライバシーポリシー(以下「本ポリシー」という。)を定めます。
第1条(会社情報)
商号:株式会社〇〇〇〇
所在地:〒〇〇○―〇〇〇〇
〇県○市○町○番地~
代表者名:代表取締役 甲川 乙蔵
第2条(定義)
「個人情報」、「個人データ」など、本ポリシーで用いる文言は、個人情報保護法第2条の定義に従って解釈されるものとする。
第3条(法令およびガイドラインの遵守)
当社は、個人情報保護法その他の法令、個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインその他のガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守して、個人データを適正に取り扱います。
第4条(個人情報の取得)
当社において、個人情報を取得する際には、本ポリシーなどを通じ、あらかじめ利用目的(4条)を公表または通知して、適法かつ公正な方法で行います。
当社は、当社ウェブサイトにCookie(クッキー)を設置し、これにより取得した情報(以下「Cookie情報」という。)を、当社の保有するお客様の他の情報と紐付けて、取り扱うことがあります。この場合、本ポリシーに沿って、個人情報と同様に適切に取り扱うものとします。なお、Cookieとは、ウェブサイトが利用者のコンピュータに格納する微細なデータファイルを指し、利用者のブラウザを通じて特定の情報を記録・保持する技術をいいます。
なお、当社または第三者の広告配信事業者のcookieに関する取扱いの詳細については、以下のページから、当社のCookieポリシーをご覧ください。
○○○○(URL)
第5条(個人情報の利用)
当社は、次の目的において、個人情報を利用します。
【利用目的の一例】
①お客様と当社との取引に基づき、当社に求められる商品やサービスの提供、これに付随する事務処理のため ②お客様が参加されたキャンペーンやイベントに関するご連絡のため ③商品やサービスの改善・向上、新たな商品やサービスの開発のため ④商品やサービスのキャンペーン等の情報をはがきや電子メールなどで提供するため ⑤お客様からご請求やお問合せがあったときに、ご本人様確認を行うため ⑥お客様から、当社のウェブサイトの特定のページへのアクセス申請や、お客様のアカウントへのログイン申請などがあったときに、ご本人様認証を行うため
きなどに、ご本人様認証を行うため
第6条(個人データの第三者提供)
当社は、個人情報保護法第27条第1項各号に定める場合を除き、お客様からの同意を得ることなく、第三者(他の法人・個人など)に対し、お客様の個人データを提供しません。
【オプトアウト方式】
ただし、当社は、個人情報保護委員会に届出をした上で、次の内容に従い、お客様からの利用停止の求めがあるまでの間に限り、お客様の同意なく、第三者に対し、お客様の個人データを提供することがあります。なお、当社の名称、住所、代表者名については、第1条をご覧ください。
(1)第三者提供の目的
第5条に定める利用目的をご覧下さい。
(2)対象となる個人データ
〇〇〇〇
(3)対象となる個人データの取得方法、提供方法
〇〇〇〇
第7条(個人データの共同利用)
当社は、お客様の個人情報を、次のとおり、共同利用します。
(1)対象となる個人データの項目
〇〇、○○
(2)共同利用者
〇〇社、その他当社グループ会社
(3)利用目的
○○○○
(4)個人データの管理責任者
商号:株式会社〇〇〇〇
所在地:〒〇〇○―〇〇〇〇
○県○市○町○番地~
代表者名:代表取締役 ○○ ○○
第8条(安全管理措置に関する事項)
当社では、個人データについて、漏えい、滅失または毀損の防止、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じています。また、個人データを取り扱う従業者や委託先に対しても、必要かつ適切な監督を行っています。当社では、セキュリティの一環としてSSLを導入し、お客様と当社との個人情報のやり取りを暗号化して行う体制を整え、お客様の個人情報の保護に努めています。
第9条(開示等のご請求)
お客様において、本ポリシーに定める求めや、その他、利用目的の通知の求め(個人情報保護法32条2項)、開示請求(同法33条1項)、訂正等の請求(同法34条1項)、利用停止等の請求(同法33条1項3項5項)をされる場合、当社は、当社の指定する方法により、ご本人様確認をいたします。その後、以下の手続に沿って、対応します。
【手続】(一例)
(1) お客様からの請求を受け付けた日から、○○日以内に、請求の当否について回答を書面により発送します。
(2)この発送は、お預かりしているお客様の住所宛に行います。もし、発送先について、変更のご希望があるときは、請求の際に、その旨をお申し向けください。
なお、本条のご請求については、下記「ご請求先」宛に、メールまたは郵送によって、ご連絡ください。また、お客様からのご要望に応じて、当社において、利用目的の通知の求め、開示請求、訂正等の請求、利用停止等の請求について調査・対応する場合には、1つの請求ごとに、手数料○○円がかかります。
ご請求先
〒〇〇○-○○○○
(住所)○県○市○町○番地
株式会社○○○○ お問合せ窓口
E-maiアドレス 〇〇〇〇
第10条(その他のお問合せ)
お客様において、個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせについては、当社のお問い合わせフォーム(URL)により、ご連絡ください。
制定日:202○年○○月○○日
最終更新日:202○年○○月○○日
①前文(本ポリシー第1条)
前文っていうのは、要するに、『個人情報へのしっかりとした理解をもって、お客さんの情報を適切に取り扱います』っていう会社の真摯な姿勢を伝える文章のことです。
お客さんから個人情報を預かってビジネスをするためには、前提として、お客さんの信頼を獲得していくことが必要ですよね。ですから、前文を通して、「わが社では個人情報を大切に扱っていますよ」というメッセージを伝えるわけです。
前文をしっかりと作っておくと、お客さんに、会社に対してクリーンかつ誠実なイメージを持ってもらえるので、「この会社の商品・サービスを利用しよう」と思ってもらいやすくなるんですよ。
②定義(本ポリシー第2条)
定義をきちんと決めておくと、これらの指針がよりはっきりとするので、会社もお客さんも行動しやすくなるんです。
なお、定義を全部書き写すと、手間と感じたり、プライバシーポリシーが読みづらくなると感じる場合には、本ポリシー第2条のように、「本ポリシーにおいて用いる文言は、個人情報保護法第2条の定義に従って解釈される」などと書いてしまってもokです。
③会社情報(本ポリシー第3条)
令和2年にあった個人情報保護法改正で、保有個人データを取り扱う事業者に対し、いくつかの事項について、本人の知りうる状態にしておくことが義務化されました。そして、当該事項の1つが、この「会社情報」なんです。
つまり、法律を遵守するために、プライバシーポリシーに会社情報を書いておく必要があるんですよ。
シンプルに言ってしまうと、会社において、直接お客さんから預かった情報については、そのほとんどが『保有個人データ』に該当するでしょう。
こういった情報をきちんと書いておくことで、お客さんとしては、『何か問題があったときに、誰に連絡すればいいのか』を知ることができるので、安心してT社長の会社と取引ができるんですよ。
④個人情報の取得方法(本ポリシー第4条)
法律では、事業者に対し、お客さんなどの個人情報を入手する際は適切な手段を用いることを求めています。ですから、プライバシーポリシーを通して、念のためお客さんに向けて『わが社でお客さんの情報を取得するときは、適法かつ正当な手段を使っています』というメッセージを伝えておくんです。
これらのCookie情報は、氏名・住所などの情報とは違って、それ単体では、どのお客さんの情報なのかを識別することが難しいものが多いので、日本の法律に限定して話すと、「個人情報」に該当しないことも多いです。
しかしながら、こうしたサイト内の行動パターンやカート内の履歴などの情報であっても、その対象となったお客さんと紐付けて利用される場合には、それが誰の情報なのかを識別できるものへと変わりますので、「個人情報」として取り扱わないといけません。
ですから、もし自社のウェブサイトでCookieなどを使って、お客さんの行動パターンや、お客さんが購入(または予約)した商品・サービスの履歴といった情報を取得する場合には、本ポリシー第4条後段のように、『Cookie情報であっても「個人情報」として取り扱うことがある』旨を確認的に書いておくことを、お勧めします。
なお、一般に、EUにおける個人情報保護法に該当する指令を「GDPR」と呼び、カルフォルニア州における個人情報保護法に該当する州法を「CPRA」と呼びます。
GDPRやCPRAはまさにこの例外であり、T社長の会社の所在地がEUやカリフォルニア州以外(例えば、日本など)にあったとしても、これらの地域や州の人たちから個人データを入手する際には、これらの法が適用されることがあります。もし、これらに違反してしまうと、巨額の損害賠償などのペナルティが課せられるおそれがあります。
会社にとって、ウェブサイトに流入した人がどこの国から来たかなどを逐一確認するのは難しく、Cookieを使って情報を入手していると、知らず知らずのうちに、EUやカルフォルニア州の人たちの情報を取得してしまっているといったことも起こりえます。加えて、GDPRやCPRAにおいては、日本法の場合と比べて、Cookie情報も『個人を識別できる情報(=個人データ)』として補足される傾向が強く、GDPR等が適用されてしまうリスクが高いです。
ですから、自社ウェブサイトにCookieを設置する際には、例えば、⑴ ウェブサイト訪問者に向けて、Cookieバナーを表示しておき、これについて適切に同意を得られる仕様にしておき、また、⑵ 下記のことを、プライバシーポリシーに直接書き込んだり、またはプライバシーポリシーとは別にCookieポリシーを作成しそのページのリンクをわかりやすい場所に貼っておくといいですよ。
▪Cookieの種類ごとの定義
▪利用目的
▪保存期間
▪Cookieを拒否する(=無効にする)方法
など
なお、GDPR等の外国法との関係では、その他にも注意すべき事項が多くありますので、特に欧州やカルフォルニア州などへの海外展開をお考えのときには、念のため専門の弁護士に相談しておくことを、おすすめします。
⑤利用目的(本ポリシー第5条)
したがいまして、まずは『どういったビジネスシーンで、何の目的に、個人情報を使うのか』についてしっかりとイメージしながら、そのイメージを文章に起こしてみましょう。それができたら、最後に、読み手の立場になってイメージが伝わる文章になっているかをチェックするといいですよ。こうした工程を踏むことが、「利用目的」を書くことが大切なポイントですね。
ですから、この場合、「お客様と当社との取引により、当社に求められる商品やサービスの提供、これに付随する事務処理のため」といったように、お客さんがイメージをしやすいように、書いておけるとよいですね。
本ポリシー第5条の書き方も参考になるかと思いますので、あとで一覧してみてください。
⑥個人データの第三者提供(本ポリシー第6条)
まず、前提として、お客さんから預かった個人情報を他の会社に渡す際には、原則としては、そのお客さんの同意が必要です。個人情報はあくまで『預かっているもの』ですので、これを別の誰かに渡すのであれば、本人の同意を必要というわけです。
つまり、一定の手続を踏むと、お客さんから「他の会社に提供しないでください」って言われるまでの間、お客さんの同意を得ずに、第三者提供できるんですよ。
これは、『お客さんのプライバシー保護を図りながら、個人情報の有効活用を促進する』というコンセプトで作られた制度で、「オプトアウト」と呼ばれています。
というのも、第三者提供をした会社は、法律上、提供先の会社を適切に監督する義務が生じます。ですから、もし提供先で漏洩などが生じた際には、法令違反のリスクに晒されてしまいます。また、お客さんからも、クレームを入れられたり、責任追及されてしまうこともあるでしょう。
まとめると、その第三者提供が、会社にとってどうしても必要なものなのか、また、提供先の会社は情報管理体制がきちんとしているのかといった点について、あらかじめよく検討しておくことが、とても大切なポイントです。
⑦個人データの共同利用(本ポリシー第7条)
簡単に言うと、「共同利用」っていうのは、お客さんの情報を、他の会社と一緒に使うことを言います。ただ、これをする際には、法律に基づいて、前もってやっておくべきことがあります。
この伝え方については、本人に直接通知することもできますし、また、プライバシーポリシーに書いておき、それを公表する方法でもokです。
なお、実務ですと、個々に通知することの面倒さを嫌って、プライバシーポリシーに書いておく会社が多いように思います。
⑧安全管理措置について(本ポリシー第8条)
まず、個人情報保護法は、事業者に対し、お客さんなどから預かっている個人データについて、これをきちんと丁寧に管理するよう、義務付けています。これを「安全管理措置」と言います。
⑨利用目的の通知、開示等、訂正等、利用停止等の請求(本ポリシー第9条)
そして、これらの請求のハードルを下げるといった趣旨のもと、個人情報保護法は、事業者に対して、どういった手続に則り、どこに請求すればよいのか、また請求に際し手数料が生じるときはそれがいくらなのか等を、お客さんにきちんと知らせておくよう、義務付けています。
ですから、この義務を果たすために、プライバシーポリシーに、こういった事項を書いておくことが多いんですよ。
⑩個人情報の取扱いについての質問やクレームなどのお問合せ(本ポリシー第10条)
要するに、会社が扱っているお客さんの情報について、そのお客さんが質問やクレームなどをするときには、どこに連絡すればいいのかを教えておく必要があるってことです。
これを実施する方法の1つとしては、プライバシーポリシーに、問合せ窓口の連絡先を書くことですね。
例えば、「ご質問やご不明点がございましたら、以下の連絡先(窓口)までお気軽にお問い合わせください。」として、会社の電話番号やメールアドレス、担当者名を書いておくんです。
- オプトアウトとは
-
『オプトアウト』とは、一般には自分が他人から情報を受領するか否かや、他人が自分の情報を第三者に渡すのを許すか否かといった選択を迫られた際に、自分が「No」と意思表示することを言います。
この点について、個人情報保護法の場合には、『後になって「やっぱりNoにします」と意思表示できることを条件にして、他人が自分の情報を第三者に渡すのを許すこと』を、オプトアウトとして説明しています(同法27条2項)。このオプトアウトを利用する際には、第三者提供を行う事業者(提供元事業者)において、対象となるデータの項目やその取得・提供に関する方法、どんな方式に則り「No」と主張できるのか等について、あらかじめ本人に対し通知し又はプライバシーポリシーなどに書いて公表しておく義務があります。
なお、これらの義務の遵守に加えて、個人情報保護委員会に届出をしておく必要もありますので、ご注意ください。
その他に、プライバシーポリシーに書くことはありますか?
(プライバシーポリシーの中に、追記されることのある事項や項目)
というのも、プライバシーポリシーは、お客さんにお知らせするためのものであって、お客さんと合意するものではないからです。
ですから、プライバシーポリシーに、サービスの提供に関し免責事項を書いて公表しても、これだけで、その免責を受けられるわけではありません。
プライバシーポリシーに書くことで免責される事項とは、会社とお客さんの双方において暗黙の了解があると言えるもの、つまり『一般的に、お客さんの自己責任と考えられているもの』になるでしょうね。
もっと詳しく!
Gogleアナリティクス、Googleアドセンスと同意取得
こういったサービスって、わが社のサイトにアクセスした人たちの行動パターンなどを取得して行うことになると思うんですが、わが社の方でお客さんから同意を得ておく必要があるんですかね?
GoogleアナリティクスやGoogleアドセンスを使った場合、Googleが直接お客さんから情報を取得することになります。つまり、個人情報の流れとしては『お客さん→Google』なんですよ。そうすると、同法との関係では、T社長の会社の方で同意取得すべき義務はありませんよね。
でも、仮に、Googleがウェブサイト上で取得した情報の中に、EU圏からアクセスした人の個人情報が含まれていると、GDPRが適用されるおそれがあります。
GDPRによると、個人情報を直接取得しておらずとも、その取得について目的や方法を決定をした者(「controller」(GDPR第4条⑺))は、本人から同意取得すべき義務があるんですよ(GDPR第7条1項)。そして、Googleアナリティクス等を自社ウェブサイトに導入した会社は、この「controller」と見なされることが多いので、GDPRへの違反がないように、会社の方で同意取得しておくのが無難でしょう。
また、GoogleアナリティクスやGoogleアドセンスの規約(Googleアナリティクス利用規約、Googleアドセンスヘルプ)によると、T社長の会社において、プライバシーポリシーの中に一定の事項を書いておく必要があります。これを怠ると、Googleから『契約違反だ』と言われてしまうので、こちらも忘れないようにしましょうね。
プライバシーポリシーを作成するときに注意することはありますか?
(プライバシーポリシーの作成上の注意点)
というのも、プライバシーポリシーとは、お客さんから『預かっている』個人情報についてのルールです。ですから、会社で行うビジネスに沿って、誰から、どのような個人情報を預かっているかをはっきりとさせておくことが必要なんです。
また、この洗い出しをちゃんとやっておくと、自社ビジネスとの関係で、個人情報をどんなふうに使うことを想定しているのか、これに伴って他の会社に提供する予定があるのかなどの点についても明らかになってきます。そうすると、プライバシーポリシーに何を書くべきなのかを適切にイメージできるようになり、結果として、自社にとって最適解のプライバシーポリシーを作ることができるんですよ。
とても基本的なことではありますが、これがちゃんとできている会社は、個人情報の取扱やお客さんからの請求や問合せに対し、テキパキと行動できますので、会社の業務効率を落とすことなく、法律を遵守し、会社の評判を上げていくことができるんですよ。
なお、個人情報保護法についてのガイドラインによると、会社の運営するウェブサイトのトップページから 『1 回程度』のクリックでアクセスできる所に、プライバシーポリシーを設置しておくのが望ましいとのことですね。
- 個人情報保護法については、国がガイドラインで詳しい説明をしていますので、もっと詳しくしりたい場合は、ぜひ参照してみてください。
-
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
プライバシーポリシーの作成について弁護士に相談できますか?
(プライバシーポリシーの作り方やその方法)
ただ、そうなると、おそらくインターネットなどから、プライバシーポリシーの雛形を引っ張ってきて、作成していくことになるかと思います。雛形は無料のものが多いので費用的にはよいのですが、こういった雛形はあくまで『一般的なもの』であり、必ずしもT社長の会社のビジネスに沿った内容であるとは限りません。
雛形をそのまま使ってしまうと、もしかすると、T社長の会社で実際に行っているビジネスとプライバシーポリシーの内容に食い違いが起きてしまい、現場が混乱するといった事態にもなりかねます。
ですから、できれば企業法務について詳しい弁護士に依頼して、自分の会社に合ったプライバシーポリシーのたたき台を作ってもらうことを、お勧めします。
ですから、自分の会社が、どういったビジネスを行っており、また将来に向けてどうしていきたいのかを、ハッキリとさせ、それを弁護士としっかりと共有していただくことが、充実したプライバシーポリシーを作っていく上で、とても重要なポイントなんです。
まとめ
その他にも、会社のビジネスをイメージしながら、プライバシーポリシーどう書くのがよいのかをしっかりと考えてみると、意外にも、いま会社で採用している情報管理体制をグレードアップさせるヒントが見つかったりもします。
つまり、プライバシーポリシーの大切さを認め、これを正しく、そして丁寧に書くことは、T社長の会社のビジネスを成功させるパワーになるんです。
■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解のうえ、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、ぜひ専門家にご相談ください。
- ご相談はこちらから!
- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。
- メールでスピード相談
24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」